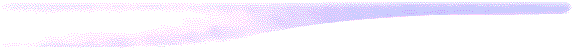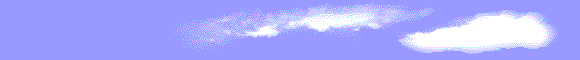
私の仕事
1982年以降の仕事です。
|
1)執筆 【単行本単著】 ●堤 研二(2011.2.24):『人口減少・高齢化と生活環境:山間地域とソーシャル・キャピタルの事例に学ぶ』、九州大学出版会、xvi+P.295。【平成22年度日本生命財団学術書出版助成】。ISBN:978-4-7985-0035-5 ●堤 研二(2015.9.24):『人口減少・高齢化と生活環境:山間地域とソーシャル・キャピタルの事例に学ぶ』(新装版)、九州大学出版会、xvi+P.295。ISBN: 978-4-7985-0166-6 【単行本共編著】 ★Kobayashi, K., Matsuo, Y. and Tsutsumi,
K.(eds.)(1999.12):“Local Knowledge and Innovation: Enhancing the Substance of
Non-Metropolitan Regions, ”MARG(Kyoto),357P(執筆部分:Tsutsumi, K.“An Essay on Counterpolicies
to Depopulation: Challenges for/from Depopulated Regions, ”pp.249-255.ほかCh.1, pp.1-4を共編者で執筆). ●人文地理学会 編(2013.9.30):『人文地理学事典』、丸善出版、xxii+P.761(編集委員として編集を担当)。 ●豊中市スポーツ少年団(2015.6.1)『豊中市スポーツ少年団50年の歩み:1963 ~ 2013』、豊中市スポーツ少年団本部、ii+P.125(豊中市スポーツ少年団創設50周年記念誌編集部会委員長(編集責任者)として編集・執筆を担当)。 【学会誌(レフェリー付き)所収】 ●堤 研二(1987.6):「過疎山村・ ●堤 研二(1989.12):「人口移動研究の課題と視点」、『人文地理』(人文地理学会)第41巻6号、pp.41-62。 ●堤 研二(1992.4):「ドイツ社会地理学の一系譜:社会地理学論争の周辺」、『人文地理』(人文地理学会)第44巻2号、pp.44-65。 ●堤 研二(1995.9):「産業近代化とエージェント:近代の八女地方における茶業を事例として」、『経済地理学年報』(経済地理学会)第41巻3号、pp.17-37。 ★高津斌彰・水内俊雄・実清隆・水岡不二雄・堤 研二(1995.3):「空間編成論と日本の社会・経済地理学:D.ハーヴェイの理論を中心に(1994年秋季学術大会シンポジウム)」、『地理学評論』(日本地理学会)第68(A)巻3号、pp.180-190。 ●堤 研二(1998.6):「離島空港をめぐる諸問題:隠岐空港を事例として」、『地域地理研究』(地域地理科学会)第3巻、pp.57-66。 ★Mizuoka, F., Mizuuchi, T., Hisatake, T.,
Tsutsumi, K. and Fujita, T.(2005.6)“The Critical Heritage of
Japanese Geography: Its Tortured Trajectory for Seven Decades, ”Society and Space (Environment and Planning, Ser.D)23-3, pp.453-473. (電子ジャーナルによるフルテキスト: http://www.envplan.com/epd/fulltext/d23/d2204r.pdf) 【研究書(レフェリー付き)所収】 ●Tsutsumi, K.(1995.12)“Regional
Identity in Japanese Centralism, ”in Winfried
Flüchter (ed.)“Japan
and Central Europe Restructuring: Geographical Aspects of Socio-economic,
Urban and Regional Development, ”pp.240-250, Verlag Harrassowitz (Wiesbaden). ●Tsutsumi, K.(1998.8):“Depopulated
Regions in Japan: A Case Study on the Former Coal-Mining Region, Takashima,
Nagasaki Prefecture, Japan, ” in Lennart Andersson
and Thomas Blom (eds.)“Sustainability and Development: On the Future of Small Society in
a Dynamic Economy, ”
pp.230-235, University of Karlstad (Karlstad, Sweden). ●Tsutsumi, K.(2002.11): “Regional Functions and Information Technology in Depopulated
Areas: Some Cases in Japan, ” Communication and
Regional Development (The International Symposium
on Communication and Regional Development), pp.183-189 (University of
Karlstad, Karlstad Sweden). ●Tsutsumi, K.(2005.6) : “ Fundamental Functions of Living, Social
Capital and Agents in a Small Community: A Case
in Depopulated Areas in Japan, ”
Kobayashi, K., Westlund, H. and Matsushima, K.(eds.) “Social Capital and Development Trends in
Rural Areas, ” pp.131-138(Chapter 8),
MARG(Kyoto). ●Tsutsumi, K.(2005.):“Aging, Landscape, Restructuring
and Conflicts in an Old New Town: Senri New Town in Osaka Metropolitan Area, ” Thomas Feldhoff and Winfried Flüchter (eds.) “Shaping the Future of Metropolitan Regions in Japan and Germany:
Governance,
Institutions and Place in New Context” (The 9th
Japanese-German Geographical Conference, Ruhr University Bochum, Bochum,
Germany, published in Duisburg): No1:ISSN 1861-3225, pp.171-177. ●Tsutsumi, K.(2006.3) : “Social Ties in Communities: Some Rural and Urban Cases in Japan, ” Ito,
K., Westlund, H., Kobayashi, K. and Hatori, T.(eds.)“Social Capital
and Development Trends in Rural Areas Vol.2, ” pp.115-127(Chapter 9), MARG(Kyoto). ●Tsutsumi, K.(2008.9):“Drastic Depopulation, Town Renovation and
Social Capital on a Coal Mining Island, ”Kobayashi, K., Westin, L.
and Westlund, L. (eds.)“Social Capital and Development Trends in Rural Areas Vol.3” (ISBN:
978-91-7264-669-8)pp.47-59(Chapter 4), CERUM(Center for Regional Science,
Umeå University, Umeå , Sweden). ●Tsutsumi, K.(2009.3):“Social Ties and “Social Capital” in Areas under Shrinking
and Marginalization process in Japan, ”Kobayashi K., Tamura, T., Westlund, L. and Jeong Hayeong (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.4”
(ISBN: 978-4-907830-06-9) pp.19-29(Chapter 3), MARG(Marginal Areas Research
Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto, Japan). ●Tsutsumi, K.(2010.8):“Settlement Activities and Social
Capital of Depopulated Rural Areas in Japan, ” Westlund H. and Kobayashi, K. (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.5”
(ISBN: 978-91-633-7221-6) pp.93-106(Chapter 7), MARG(Marginal Areas Research
Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto, Japan),
supported by Swedish Board of Agriculture
(Jordbruk-sverket), Royal Institute of Technology (KTH), and RUREG (Research
Unit for Rural Entrepreneurship and Growth) of Jönköping International
Business School of Jönköping University, Sweden, and distributed by RUREG. ●Tsutsumi, K.(2011.2):“Social Capital in Rural Studies
in Japan: An Examination of Actual Forms of Social Capital Especially in
Rural Japan, ”Kobayashi K., Westlund,
L. and Jeong Hayeong (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.6”
(ISBN: 978-4-907830-07-6) pp.129-139(Chapter 10), MARG(Marginal Areas
Research Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto,
Japan). ●Tsutsumi, K.(2012. 2):“Formation of the Tourist Industry
at the Core of a Shrine through the Modern and Present Eras: Social Capital
and Agent around Dazaifu, ” Kobayashi K., Westlund, L. and Jeong Hayeong (eds.)“Social Capital and Development Trends in Rural Areas Vol.7” (ISBN: 978-4-907830-08-3)
pp.69-85(Chapter 6), MARG(Marginal Areas Research Group, Graduate School of
Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto, Japan). ●Tsutsumi, K.(2012. 2):“Interscale and Interlevel
Problems of Research on Social Capital in Rural Japan, ” Kobayashi, K., Westlund, L. and Jeong Hayeong
(eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.7”
(ISBN: 978-4-907830-08-3) pp.241-256(Chapter 15), MARG(Marginal Areas
Research Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto,
Japan). ●Tsutsumi, K.(2013.12):“Mountainous Areas in Japan and Forest Town Management Model (FTMM), ” Westerdahl, S., Westlund, H. and Kobayashi, K. (eds.)“Social Capital and Development Trends in Rural Areas Vol.8” (ISBN:978-91-86345-48-8)pp.
245-254(Chapter 15), CENSE (Center for Entrepreneurship and Spatial
Economics), Jönköping International Business School of
Jönköping University, Sweden. ●Tsutsumi, K.(2014.7)“Marginality
and Sustainability of Mountainous Village and Forestry,” Matsushima, K., Westlund, H. and Kobayashi,
K. (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.9”
(ISBN:978-4-907830-09-0)pp. 39-48(Chapter 5), MARG(Marginal Areas Research
Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto, Japan). ●Tsutsumi, K.(2015. 12)“Junior Sports Club and Regional Social Capital in
Japan,” von Friedrichs, Y., Westlund, H. and
Kobayashi, K. (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.10”
(ISBN:978-91-86345-64-8) pp.69-75 (Chapter 6), Jönköping International Business School of Jönköping University, Sweden. ●Tsutsumi, K.(2016. 3)“Trial for Sustaining Regional Life in a
Peripheral Island Town: A Case of Okinoshima -,” Kobayashi, K., Wetlund, H., Matsushima, K.
and Ohno, S. (eds.)“Social Capital and Development Trends in
Rural Areas Vol.11”
(ISBN: 978-4-907830-11-3)pp. 223-236 (Chapter 15), MARG(Marginal Areas
Research Group, Graduate School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto,
Japan). ●Tsutsumi, K.(2016.▲)“Social capital,” The Association of American Geographers
(eds.)“The International Encyclopedia of
Geography: People, the Earth, Environment, and Technology,” (ISBN:▲)pp.
▲-▲(Chapter ▲), Wiley. ●Tsutsumi, K.(2016.▲):“Coal Miners and Social
Capital around Them: Cases of Miike and Takashima, ” ▲▲▲. (eds.)“Social Capital and Development Trends in Rural
Areas Vol.▲” (ISBN: ▲)pp. ▲-▲ (Chapter
▲), MARG(Marginal Areas Research Group, Graduate
School of Urban Management, Kyoto Univ., Kyoto, Japan). 【学会誌】 ●堤 研二(1995.6):「戦後の人文地理学とデイヴィド・ハーヴェイ」、『島根地理学会誌』31号、pp.11-30。 【紀要】 ●堤 研二(1986.11):「人口流出傾向の鈍化以後における山村研究の課題について」、『佐世保工業高等専門学校研究報告』、23号、pp.119-127。 ●堤 研二(1990.1):「ドイツ社会地理学に関する一ノート:Ruppert, SchafferとLengとの論争」、『佐世保工業高等専門学校研究報告』、26号、pp.135-144。 ●堤 研二(1997.3):「縁辺地域に関する一考察:縁辺地域の基本性格と地域変動」、『地域社会論集』(島根大学法文学部地域社会教室)第6号、pp.81-98。 ●堤 研二(2000.12):「近代における地方鉄道と地域構造:福岡県太宰府地域を事例として」、『待兼山論叢』(日本学篇)(大阪大学大学院文学研究科)第34号、pp.47-61。 ●堤 研二(2006.3):「高島炭鉱閉山に伴う人口流出の分析」、『大阪大学大学院文学研究科紀要(モノグラフ編)』第46巻-2、v+113P。 ●堤 研二(2011.12):「地域科学、新経済地理学と日本の経済地理学に関する試論的考察:ERSA50周年と日本の経済地理学」、『待兼山論叢』(日本学篇)(大阪大学大学院文学研究科)第45号、pp.1-25。 ●堤 研二(2015. 12):「計量的地域分析の体系とその教育上の課題」、『待兼山論叢』(日本学篇)(大阪大学大学院文学研究科)第49号、pp. 1-16。 【自治体史】 ★小林 茂・堤 研二(2001.9):「土地利用の変化と伝統的環境利用」、 ●堤 研二(2004.3):「太宰府の観光産業」、 ●堤 研二(2004.9):「高度成長期の変貌」、 【財団法人・社団法人・シンクタンク等雑誌】 ●堤 研二(2001.4):「過疎地域の人口と過疎問題:2000年国勢調査速報をもとに」、『統計』(財団法人・日本統計協会)第52巻第4号、pp.18-24。 ●堤 研二(2002.4):「過疎・高齢化地域における医療・救急体制の整備とIT」、『建築と社会』(社団法人・日本建築教会)第83集・通巻961号、pp.28-29。 ●堤 研二(2016.4)「人口のメガシュリンクと街づくり:過疎地域の実態から学ぶこと」、ER(富士通総研経済研究所 経済・経営・技術読本)第2号、pp.38-39。 【商業誌】 ●堤 研二(1987.12):「西海の港湾都市: ●堤 研二(1992.6: 1992.7):「欧米社会地理学とミュンヘン学派(前編・後編)」、『地理』(古今書院)38巻6号、pp.106-111および38巻7号、pp.109-113。 【単行本所収(ハードカバーのプロシーディングスを含む)】 ●堤 研二(1995.11):「地方大都市近郊農村の里山利用の変化: ●堤 研二(1997.3):「炭鉱都市から市民都市へ」、平岡昭利 編『九州:地図で読む百年』、pp.25-30、古今書院(東京)。 ●堤 研二(1997.11):「旧軍港都市 ●堤 研二(1999.5):「 ●堤 研二(1999.5):「出雲平野」、平岡昭利 編『中国・四国:地図で読む百年』、pp.107-112、古今書院(東京)。 ●堤 研二(2003.6):「農村研究・集落研究」(第3章「第1次産業」、第4節)、経済地理学会
編『経済地理学の成果と課題 第Ⅵ集』、pp.99-107、大明堂。 ●堤 研二(2004.3):「金屋子神信仰形態の分類」、鉄の道文化圏推進協議会編『金屋子神信仰の基礎的研究』、pp.245-257、岩田書院。 ●堤 研二(2004.6):「社会地理学研究の系譜」、水内俊雄 編『空間の社会地理』(「シリーズ 人文地理学」、第5巻)、pp.1-22(第1章)、朝倉書店。 ●堤 研二(2006.3):「千里ニュータウン」、金田章裕・石川義孝 編『近畿圏』(「日本の地誌」、第8巻)、pp.169-175、朝倉書店。 ●堤 研二(2006.8):「農村人口の変動」、山本正三・奥野隆史・谷内 達・田林 明 編『日本総論Ⅱ(人文・社会編)』(『日本の地誌』第2巻)、pp.418-423、朝倉書店。 ●堤 研二(2007.4):「社会的不平等」、上野和彦・椿真智子・中村康子編『地理学概論』(地理学基礎シリーズ1)、pp.107-111、(p.114:コラム「地理教育における社会的不平等」)、朝倉書店。 ●Tsutsumi, K.(2008)“Senri New
Town,”in Philipp Oswalt (ed.)“Shrinking Cities :
Complete Works 3 Japan,”
Ch.6, pp.32-41, Project Office Philipp Oswalt( Berlin). ●堤 研二(2011.3):「山間地域集落の生活機能とソーシャル・キャピタル」(第9章)、藤田佳久 編著『山村政策の展開と山村の変容』、pp.219-243、原書房。 ●堤 研二(2015.10):「社会的不平等」、上野和彦・椿真智子・中村康子編『地理学概論 第2版』(地理学基礎シリーズ1)、pp.108-112、(p.115:コラム「地理教育における社会的不平等」)、朝倉書店。 ●堤 研二(2016.5):「考古学と人文地理学の間:科学性の検討」、田中良之先生追悼論文集編集委員会 編『考古学は科学か:田中良之先生追悼論文集』(上)、pp.35-49、中国書店。 ●堤 研二(2016.5):「考古学と地理学・空間分析:『考古学方法論研究会』とその時代」、田中良之『縄文文化構造変動論Ⅰ:もう一人の田中良之』、pp.439-445、すいれん舎。 ▲●堤 研二(2016.●):「山間地域・離島における産業・地域生活機能の維持とその課題:鳥取県日南町と島根県隠岐の島町の調査から」、● 編『続・現代農山村の社会分析』、pp.●-●、学文社。 【プロシーディングス所収】 ●Tsutsumi, K.(1998.3):“Development
of the Settlement System in Japan in the Context of Sustainable Regional
Development: A Case of Peripheral Region, ” in The
Organizing Committee of the 8th Japanese-German Geographical Conference (ed.)
“Sustainability
as an Approach for National, Regional and Local Development in Japan and
Germany,” pp.125-141, The Organizing Committee of
the 8th Japanese-German Geographical Conference (Hachioji, Tokyo). ●Tsutsumi, K.(2001.8): “Modernization,
Industrialization and Regional Change in Japan: A Case of a Coal Mining
Region: Panopticonization towards Space and Society in Modern Japan, ”The Organizing Committee of the 2nd International Conference of
Critical Geography (ed.) “For Alternative 21st Century Geographies: The 2nd International
Conference of Critical Geography, ”pp.127-135, The Organizing Committee of the 2nd International
Conference of Critical Geography (University of Taegu, Taegu, S.Korea). ●Tsutsumi, K.(2002.6):“Forest
Commons in the Present Japan: A Case of the New Trend in Forest Land Use, ”The International Critical Geography Group(ed.) “The 3rd International
Conference of Critical Geography, ”pp.284-289 (The Center for Regional Studies of the Hungarian
Academy of Sciences (Magyar Tudomanyos Akademia Regionalis Kutatasok
Kozpontja), Budapest, Hungary). ●Tsutsumi, K.(2017.●):“Population Outflow and Regional Attributes of Peripheral Regions
in Japan: Two Cases of Mountain Village and Ex-coalmining Region, ”Graduate School of Letteers, Osaka University (ed.) “Open Japan, Closed Japan:
Towards Interdisciplinary Studies in Human Mobility (Proceedings on the International Symposium on Japanese Studies
in Global Context), ”pp.●-● (Graduate School of Letters, Osaka University, Toyonaka). ●Tsutsumi, K.(2017.●):“Nagasaki: A Hodgepodge City
of Cultures, ” Crossroads of Cultures
and Firms: From the Age of Discovery to the Age of Globalization●. 【報告書】 ●堤 研二(1982.1):「 ●堤 研二(1984.3):「 ●堤 研二(1989.9):「地理学における計量分析について」、『佐世保工業高等専門学校電子計算機室広報』2号、pp.13-21。 ●堤 研二・藤田佳久・中島弘二(1991.3):「里山・奥山・牧野における林野利用の変化」、文部省科学研究費重点領域研究『「近代化による環境変化の地理情報システム」平成2年度総合報告書』1巻、pp.215-222。 ●堤 研二(1991.8):「炭鉱閉山に伴う ●西野寿章・堤 研二・関戸明子・中島弘二(1992.3):「中部および東北日本の山間集落における林野利用の変化」、文部省科学研究費重点領域研究『「近代化による環境変化の地理情報システム」平成3年度総合報告書』1巻、pp.175-182。 ●堤 研二(1992.11):「地方大都市近郊農村の里山利用の変化: ●堤 研二(1994.8):「過疎現象と島根県の過疎地域(第1部第1章)」・「調査の目的(第2部第1章)」・「回答者の属性と職業(同第2章)」・「生活環境の評価と生活圏(同第6章)」、島根県過疎地域対策協議会『生活環境調査報告書:過疎問題調査事業業』、pp.1-13, 33-35, 36-39, 55-64、同協議会。 ●Tsutsumi, K.(1996.3):“Industrialization in a Peripheral Region at
Modern Japan : A Case of Tea Industry in Yame Region, Fukuoka Prefecture, ”in Nozawa, H.(ed.)“Social Theory and Geographical Thought: Japanese Contributions to
the History of Geographical Thought(6), ”pp.7-10, Institute of Geography, Faculty of Letters, Kyushu
University (Fukuoka). ●Tsutsumi, K.(1996.3):“Depopulated Regions in Japan : A model on Social Change in Peripheral
Regions, ”in Kobayashi, K. and Kita, K.(eds.)“Exploring Sustainability
: Proceedings of the International Symposium on the Future of Small Society in a Dynamic Economy, ”pp.251-259, Regional Planning Research
Group (Tottori and Karlstad). ●堤 研二(1996.3):「多変量解析による分類」、島根県教育委員会・島根県古代文化センター 編『出雲神庭荒神谷遺跡 第1冊 本文編』、pp.97-105(第1部「神庭荒神谷遺跡の環境」第5章「遺物」第1節「銅剣」2「銅剣の分類」Bとして所収)。 ●Tsutsumi, K.(1998.3):“Development of the Settlement System in
Japan in the Context of Sustainable Regional Development : a Case of Peripheral Region, ”in The Organizing Committee of the 8th Japanese-German
Geographical Conference(ed.)“Sustainability as an Approach for National, Regional and Local
Development in Japan and Germany, ”pp.125-141, The Organizing Committee of the 8th Japanese-German
Geographical Conference(Tokyo). ●堤 研二(2000.3):『地域空間の形成と変動に関する実証的および理論的研究』、平成10年度~11年度・文部省科学研究費・基盤研究(C)(2)、課題番号:10680082、研究代表者:堤 研二、研究組織:1名(研究代表者のみ)、交付金額:総額2,200千円(平成10年度:、1,400千円、平成11年度:800千円)、53P。 ●堤 研二(2001.12):『人口減少・高齢化地域における生活機能・社会経済的地域機能の実態とIT支援』、平成12年度、日本証券奨学財団研究助成・経済学分野、研究代表者:堤 研二、研究組織:1名(研究代表者のみ)、交付金額:総額900千円、55P。 ●堤 研二(2003.3):『人口減少・高齢化地域における交通弱者の行動パターンと交通安全対策に関する研究』、平成14年度、佐川交通社会財団・交通研究助成(一般研究)、研究代表者:堤 研二、研究組織:1名(研究代表者のみ)、交付金額:総額950千円、20P。 ●堤 研二(2003.3):「地域社会と伝統的祭り」(第3章)、祭りとコミュニティ研究会 編『祭の存在の有無がもたらすコミュニティ意思の差異に関する調査研究』、pp.23-30. ●堤 研二(2003.5):『ダム建設に伴う水没・移転集落の自立的再編成に関する研究』、平成14年度、河川環境整備財団・河川整備基金(一般的研究)、研究代表者:堤 研二、研究組織:2名(共同研究者:今里悟之)、交付金額:総額950千円、30P。 ●Tsutsumi, K.(2003.8):“Panopticonization towards Space and Society
in Modern Japan : A Case of a Coal-mining Region, ”in Mizuuchi, T.(ed.)“Representing Local Places and Raising Voices from Below: Japanese
Contributions to the History of Geographical Thought(8), ”pp.135-142, Department of
Geography/Urban-Culture Research Center, Osaka City University (Osaka). ●堤 研二 編(2005.3):『構造改革期における農山村・人口減少地域の変動と政策課題』、平成15年度~16年度・日本学術振興会・基盤研究(C)(1)、課題番号:15520497、研究代表者:堤 研二、研究組織:6名、交付金額:総額3,400千円(平成15年度:、2,000千円、平成16年度:1,400千円)、96P。 ●堤 研二(2007.3):『林野・水をめぐる環境コモンズとsocial capital』、2005年度昭和シェル石油環境研究財団研究助成調査報告書、研究代表者:堤 研二、研究組織:1名(研究代表者のみ)、交付金額:総額1,500千円、20P。 ●堤 研二 (2008.3):『人口減少期の地域社会における集落システムと生活機能の維持に関する地理学的研究』、平成17年度~19年度・日本学術振興会・基盤研究(C)(1)、課題番号:17520534、研究代表者:堤 研二、研究組織:1名、交付金額:総額3,400千円(平成17年度:、1,300千円、平成18年度:1,300千円、平成19年度:800千円)、75P(データベースCD-ROM付き)。 【解題付き翻訳】 ●堤 研二 訳、ハーヴェイ, D.著(1997.3):「 空間と時間の間で――地理学的想像力に関する省察」、『空間・社会・地理思想』第 2号、pp. 54-78(翻訳pp.54-73、解題ほかpp.73-78)。 【中学教科書】 ●堤 研二(2016.2):「人口からみた日本」、『中学社会 地理的分野』、pp.150-153、日本文教出版。 ●堤 研二(2016.2):「中国・四国地方」、『中学社会 地理的分野』、pp.182-193、日本文教出版。 【翻訳】 なし 【事典・資料集などの大項目】 ●堤 研二(2002.6):「人口移動と過密・過疎」、日本人口学会 編『人口大事典』(第2部「世界と日本の人口問題」、第5章「日本の人口問題」、第Ⅲ節として)、pp.170-175、培風館。 ●【前掲】Tsutsumi, K.(2017.▲):“Social Capital, ”in AAG (ed.)“The International Encyclopedia of Geography,”vol.▲, pp.▲-▲, Wiley(▲). 【事典・資料集などの小項目】 ●堤 研二(1994.4):「世界人口会議」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.57、実務教育出版(東京)。 ●堤 研二(1994.4):「インドの人口問題」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.60、実務教育出版(東京)。 ●堤 研二(1994.4):「人口抑制政策」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.60、実務教育出版(東京)。 ●堤 研二(1994.4):「高齢化社会とその対策」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.63、実務教育出版(東京)。 ●堤 研二(1994.4):「難民問題」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.66、実務教育出版(東京)。 ●堤 研二(1994.4):「家計を支える子ども達」、実務教育出版編『地理B指導資料』、p.67、実務教育出版(東京)。 ★林 正久・堤 研二(1994.12):「地理学教室案内:島根大学法文学部・教育学部」、『地理』、第39巻12号、pp.70-77、古今書院(東京)。 ●堤 研二(2000.10):「島根県」、永原慶二ほか編『日本歴史大事典』第2巻(こ-て)、pp.413-414、小学館(東京)。 ●堤 研二(2001.3):「斐伊川」、永原慶二ほか編『日本歴史大事典』第3巻(と-わ)、p.435、小学館(東京)。 ●堤 研二(2001.3):「松江」、永原慶二ほか編『日本歴史大事典』第3巻(と-わ)、p.750、小学館(東京)。 ●堤 研二(2001.3):「温泉津」、永原慶二ほか編『日本歴史大事典』第3巻(と-わ)、p.1017、小学館(東京)。 【学界展望】 ●堤 研二(1991.6):「学界展望(1990年1月~12月)「人口」」、『人文地理』(人文地理学会)第43巻3号、pp.24-26。 ●堤 研二(2002.6):「学界展望(2001年1月~12月)「学史・方法論」、『人文地理』(人文地理学会)第54巻3号、pp.25-27。 【書評】 ●堤 研二(1994.11):「書評:P.ノックス 著・小長谷一之 訳:『都市社会地理学』上・下」、『地理』第39巻11号、pp.127-128。 ●堤 研二(1997.9):「書評:岡橋秀典 著:『周辺地域の存立構造:現代山村の形成と展開』、1997年、大明堂刊」、地理学評論(日本地理学会)、第70巻(Ser. A)9号、pp.592-594。 ●堤 研二(1999.6):「書評:西野寿章 著:『山村地域開発論』、1998年、大明堂刊」、地理学評論(日本地理学会)、第72巻(Ser. A)6号、pp.391-393。 ●堤 研二(2005.11)「新刊短評:店田廣文 編:『アジアの少子高齢化と社会・経済発展』、2005年、早稲田大学出版部刊」、人口学研究(日本人口学会)、第37号、pp.110-111。 ●堤 研二(19▲):「書評:K.ホガート & H.ブラー著、岡橋秀典・澤 宗則 監訳:『農村開発の論理:グローバリゼーションとロカリティ(上・下)1998年、古今書院刊』」、pp.▲-▲。 ●堤 研二(2007.4):「書評:J.アーリ著、吉原直樹監訳:『社会を越える社会学:移動・環境・シチズンシップ』、2006年、法政大学出版局刊」、社会学研究(東北社会学研究会)81、pp.93-97。 ●堤 研二(2017.●):「新刊短評:加藤久和著:『8000万人社会の衝撃:地方消滅から日本消滅へ』、2016年、祥伝社」、人口学研究(日本人口学会)第53号、pp.●-●。 【授業テキスト】 ●石井 徹・飯塚登世一・田籠 博・堤 研二・松井嘉徳(島根大学法文学部文学科情報科学演習カリキュラム委員会)(1995.3):『チャレンジ・パソコン(第1版)』(堤担当箇所:「第4章
表計算 LOTUS1-2-3」pp.54-77 および「第5章 LIBISとSUNCS」pp.78-87)、同委員会。 【単行本編集】 ●懐徳堂記念会編(2007.5)『大坂・近畿の城と町』(懐徳堂ライブラリー7)、和泉書院、iii+165頁。 【WEBサイト】 ●Tsutsumi, K.(1997.8):“A Most
Uneven Developed Country, Japan : Depopulated Regions There, ” The Organizing Committee of the Inaugural International
Conference in Critical Geography (IICCG) (University of British Columbia,
Vancouver): http://www.geog.ubc.ca/iiccg/papers/Tsutsumi.html. 【新聞記事】 ●堤 研二(2010.9):「山間地域で学んだ『自他共楽』」、西日本新聞「土曜エッセー」、西日本新聞朝刊 学術・芸術面(13面)、2010.9.25(土)。 【雑誌記事】 ●堤 研二(2012.2):コメント記事「人口激減社会で『消えていくもの』一覧」(42~44頁)、うち44頁においてコメント2件掲載、週刊現代2012年2月25日号(第54巻第7号)。 【解説】 ●堤 研二(2012.10):「地域社会学と『地域社会学会会報』の意義」、「会報」刊行世話人会
監修『復刻 地域社会学会会報 別冊(解説)』、pp.9-11、近現代資料刊行会。 【卒業論文・修士論文・博士論文】 ●堤 研二(1983.1):『八女茶業地域の形成過程』、九州大学文学部卒業論文。 ●堤 研二(1986.1):『山村からの人口移動の分析:大分県上津江村を事例に』、九州大学大学院文学研究科修士課程修了論文。 ●堤 研二(2009.2):『過疎・人口激減地域における人口流出に関する研究』(学位:2009.2.13(金):九州大学:文博乙第249号、博士(文学))。 2)口頭発表・講演・他大学での授業など ■は招聘または依頼または招待 【海外で開催分の国際学会・国際集会】 ●■Tsutsumi, K.(1992.8):“Regional Identity in the Japanese
Centralism, ” The 7th Japanese-German Geographical Conference
(Duisburg University, Duisburg, Germany):1992.8.16(日)-27(木). ●Tsutsumi, K.(1996.1):“Mountain Villages and Coal Mining regions
in Japan: A Model of Regional Social Change in peripheral Regions, ” The International Comparative Study of Coalminers: Canada and
Japan (University of Toronto, Erindale College, Toronto, Canada):1996.1.▲. ●■Tsutsumi, K.(1997.5):“Depopulated
Region in Japan: A Case Study on Former Coal Mining Region, Takashima,
Nagasaki Prefecture, Japan, ” The International
Symposium on the Future of Small Society in a Dynamic Economy (University of
Karlstad, Karlstad, Sweden):1997.5.11(日)-14(水). ●Tsutsumi, K.(1997.8):“A Most
Uneven Developed Country, Japan: Depopulated Regions There,”The Inaugural International Conference of Critical Geography (University of British Columbia etc.,
Vancouver, Canada):1997.8.10(日)-13(水). ●■Tsutsumi, K.(1999.1):“Industrialization
and Spatial Integration in Modern Japan” The 1st East
Asia Regional Conference in Alternative Geography (EARCAG) , (Kyongju,
S.Korea):1999.1.23(土)-26(火). ●Tsutsumi, K.(2000.8):“Modernization,
Industrialization and Regional Change in Japan: A Case of a Coal Mining
Region: Panopticonization towards Space and Society in Modern Japan, ” The 2nd International Conference of Critical Geography (University of Taegu, Taegu,
S.Korea):2000.8.9(水)-13(日). ●Tsutsumi, K.(2000.8):“Public
Administration to Depopulated Regions in Japan, ” The
International Geographical Congress (Seoul, S.Korea):2000.8.15(火). ●■Tsutsumi, K.(2001.9):“Regional
Functions and Information Technology in Depopulated Areas: Some Cases in
Japan, ” The International Symposium on Communication
and Regional Development (University of Karlstad, Karlstad Sweden):2001.9.17(月)-19(水). ●Tsutsumi, K.(2002.6):“Forest
Commons in the Present Japan: A Case of the New Trend in Forest Land Use, ” The 3rd International Conference of Critical Geography (Tessedik Samuel Foiskola,Bekescsaba):2002.6.25(火)-29(土). ●■Tsutsumi, K.(2004.8):“Fundamental Functions of Living in a Small
Community: Some Cases in Depopulated Areas in Japan, ” The Workshop on “Social Capital and Development Trends in Japan's and Sweden's
Countryside, ”(Mid-Sweden University, Östersund, Sweden):2004.8.23(月)-24(火). ●■Tsutsumi, K.(2004.9):“Aging, Landscape, Restructuring
and Conflicts in an Old New Town: Senri New Town in Osaka Metropolitan Area, ” The 9th Japanese-German Geographical Conference (Ruhr University
Bochum, Bochum, Germany):2004.8.30(月)-9.1(水). ●■Tsutsumi, K.(2006.8):“Drastic Depopulation, Town
Renovation and Social Capital in a Coal Mining Island: a Case of Takashima in
Nagasaki Prefecture, ” The 3rd Workshop on
Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside
(Hotel Vindelälven, Vindeln, Sweden):2006.8.19(土)-20(日). ●■Tsutsumi, K.(2008.8):“Sustainable Policy for Settlement Life and
Socio-economic Trends of Depopulation in Rural Japan, ”The 5th Workshop on Social Capital and Development Trends in the
Japanese and Swedish Countryside (Södra Vätterbygdens Folkögskola, Jönköping,
Sweden):2008.8.18(月)-19(火). ●Tsutsumi, K.(2008.12):“Over Neoliberal
Social Capitalism: Social Capital and Revitalization of Depopulated
Mountainous Areas in Japan,”The 5th East Asia Regional
Conference in Alternative Geographies (EARCAG), (Seoul, S.Korea):2008.12.13(土)-16(火). ●■Tsutsumi, K.(2008.12):“Some Materials for
Discussion: at panel Discussion,”The 5th East Asia
Regional Conference in Alternative Geographies (EARCAG), (Seoul, S.Korea):2008.12.13(土)-16(火). ●■Tsutsumi, K.(2010.7):“Resources for Some
Possibilities Bonding to Cultural Translation: Section of Human Geography at
Graduate School of Letters, Osaka University,” Group E: Cultural
Translation, Japanese-German Presidents’ Conference,
(Heidelberg University, Heidelberg Germany): 2010.7.29(木)-30(金). ●■Tsutsumi, K.(2010.8):“Interscale
and Interlevel Problems of Research on Social Capital in Rural Japan,”The 7th Workshop on Social Capital and Development Trends in the
Swedish and Japanese Countryside, with a conference of the 50th
years anniversary of European Regional Science Association (ERSA) “Sustainable Regional Growth and Development in the Creative
Knowledge Economy” (Jönköping University, Jönköping,
Sweden):2010.8.19(木)-22(日). ●Tsutsumi, K.(2011.6):“Regional Science and
New Economic Geography in the Academia of Japanese Economic Geography,”The 3rd Global Conference on Economic Geography, (COEX, Seoul,
S.Korea):2011.6.28(火)-7.2(土). ●■Tsutsumi, K.(2012.5):“Mountainous Areas in Japan and
the Forest Town Management Model, ”The 9th Workshop on
Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside
(Blasingsborgs Conference Hotel, Österlen, Sköne, Sweden):2012.5.24(木)-25(金). ●■Tsutsumi, K.(2014.8):“Junior Sports Club and Regional
Social Capital in Japan, ”The 11th Workshop on
Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside
(Mid-Sweden University, Östersund,
Sweden):2014.8.21(木)-22(金). ●Tsutsumi, K.(2015.8):“A
Compact Town Model in Peripheral Regions in Japan: Some Cases and Trials,”The 4thd Global Conference on Economic Geography, (Oxford
University, Oxford, England):2015.8.19(水)-8.23(日).
●■Tsutsumi, K.(2016.6):“Coal Miners and Social Capital
around Them: Cases of Miike and Takashima, ” The 13th Workshop on Social Capital and Development Trends in the
Japanese and Swedish Countryside:Transforming Mining
Cities (Hotel Scandic Ferrum, Kiruna, Sweden):2016.6.17(金)-6.19(日). ●■Tsutsumi, K.(2016.9):“Nagasaki: A Hodgepodge City of
Cultures, ” Crossroads of Cultures
and Firms: From the Age of Discovery to the Age of Globalization (Nova
University of Lisbon, Portgal):2016.9.5(月). ●■Tsutsumi, K.(2016.12):“A Struggle for
Establishment of University Coop at Shimane University, 1992-1999:An Experience of
Conflicts and Contradictions through a Students' and Teachers' Movement, ” The 8th East Asia Regional Conference in Alternative Geography
(EARCAG), (Hong Kong Baptist University, Hong Kong):2016.12.6(火)-8(木). 【国内で開催の国際学会・国際集会・国際プログラム】 ●Tsutsumi, K.(1995.10):“Depopulated
regions in Japan: A Model on Social Regional Change in Peripheral Regions, ”
Exploring Sustainability: The International Symposium on the
Future of Small Society in a Dynamic Economy, (Tottori Prefectural Culture
Hall, Tottori):1995.10.24(火)-28(土). ●Tsutsumi, K.(1998.3):“Development
of the Settlement System in the Context of Sustainable Regional Development:
A Case of Peripheral Region, ” The 8th
Japanese-German Geographical Conference (Hachioji, Tokyo):1998.3.16(月). ●Tsutsumi, K.(1999.5):“Challenges
from Depopulated Regions, ” The International
Symposium “Local Knowledge and Innovation: Enhancing
the Substance of Non-Metreopolitan Regions” (Tottori
University, Tottori):1999.5.11(火)-14(金). ●Tsutsumi, K.(1999.8):“Industrialization
and Panopticonization towards Space and Society in Modern Japan: A Case of a
Coal Mining Region, ” The Osaka Workshop for
Frontiers of Asian Geographies (Osaka City University, Osaka):1999.8.16(月)-17(火). ●Tsutsumi, K.(2003.8):“An Old
“New Town”: Involution in
Senri New Town, Osaka Prefecture, ” The 3rd East Asia
Regional Conference in Alternative Geography (EARCAG) , (Tokyo and Osaka,
Japan):2003.8.5(火)-9(土). ●Tsutsumi, K.(2005.10):“Social
Ties in Communities: Some Rural and Urban Cases in Japan, ” A Workshop on “〝Social Capital and
Development Trends in Japan’s and Sweden’s Countryside” (MARG), (Nichi’nan town, Tottori prefecture, Japan):2005.10.24(月)-25(火). ●Tsutsumi, K.(2007.8): “Social ties and “Social Capital” in areas under shrinking
and marginalization process in Japan,” The 4th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside; jointed with The
2007 World Conference of International Geographical Conference/C 04.27 on “Marginalization, Globalization and Regional and Local response.” (Hokkai Gakuen University of Commerce, Kitami, Japan):2007.8.20(月)-22(水). ●Tsutsumi, K.(2009.7): “Social Capital in Rural Studies in Japan: An
Examination of Actual Forms of Social Capital,” The 6th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Ohama Nobumoto
Memorial Hall, Ishigaki, Japan):2009.7.1(水)-2(木). ●Tsutsumi, K.(2011.5): “Formation of the Tourist Industry at the Core of a
Shrine through the Modern and Present Eras: Social Capital and Agents around
Dazaifu Tenmangu,” The 8th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Nara Prefecture
New Public Hall, Nara, Japan):2011.5.20(金)-22(日). ●Tsutsumi, K.(2013.5)“Marginality and
Sustainability of Mountainous Village and Forestry,” The 10th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Amakusa Treasure
Island International Exchange Hall "Porto," Amakusa, Japan):2013.5.16(木)-18(土). ●■Tsutsumi, K.(2013.7)“Thinking
from Japan beyond the four "D"s, concerning with Social Capital:
Diversity, Disparity, Depopulation and Deprivation (A Plenary Lecture),”The 8th Japan-Korea-China Joint Conference on Geography.(Kyushu University, Fukuoka, Japan):
2013.7.31(水)-8.4(日). ●Tsutsumi, K.(2013.8.6, 17:30-19:00, Room663) “Forestry Revitalization and Regional Marginality at Mountainous
Areas in Japan,” IGU (International Geographical
Union) 2013 Kyoto Regional Conference. (Kyoto
International Conference Center (ICC Kyoto), Kyoto, Japan):2013.8.4(日)-9(金). ●■Tsutsumi, K.(2014.12.17, 12:50-14:20, Room B204) “Regional Social Capital in Rural
Regions: Some Cases in Depopulated Areas in Japan and the Other Countries,” The 28th Taoyaka Program Seminar
(TAOYAKA PROGRAM for creating a flexible, enduring, peaceful society:
Organization of the Leading Graduate Education Program), Graduate School of
Letters, Hiroshima University, Higashihiroshima, Japan):2014.12.17(水). ●Tsutsumi, K.(2015.5)“Trial for Sustaining Regional Life in a Peripheral Island Town - A Case of Okinoshima
-,” The 12th
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside. (Hida Earth Wisdom Center, Takayama, Japan):2015.5.23(土)-25(月). ●■Tsutsumi, K.(2016.3):“Population Outflow and Regional Attributes
of Peripheral Regions in Japan: Two Cases of Mountain Village and
Ex-coalmining Region, ”“Open Japan, Closed Japan: Towards Interdisciplinary
Studies in Human Mobility (International Symposium on Japanese Studies in
Global Contexts)”(グローバル日本研究国際シンポジウム「開く日本・閉じる日本—「人間移動学」事始め—」), (Sigma Hall, Osaka University,
Toyonaka, Japan):2016.3.23(水)-24(木). 【国内で開催の研究会・講演会:依頼によるゲスト・スピーカー】 ●■堤 研二(1991.12):「過疎山村地域の道路整備について」、建設省九州地方建設局主催『フォーラム みち・みらい九州』(ホテル日航福岡、 ●■堤 研二(1997.11):「環境利用と地域形成」、平成9年度 和鋼博物館講座11月例会 ( ●■堤 研二(2000.11):「地域社会と教育- 西城における取り組みと問題の整理」、第2回 ●■堤 研二(2000.11):「近代の地方鉄道と地域構造:太宰府馬車鉄道を事例として」、 ●■堤 研二(2001.1):「隠岐空港整備・利用促進に関する総合調査私案」ほか、隠岐空港整備利用促進協議会理事会(島根県隠岐支庁、島根県隠岐郡 ●■堤 研二(2001.5):「明治・大正・昭和の太宰府軌道(馬車鉄道):近代の鉄道と地域構造」、太宰府を語る会 第517回例会(太宰府天満宮文華館、 ●■堤 研二(2001.10):「温泉地区ダム周辺地域活性化について」、島根県中山間地域づくり支援ブレーンバンク派遣事業( ●■堤 研二(2001.12):「人間・環境・地域社会:過疎地域研究の視座から」、2001年度大阪大学地球総合工学シンポジウム:「大阪大学は地球を救うことに貢献できるか?:持続可能な発展を目指して」(大阪大学吹田キャンパス、銀杏会館、阪急電鉄・三和銀行ホール、 ●■堤 研二(2002.3):「地域連携教育の動向と課題」、 ●■堤 研二(2002.3):「大学から見た高専教育:学生指導の立場から」(佐世保工業高等専門学校、 ●■堤 研二(2002.11):「農山村の地域変動に学ぶ:環境利用と地域連携教育」、公開講座フェスタ2002年(主催:阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット。財団法人・懐徳堂記念会担当分)、(大阪府立文化情報センター・さいかくホール、 ●■堤 研二(2003.1):「隠岐空港の現状と課題」、隠岐空港整備・利用促進協議会ワーキングスタッフ会( ●■堤 研二(2003.3):「槻之屋集落の取組みの位置づけ」、河川環境管理財団・河川整備基金助成(一般)・研究課題名:「ダム建設に伴う水没・移転集落の自立的再編成に関する研究」に関する調査時の対象集落での講演活動( ●■堤 研二(2004.6):「環境・地域・暮らしと地理的思考」、大阪府第一学区校長会依頼事業(出前講義)(大阪府立池田高等学校、 ●■堤 研二(2005.9):「太宰府の観光産業史」、「太宰府発見塾」( ●■堤 研二(2007.2):「地域連携活動について」(スポーツ少年団長としてのラウンドテーブルへの参加)、千里市民フォーラム主催「千里ニュータウンまちづくり市民フォーラム -地域での自治活動のあり方を考える-」(千里市民センター、 ●■堤 研二(2008.7):「ふるさとの力を引き出す」、徳島県人会近畿連合会・NPO法人ふるさと力協賛勉強会「ふるさとの力を引き出す」(徳島県三次市三野活性化センター「紅葉の郷」、徳島県三好市):2008.7.12(土)。 ●■堤 研二(2010.8):「地域連携と子の育ち:地域の事情を知り、学校現場に生かす手法とは」、豊中市立小曽根小学校・学力向上自主企画事業・校内研修会、(豊中市立小曽根小学校、大阪府豊中市):2010.8.31(火)。 ●■堤 研二(2011.10):「大阪の地域特性とその課題」、大阪・京都文化講座(2011年度後期 立命館プロムナードセミナー)「大阪・京都の風土と景観」(第1回)、(立命館大阪キャンパス、大阪府大阪市): 2011.10.17(月)。 ●■堤 研二(2016.4):「ソーシャル・キャピタルと地域の持続可能性」、島根県出雲市議会研修会講演(出雲市議会、島根県出雲市):2016.4.13(水)。 ●■堤 研二(2016.11):「大阪のスポーツ少年団」、大阪・京都文化講座(2016年度後期 立命館プロムナードセミナー)「昭和の風俗・風物・風景-忘れられた昭和史-」(第●回)、(立命館大阪キャンパス、大阪府大阪市): 2016.11.14(月)。 【国内で開催の学会】 ●堤 研二(1983.7):「八女茶業地域の形成過程」、福岡地理学会夏季研究発表会(福岡ガーデンパレス、 ●堤 研二(1986.8):「過疎山村・ ●堤 研二(1987.10):「人口移動に関する研究課題の検討について」、日本地理学会秋季学術大会(九州大学、 ●堤 研二(1988.1):「炭鉱閉山後の ●堤 研二(1989.7):「近年の考古学・人類学における空間分析:地理学からの影響について」、福岡地理学会夏季研究発表会(福岡大学セミナーハウス、 ●堤 研二(1990.4):「炭鉱閉山の島・ ●堤 研二(1991.3):「里山・奥山・牧野における林野利用の変化」、『近代化による環境変化の地理情報システム』第2回シンポジウム(東北大学、 ●堤 研二(1991.4):「ドイツ社会地理学の一系譜:とくにRuppert, Schafferの社会地理学について」、日本地理学会「社会地理学の理論と課題」作業グループ研究会( ●堤 研二(1991.7):「地理学における過疎地域研究について:社会地理学的アプローチ」、島根大学過疎地域研究会(島根大学、 ●堤 研二(1991.8):「里山における土地利用の変化: ●堤 研二(1991.10):「九州山地における伝統的環境利用について」、島根地理学会(島根大学、 ●堤 研二(1991.11):「太宰府における都市化と土地利用変化」、第15回 ●堤 研二(1992.11):「社会地理学的視点と統一後のドイツ」、中四国歴史学地理学社会科教育学研究大会(島根大学、 ●堤 研二(1993.7):「近代の八女地方における茶業と産業組合活動」、歴史地理学会第158回例会(福岡教育大学、 ●堤 研二(1993.7):「地域社会変動の一考察:事例分析( ●堤 研二(1993.9):「近代の八女地方における茶業と産業組合活動」、島根大学国家論研究会(島根大学、 ●堤 研二(1993.12):「近代化・縁辺地域・ローカリティ」、文部省科学研究費総合研究(A)『社会理論と地理学:その思想史的考察』第2回研究集会(福井県芦原):1993.12.25(土)。 ●堤 研二(1994.12):「近代における産業と空間:前田正名、田中慶介と八女茶業」、文部省科学研究費総合研究(A)『社会理論と地理学:その思想史的考察』第4回研究集会( ●堤 研二(1995.9):「島根県における過疎地域の現状と課題」、経済地理学会関西支部例会(関西大学、 ●堤 研二(2001.3):「第2回国際批判地理学会の概要」ほか、日本地理学会批判地理学研究グループ部会(敬愛大学、 ●堤 研二(2002.9):「 ●堤 研二(2002.9):「ICGG第1回・第2回大会とEARCAG関説して」、日本地理学会秋季学術大会シンポジウムⅦ「批判地理学:日本からの発信に向けて」(金沢大学、 ●堤 研二(2002.12):「近・現代における観光地『太宰府』の形成:天満宮・鉄道・エージェント」、人文地理学会第245回例会( ●堤 研二(2005.11):「長崎県高島炭鉱閉山に伴う人口流出:移動者の属性・移動パターンと転出先での生活状況」、2005年人文地理学会大会(九州大学六本松地区、 ●堤 研二(2007.6):「人口激減地域の比較研究:山村と炭鉱閉山地域からの人口流出を事例に」、日本人口学会第59回大会(島根大学、 ●■堤 研二(2012.8):「人口流出と地域変化:山村と炭鉱地域の調査から見えてきたこと」、日本村落研究学会(村研)2012年度九州・中国・四国地区研究会(九州大学箱崎キャンパス文学部社会学演習室、福岡市):2012.8.18(土)。 ●堤 研二(2012.10):「林業・森林管理・地域システム:山間地域の持続システム」、2012年日本地理学会秋季学術大会 シンポジウム「日本の山村の非限界性と村立基盤」(神戸大学鶴甲第一キャンパス、神戸市):2012.10.7(日)。 【国内でのその他の研究集会】 ●堤 研二(2000.1):「ICGGテグについて」、日本地理学会社会地理学研究グループ研究会( ●堤 研二(2003.1):「近・現代における観光地『太宰府』の形成:天満宮・鉄道・エージェント」、第4回祭りとコミュニティ研究会( ●堤 研二(2003.3):「兵要地誌と少林寺拳法・宗道臣」、空間論研究会(東京大学社会情報研究所、 ●堤 研二(2003.11):「兵要地誌と宗道臣」、科学研究費(基盤研究B「ポストモダンの景観論・空間論における『文化的転回』の影響とその評価に関する研究」(課題番号14380028、研究代表者・山野正彦)研究集会(ホテルマーレ南千里、 【他大学での集中講義】 ●(1992年度前期:7月)長崎大学教育学部:「地理学特講」 ●(1994年度前期:7月)長崎大学教育学部:「地理学特講」 ●(1995年度前期:7月)長崎大学教育学部:「人文地理学Ⅱ」 ●(1996年度前期:7月)長崎大学教育学部:「地理学特講」 ●(1997年度前期:7月)東京都立大学大学院理学研究科:「人文地理学特別講義Ⅱ」 ●(1997年度後期:12月)長崎大学教育学部:「人文地理学Ⅱ」 ●(1998年度前期:7月)長崎大学教育学部:「地理学特講」 ●(2000年度前期:7月)長崎大学教育学部:「地理学特講」 ●(2003年度前期:9月)島根大学法文学部:「社会地理学特論」 ●(2004年度前期:8月)東京都立大学大学院理学研究科:「地理学特別講義Ⅰ」・理学部: 「社会地理学」 ●(2008年度後期:12月)お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科:「環境認識論」 ●(2013年度後期)九州大学大学院人文科学府:「地理学講義」 【他大学での非常勤講師(集中講義以外)】 ●(1992年度後期~1995年度後期)島根医科大学医学部:「地理学」 ●(1999年度後期) ●(1999年度後期) ●(2002年度前期)関西学院大学文学部:「地理学特殊講義」 ●(2004年度前期)追手門学院大学文学部:「日本の中のアジア1」 ●(2004年度後期)追手門学院大学文学部:「日本文化の諸相2」 ●(2004年度後期)関西学院大学文学部:「地理学地域文化学特殊講義」 ●(2005年度前期)追手門学院大学経済学部:「経済地理1」 ●(2005年度後期)追手門学院大学経済学部:「経済地理2」 ●(2006年度前期)関西学院大学文学部:「地理学地域文化学特殊講義」 ●(2006年度前期)追手門学院大学経済学部:「経済地理1」 ●(2006年度後期)追手門学院大学経済学部:「経済地理2」 ●(2006年度後期)奈良女子大学文学研究科:「地域環境学特殊研究」、文学部:「人文地理学特論」 ●(2007年度前期)追手門学院大学経済学部:「経済地理1」 ●(2007年度後期)追手門学院大学経済学部:「経済地理2」 ●(2007年度後期) ●(2008年度後期) ●(2009年度前期)関西学院大学社会学部:「社会地理学A」 ●(2011年度後期)京都大学大学院文学研究科:「地理学特殊講義」 ●(2013年度後期:10月)京都大学経営管理大学院:「国土・地域ソーシャル・キャピタル論講義」(オムニバス授業の一回分「第2回:ソーシャル・キャピタルとコミュニティ」を担当) ●(2014年度後期:10月)京都大学経営管理大学院:「国土・地域ソーシャル・キャピタル論講義」(オムニバス授業の一回分「第2回:ソーシャル・キャピタルとコミュニティ」を担当) ●(2015年度後期:10月)京都大学経営管理大学院:「国土・地域ソーシャル・キャピタル論講義」(オムニバス授業の一回分「第1回:ソーシャル・キャピタルとコミュニティ」を担当) ●(2016年度後期:10月)京都大学経営管理大学院:「国土・地域ソーシャル・キャピタル論講義」(オムニバス授業の一回分「第1回:ソーシャル・キャピタルとコミュニティ」を担当) 【その他の学校での授業など】 ●堤研二「大学教員の仕事(文学部の場合):研究、教育、社会連携」、福岡県立筑紫丘高等学校社会人講演会(同校創立80周年記念事業の一環)、同校(福岡市):2007.6.30(土)。 ●堤研二「地域と地域変動」、鹿児島県立甲南高等学校ブラッシュ・アップ・セミナー、同校(鹿児島市):2013.11.22(金)。 ●堤研二「人口の減少と地域・社会:過疎地域の例から人口減少社会のことを考えてみよう(主権者教育の視点による)」、さいたま市立桜木中学校・主権者教育授業、中学校3年生4クラス対象の4コマ授業、同校(さいたま市):2016.12.12(月)。 3)オーガナイザー、チェアー、パネラー、コメンテーターなど 【海外で開催分の国際学会・国際集会】 ●チェアー:(1997.8):The Inaugural
International Conference of Critical Geography (University of British Columbia etc.,
Vancouver, Canada):1997.8.10(日)-13(水). ●セッション・オーガナイザー:(2000.8):“A
New Wave of Critical Geography in Non-Anglophone World, ” The 2nd International Conference of Critical Geography (University of Taegu, Taegu,
S.Korea):2000.8.9(水)-8.13(日). ●チェアー:(2002.6):The 3rd
International Conference of Critical Geography (Tessedik Samuel Foiskola,Bekescsaba):2002.6.25(火)-29(土). ●ディスカッサント:(2004.8): The Workshop on “Social Capital and
Development Trends in Japan's and Sweden's Countryside, ”(Mid-Sweden University, Östersund,
Sweden):2004.8.23(月)-24(火). ●チェアー:(2006.8):The 3rd
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside (Hotel Vindelälven, Vindeln, Sweden):2006.8.19(土)-20(日). ●ディスカッサント(発表あり):(2006.8)Ulf Wiberg “In
search for sustainable development in sparsely populated areas,” The 3rd
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside (Hotel Vindelälven, Vindeln, Sweden):2006.8.19(土)-20(日). 【国内で開催の国際学会・国際集会】 ●オーガナイザー、コーディネーター:(1999.5):“
The International Symposium 〝Local Knowledge and
Innovation: Enhancing the Substance of Non-Metreopolitan Regions” (Tottori University, Tottori):1999.5.11(火)-14(金). ●オーガナイザー(巡検担当):(1998.3):The
8th Japanese-German Geographical Conference (島根巡検。メイン会場は、Hachioji, Tokyo):島根巡検は1998.3.20(金)-23(月). ●チェアー・組織委員:(2003.8): The 3rd East Asia Regional
Conference in Alternative Geography (EARCAG) , (Tokyo and Osaka,
Japan):2003.8.5(火)-9(土). ●チェアー・ディスカッサント:(2005.10): A Workshop on “Social Capital and Development Trends in Japan’s and Sweden’s Countryside” (MARG), (Nichi’nan town, Tottori
prefecture, Japan):2005.10.24(月)-25(火). ●ディスカッサント(発表あり):(2007.8)Martin Paju “Cooperation
structures between municipalities: A question about trust and social capital
?,” The 4th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside; jointed with The
2007 World Conference of International Geographical Conference/C 04.27 on “Marginalization, Globalization and Regional and Local response.” (Hokkai Gakuen University of Commerce, Kitami, Japan):2007.8.20(月)-22(水). ●チェアー:(2007.8)The 4th
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside; jointed with The 2007 World Conference of International Geographical
Conference/C 04.27 on “Marginalization, Globalization
and Regional and Local response.” (Hokkai Gakuen
University of Commerce, Kitami, Japan):2007.8.20(月)-22(水). ●巡検担当:(2007.8)The 2007 World Conference
of International Geographical Conference/C 04.27 on “Marginalization,
Globalization and Regional and Local response.”:(北海道釧路地方):2007.8.22(水)-25(土). ●オーガナイザー・チェアー:(2009.1)韓国経済社会地理学の最先端(ソウル国立大学より、Kim, Yong-chang先生とPark, Bae-gyoon先生を招いての講演会):(大阪市立大学高原記念館):2009.2.16(月). ●チェアー:(2009.7)The 6th
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside. (Ohama Nobumoto Memorial Hall, Ishigaki, Japan):2009.7.1(水)-2(木). ●ディスカッサント(発表あり):(2009.7)Takato
Yasuno“Monitoring Individual Sociability to Learn
from Daily Activity,” The 6th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Ohama Nobumoto
Memorial Hall, Ishigaki, Japan):2009.7.1(水)-2(木). ●ディスカッサント(発表あり):(2011.5)H.
Westlund, A. R. Olsson and J. P. Larsson“Economic
Entrepreneurship, Startups and Their Effects on Local Development: The Case
of Sweden,” The 8th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Nara Prefecture
New Public Hall, Nara, Japan):2011.5.20(金)-22(日). ●ディスカッサント(発表あり):(2013.5)S. Westerdahl “To Love the New and Learn from History: on "Social" in
Rural Development,” The 10th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Amakusa Treasure
Island International Exchange Hall "Porto," Amakusa, Japan):2013.5.16(木)-18(土). ●ディスカッサント(発表あり):(2014.8)K.
Machino “New "Affluence Indicators" and
Regional Public Policies in Hokkaido,”The 11th
Workshop on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside (Mid-Sweden University, Östersund,
Sweden):2014.8.21(木)-22(金). ●ディスカッサント(発表あり):(2015.5)T. Wallin“The Impact of Labour Diversity on the Innovativeness of Exporters,” The 12th Workshop on Social
Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Hida Earth Wisdom Center, Takayama, Japan):2015.5.23(土)-25(月). ●ディスカッサント(発表あり):(2015.5)E. Hideshima“Process and Agendas to Form a Town Organization: in the Case of the
Startup Phase of Retro Nayabashi Hyakunen Iinkai,” The 12th Workshop on Social
Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside. (Hida Earth Wisdom Center, Takayama, Japan):2015.5.23(土)-25(月). ●■総合討論司会:(2016.3):“Open Japan, Closed Japan: Towards Interdisciplinary Studies in
Human Mobility (International Symposium on Japanese Studies in Global
Contexts)”(グローバル日本研究国際シンポジウム「開く日本・閉じる日本—「人間移動学」事始め—」), (Sigma Hall, Osaka
University, Toyonaka, Japan):2016.3.23(水)-24(木). ●チェアー:(2016.6) The 13th Workshop
on Social Capital and Development Trends in the Japanese and Swedish
Countryside:Transforming Mining Cities (Hotel Scandic
Ferrum, Kiruna, Sweden):2016.6.17(金)-6.19(日). ●ディスカッサント(発表あり):(2016.6)Sofia Wixe, Lucia Naldi, Pia Nilsson and Hans Westlund “Disentangling Innovation in Small Food Firms: The
role of external knowledge, support, and collaboration,” The 13th Workshop on Social Capital and
Development Trends in the Japanese and Swedish Countryside:Transforming Mining Cities (Hotel Scandic Ferrum, Kiruna, Sweden):2016.6.17(金)-6.19(日). 【国内学会特別研究発表】 ●座長:(1999.11):人文地理学会1999年度大会・髙木彰彦氏(九州大学)による特別研究発表「政治地理学の研究動向と可能性」(奈良大学、 【国内学会シンポジウム・例会】 ●コメンテーター:(2002.9):日本地理学会2002年度秋季学術大会シンポジウムⅦ「批判地理学:日本からの発信に向けて」・水岡不二雄氏(一橋大学)による発表「国際批判地理学集団(ICGG)と、日本からグローバルへの批判地理学発信に向けて」に対するコメント「ICGG第1、2回大会&EARCAGに関説して」(再掲。金沢大学、 ●コメンテーター:(2004.5):人文地理学会第251回例会・荒井良雄氏(東京大学)による発表「日本の人口移動 国内人口移動:高度経済成長期以降の動向」に対するコメント「荒井報告について」(キャンパスプラザ京都、 ●コメンテーター:(2010.10):「コメント:多様な山村像の把握のために」、経済地理学会2010年度松本地域大会シンポジウム「今日の山村問題と経済地理学の課題」(信州大学松本キャンパス、長野県松本市):2010.10.24(日)。 【国内学会研究部会】 ●座長・コーディネーター:(1999.11):人文地理学会・第60回地理思想研究部会・森川 洋氏(福山大学)による研究発表「ドイツ語圏における戦後の人文地理学の歩み:ハンス・ボーベクからベノ・ヴァーレンまで」(奈良大学、 ●座長・コーディネーター:(2000.5):人文地理学会・第62回地理思想研究部会・小野菊雄氏(九州大学名誉教授)による研究発表「ソビエト時代と地理学者たち」(大阪大学待兼山会館、 ●記録・報告:(2001.11):人文地理学会・第68回地理思想研究部会・西部 均氏( ●座長・コーディネーター:(2002.3):人文地理学会・第69回地理思想研究部会(巡検:千里ニュータウン、 ●座長・コーディネーター:(2003.7):人文地理学会・第75回地理思想研究部会・中村 豊氏による研究発表「現象学的メンタルマップ考:メンタルマップと生活世界」(京大会館、 ●座長・コーディネーター:(2003.11):人文地理学会・第76回地理思想研究部会・ミニ=フォーラム「地理思想研究の回顧と現代的意義」(関西大学、 ●コメンテーター:(2004.11):人文地理学会・第80回地理思想研究部会・前田裕介氏(九州大・研究生)による発表「D.ハーヴェイの実践と差異の諸問題─理論的普遍性と歴史地理的個別性の弁証法」(佛教大学、 ●座長・コーディネーター(2009.2):第7回千里ニュータウンまちづくり市民フォーラム「元気づくり!人づくり!まちづくり!」(第4部 「三世代で語ろう:元気づくり!人づくり!まちづくり!」)(千里市民センター、吹田市):2009.2.28(土)。 4)社会的活動 【受賞】 ★個人受賞★ ●(1997.7.6)1997年度「地域地理科学会賞」(地域地理科学会) ●(2005.9.2)第1回「昭和シェル石油環境研究課題賞」(昭和シェル石油環境研究助成財団) ●(2006.2.10)平成17年度「国立大学法人大阪大学教育・研究功績賞」(大阪大学) ●(2012.6.16)平成22年度「大阪大学文学研究科・優秀教員表彰」(大阪大学・文学研究科) ●(2012.10.7)平成24年度「市民スポーツ・レクリエーション指導者表彰」(豊中市民体育振興協議会) ●(2013.6.5)平成24年度「大阪大学文学研究科・優秀教員表彰」(大阪大学・文学研究科) ●(2014.5.26)平成25年度「大阪大学文学研究科・優秀教員表彰」(大阪大学・文学研究科) ●(2015.6.11)平成26年度「大阪大学文学研究科・優秀教員表彰」(大阪大学・文学研究科) ●(2015.7.14)第4回大阪大学総長顕彰(研究部門) ●(2016.2.7)平成27年度大阪府スポーツ少年団功労者表彰(公益社団法人 大阪体育協会・大阪府スポーツ少年団) ●(2016.6.9)平成27年度「大阪大学文学研究科・優秀教員表彰」(大阪大学・文学研究科) ★団体受賞★ ●(2012.2.5)平成23年度「大阪府スポーツ少年団優良団表彰」(公益社団法人 大阪体育協会・大阪府スポーツ少年団) ●(2014.12.9)平成 26 年度日本政府観光局(JNTO)国際会議誘致・開催貢献賞(国際会議開催の部)(日本政府観光局(JNTO)):2013年京都国際地理学会議(IGU Kyoto Regional Conference 2013、主催者:京都国際地理学会組織委員会)に対して。堤は組織委員会委員・巡検委員長。 【所属学会】 日本地理学会(1983年~)、人文地理学会(1983年~)、経済地理学会(1986年~)、日本人口学会(1991年~)、日本社会分析学会(1994年~)、日本都市学会(中四国都市学会。のち近畿都市学会)(1994年~)、地理科学学会(1990年~)、地域地理科学会(1993年~)、島根地理学会(1990年~)、福岡地理学会(1983年~)。 【学会関係役職】 ●島根地理学会・常務理事(1990年度~1998年度) ●島根地理学会・幹事・事務局(1994年度~1997年度) ●経済地理学会幹事・渉外委員(1994年度~1995年度) ●中四国都市学会理事(1994年度) ●人文地理学会・協議員(1998年度~1999年度、2000年度~2001年度:任期2年2期) ●人文地理学会・庶務委員(1999年度、2000年度:任期1年2期) ●人文地理学会・地理思想研究部会・世話人(1999年度~2000年度:任期1年2期) ●人文地理学会・地理思想研究部会・世話人代表(2001年度~2003年度:任期1年2期) ●人文地理学会・地理学ウィーク企画委員(2001年度:任期1年1期) ●人文地理学会・評議員(2001年度~2002年度:任期2年2期) ●人文地理学会・大会準備委員(2003年度:任期1年) ●人文地理学会・選挙管理委員会委員長(2004年度:任期1年) ●人文地理学会・編集委員(2005年度~2006年度:任期1年2期) ●人文地理学会・大会準備委員(2005年度:任期1年) ●人文地理学会・協議員(2005年度~2006年度:任期2年) ●日本地理学会・代議員(2006~2007年度:任期2年) ●日本地理学会・E-journal Geo編集委員会閲読担当委員(2008~2009年度:任期2年) ●日本地理学会・E-journal Geo編集委員会閲読担当委員(2010~2011年度:任期2年) ●日本地理学会・代議員(2010~2011年度:任期2年) ●人文地理学会・評議員(2010~2011年度:任期2年) ●日本地理学会・代議員(2012~2013年度:任期2年) ●人文地理学会・評議員(2012~2013年度:任期2年) ●人文地理学会・人文地理学事典編集委員(2012~2013年度:任期不定) ●人文地理学会・将来構想検討委員会委員(2012年度:任期不定) ●人文地理学会・法人化検討委員会委員(2013年度:任期不定) ●人文地理学会・第14回学会賞(一般図書部門)選考委員会委員(2013年度12月~) ●IGU-2013京都会議・組織委員、巡検委員長(2012~2013年度:任期不定) ●AAG-Wiley, "International Encyclopedia of
Geography" 項目執筆者("Social Capital"担当)(2013-2014年度) ●日本地理学会・代議員(2014~2015年度:任期2年) ●人文地理学会・代議員(2014~2015年度:任期2年) ●人文地理学会・第15回学会賞(一般図書部門)選考委員会委員・委員長(2014年度12月~) ●人文地理学会・大会準備委員、大会実行委員会委員長(2015年度) ●The Global Conference on Economic Geography2021
Osaka大会実行委員会委員(2015年度~) ●The Global Conference on Economic Geography2018 Kölnアドバイザリー・ボード委員(2016年度~) 【公共団体等関連委員など】 ●長崎大学医学部衛生学教室:(1987年度~1990年度):客員研究員 ● ●九州大学文学部附属九州文化史研究施設考古学部門:(1990年度~92年度):研究員 ●建設省九州地方建設局:(1991年度):提言委員 ●島根県:(1997年度~2003年度):島根県航空行政推進会議委員・隠岐空港部会座長 ●建設省中国地方建設局および四国地方建設局:(1997年度~1998年度):「西中四国地方における広域連携整備計画調査」建設省委員 ●島根県:(1998年度~2004年度):島根県中山間地域研究センター地域づくり支援ブレーン ● ●国土交通省中国地方整備局:(1999年度~2000年度):「中国地方における多自然居住地域整備計画調査」国土交通省委員 ●島根県隠岐郡7町村ほか:(2001年度~2004.10):隠岐空港整備利用促進協議会オブザーバー ●東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所:外部評価委員(2012.10.1~2014.3.31) ●静岡県:人口減少問題に関する有識者会議委員(2014年度) 【地域連携教育実践ボランティア活動】 ●(2001.6~2014.11)財団法人 少林寺拳法連盟・新千里支部、現在の少林寺拳法豊中新田スポーツ少年団での少林寺拳法とスポーツ少年団活動の指導(豊中市立新田小学校) ●(2012.4~2017.3)豊中市スポーツ少年団本部・副本部長、豊能地区スポーツ少年団連絡協議会事務局担当 ●(2014.12~ )義和拳法会千里中央支部、千里中央スポーツ少年団での義和拳法とスポーツ少年団活動の指導(豊中市立新田小学校) 5)競争的教育・研究向け資金獲得状況 【科学研究費(研究代表者分)】 ●期間:平成2年度~2年度(1年間) 種目:文部省科学研究費・重点領域研究 研究課題名:「里山・牧野・奥山における林野利用の変 化」 課題番号:02243116 研究代表者:堤 研二 研究組織:3名(研究代表者のほか、藤田佳久、中島弘二の各氏) 交付金額:総額1,300千円(平成2年度:1,300千円) ●期間:平成10年度~11年度(2年間) 種目:文部省科学研究費・基盤研究(C)(2) 研究課題名:「地域空間の形成と変動に関する実証的お よび理論的研究」 課題番号:10680082 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:総額2,200千円(平成10年度:1,400千円、 平成11年度:800千円) ●期間:平成15年度~16年度(2年間) 種目:日本学術振興会科学研究費・基盤研究(C)(1) 研究課題名:「構造改革期における農山村・人口減少地 域の変動と政策課題」 課題番号:15520497 研究代表者:堤 研二 研究組織:6名(研究代表者・堤のほか、西原純・岡橋秀典・西野寿章・Kim, Doo-Chul・関戸明子の各氏) 交付金額:総額3,400千円(平成15年度:2,000千円、 平成16年度:1,400千円) ●期間:平成17年度~19年度(3年間) 種目:日本学術振興会・基盤研究(C) 研究課題名:「人口減少期の地域社会における集落システムと生活機能の維持に関する地理学的研究」 課題番号:17520534 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:総額3,400千円(平成17年度:1,300千円、平成18年度:1,300千円、平成19年度:800千円) ●期間:平成20年度~22年度(3年間) 種目:日本学術振興会・基盤研究(C) 研究課題名:「地域統計データにみる人口減少期の社会経済変動のトレンドと市町村合併のインパクト」 課題番号:20520684 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:直接経費総額3,200千円(平成20年度:1,900千円、平成21年度:800千円、平成22年度:500千円) ●期間:平成23年度~25年度(3年間) 種目:日本学術振興会・基盤研究(B) 研究課題名:「中山間地域における林業・森林環境と住民生活に関するマネジメント=モデルの構築」 課題番号:23320182 研究代表者:堤 研二 研究組織:10名(研究代表者のほか、小林茂、小林潔司、伊藤勝久、長澤良太、西野寿章、大田伊久雄、鳴海邦匡、松島格也、波江彰彦の各氏) 交付金額:直接経費総額11,600千円(平成23年度:3,600千円、平成24年度:5,800千円、平成25年度:2,200千円) ●期間:平成26年度~30年度(5年間):現在進行中 種目:日本学術振興会・基盤研究(A) 研究課題名:「中山間地域における林業合理化・森林管理・住民生活の為のマネジメント=モデルの構築」 課題番号:26244051 研究代表者:堤 研二 研究組織:9名(研究代表者のほか、小林茂、小林潔司、伊藤勝久、西野寿章、大田伊久雄、鳴海邦匡、松島格也、波江彰彦の各氏) 交付金額:直接経費総額24,800千円(平成26年度:5,200千円、平成27年度:6,000千円、平成28年度:5,300千円、平成29年度:4,600千円、平成30年度:3,700千円、) 【その他の助成(研究代表者分)】 ●期間:平成12年度(1年間):2000.12-2001.11 種目:日本証券奨学財団研究助成・経済学分野 研究課題名:「人口減少・高齢化地域における生活機 能・社会経済的地域機能の実態とIT支 援」 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:総額900千円 ●期間:平成14年度(1年間):2002.4-2003.3 種目:佐川交通社会財団・交通研究助成(一般研究) 研究課題名:「人口減少・高齢化地域における交通弱者の行動パターンと交通安全対策に関する研究」 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:総額950千円 ●期間:平成14年度:2002.6.10-2003.5.31 種目:河川環境管理財団・河川整備基金助成(一般) 研究課題名:「ダム建設に伴う水没・移転集落の自立的 再編成に関する研究」 研究代表者:堤 研二 研究組織:2名:分担者として今里悟之(大阪教育大学・ 講師) 交付金額:総額950千円 ●期間:平成17年度:2005.9.-2006.8 種目:昭和シェル石油環境研究助成財団・環境研究助成 研究課題名:「水をめぐる環境コモンズとsocial capital」 研究代表者:堤 研二 研究組織:1名(研究代表者のみ) 交付金額:総額1,500千円 【その他】 ●期間:平成22年度 種目:日本生命財団学術書出版助成 対象書籍名:『人口減少・高齢化と生活環境:山間地域 とソーシャル・キャピタルの事例に学ぶ』 直接助成先:九州大学出版会 交付金額:総額1,500千円 【大阪大学内教育関係経費(担当代表者分)】 ●期間:平成13年度(半年間):2001.10-2002.3 種目:平成13年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業 (全学共通教育機構) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:3名(堤 研二・小林 茂・今里悟之)、この 他、TAとして高橋淳一(MC2) 交付金額:総額1,330千円 ●期間:平成14年度(半年間):2002.10-2003.3(当年 度分の消耗品相当額分として) 種目:平成14年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業 (全学共通教育機構) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂)、この他、TAと して高橋淳一(MC2) 交付金額:総額200千円 ●期間:平成15年度(半年間):2003.10-2004.3(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成15年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業 (全学共通教育機構) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂)、この他、TAと して渡辺理絵(DC3) 交付金額:総額200千円 ●期間:平成16年度(半年間):2004.10-2005.3(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成16年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業 (全学共通教育機構) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:3名(堤 研二・小林 茂・鳴海邦匡)、この 他、TAとして中村有作(DC1) 交付金額:総額200千円 ●期間:平成17年度(半年間):2005.10-2006.3(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成17年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業 (全学共通教育機構) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂)、この他、TAと して波江彰彦(DC1) 交付金額:総額200千円 ●期間:平成18年度(半年間):2006.10-2007.3(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成18年度重点経費「体験的課題追求型授業科目 の構築プロジェクト」、体験的課題追求型授業(大阪大学大学教育実践センター) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂)、この他、TAと して波江彰彦(DC2) 交付金額:総額200千円 ●期間:平成19年度(半年間):2007.10-2008.3(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成19度重点経費「新型授業開発プロジェクト」、体験的課題追求型授業(大阪大学大学教育 実践センター) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂)、この他、TAと して波江彰彦(DC3) 交付金額:総額194千円 ●期間:平成21年度(半年間):2009.4-2009.9(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成21度重点経費「新型授業開発プロジェクト」、授業支援イニシャティブ(大阪大学大学教育実践センター) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂) 交付金額:総額146千円 ●期間:平成22年度(半年間):2010.4-2010.9(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成22度重点経費「新型授業開発プロジェクト」、授業支援イニシャティブ(大阪大学大学教育実践センター) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:2名(堤 研二・小林 茂。後に波江彰彦を追 加) 交付金額:総額150千円 ●期間:平成23年度(半年間):2011.4-2011.9(当年度 分の消耗品相当額分として) 種目:平成23度重点経費「新型授業開発プロジェクト」、授業支援イニシャティブ(大阪大学大学教育実践センター) 対象授業名:「人文地理学セミナー」(基礎セミナー科 目) 担当代表者:堤 研二 担当組織:3名(堤 研二・小林 茂・波江彰彦) 交付金額:総額130千円 【科学研究費(研究分担者・研究連携者分)】 ●期間:平成3年度~3年度(1年間) 種目:文部省科学研究費・重点領域研究 研究課題名:「中部および東北日本の山間村落における 林野利用の変化」 課題番号:03227110 研究代表者:西野寿章 研究組織:4名(研究代表者のほか、研究分担者として堤 研二、中島弘二、関戸明子) 交付金額:総額1,300千円(平成3年度:2,500千円) ●期間:平成10年度~10年度(1年間) 種目:文部省科学研究費・基盤研究(C) 研究課題名:「地方の知と技術革新:地方生活圏(ふる さと)の充実をめざして」 課題番号:10898001 研究代表者:松尾容孝 研究組織:6名(研究代表者のほか、研究分担者として小 林潔司、伊藤勝久、堤研二、福山敬、喜多秀行) 交付金額:総額600千円(平成10年度:600千円) ●期間:平成18年度~20年度(3年間) 種目:文部省科学研究費・基盤研究(B) 研究課題名:「グローバル化時代における公共空間と場 所アイデンティティの再編に関する研究」 課題番号:18320136 研究代表者:高木彰彦 研究組織:27名(研究代表者のほか、研究分担者10名、 連携研究者13名、研究協力者3名。堤 研二は連携研究者として参加) 交付金額:総額17,730千円(平成18年度:5,900千円 (直接経費:5,900千円)、平成19年度: 6,110千円(直接経費:4,700千円、間接経 費:1,410千円)、平成20年度:5,720千円 (直接経費:4,400千円、間接経費:1,320千円) ●期間:平成22年度~24年度(3年間) 種目:文部省科学研究費・基盤研究(B) 研究課題名:「現代山村における非限界集落の存立基盤 に関する研究」 課題番号:22320172 研究代表者:西野寿章 研究組織:9名(研究代表者のほか、研究分担者として藤 田佳久、合田昭二、岡橋秀典、堤 研二、伊藤達也、関戸明子、高柳長直、中川秀一) 交付金額:総額18,200千円(平成22年度:8,060千円 (直接経費:6,200千円、間接経費:1,860千円)、平成23年度:6,630千円(直接経費:5,100千円、間接経費:1,530千円)、平成23年度:3,510千円 (直接経費 : 2,700千円、間接経費 : 810千円) 【その他】 ●1995~96年度:文部省大学入試センター教科専門委員会委員(地理部会) ●1997年度:文部省設置審議会大学院修士課程担当「合」(地理学特別演習ほか担当) ●2008.12.1-2009.11.30:日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(第1段審査委員:人文地理学) ●2009.12.1-2010.11.30:日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(第1段審査委員:人文地理学) |
|
「堤 研二のホームページ」 |