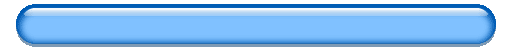
発表風景
 |
第3回 長尾山古墳発掘勉強会(7月25日) 最終回となる本日の発表は3回生の大川さんによる「古墳時代概説」と院生の高上くんによる「長尾山古墳の埴輪の評価にむけて」でした。 大川さんの発表は古墳時代の全体像を概観したものです。高上君の発表では調査で出土するであろう前期後半から中期の摂津の埴輪にいかに研究課題があるかという中心に議論が集中しました。 |
| 第2回 長尾山古墳発掘勉強会(7月18日) 寺前助教による古墳調査の心構えと3回生の露原さんによる埴輪の概説的な発表がありました。 |
|
 |
第1回 長尾山古墳発掘勉強会(7月11日) 今回からは、今夏測量および発掘調査を予定している兵庫県宝塚市長尾山古墳の調査準備のための勉強会が始まりました。 まずは、3回生2名による周辺の遺跡の概要の紹介がありました。その後、福永伸哉教授から調査の目的について、周辺の古墳の状況、猪名川流域の首長系譜の問題について紹介がありました。 今回の調査では研究室にまだ所属しない学生や他大学からの参加者も多く、大変大所帯になりそうです。 これから数回にわけて発掘調査にむけた準備を着々と進めていく予定です。 |
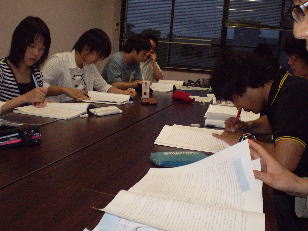 |
篠大谷3号窯科研報告書検討会 今回はこれまでと異なり、この春に刊行した京都府の平安時代の窯跡である篠大谷3号窯の中間報告(科研報告書に掲載)をふまえ、教員と学生が問題点や今後の課題を話し合いました。 現在、大谷3号窯出土の膨大な須恵器や緑釉素地などを定量的に分析し、各遺構間での接合関係を検討しています。その成果についても本HP等で紹介していこうと思います。 |
 |
酒井将史 篠窯跡群の変質過程−器種組成上の変化を中心に− 大学院生の酒井氏による大阪大学が発掘した大谷3号を 含む篠窯跡における器種組成の変遷を細かに追った 研究発表です。データとしては器種組成の他にも胎土や 焼成の違いが問題となり、緑釉とその素地そして須恵器の 関係が問題となりました。 |
 |
田中由里 日本・韓国出土心葉・楕円形鏡板付轡・ 杏葉の比較検討−形態比較を通して− 今回は去年まで韓国に留学していた田中さんが これまでの日本出土品の馬具研究をふまえて、 朝鮮半島出土資料との比較を画像をまじえて 発表しました。 |
 |
野島智実 大谷3号窯併行期における武蔵国の須恵器生産 今回は、篠大谷と時期的に平行する関東の須恵器生産が、 紹介されました。糸切りなどのありかたの違いに注目があつまりました。 |
 |
木村理恵(M2) 大谷3号窯出土鉢の型式学的検討 本日は篠窯を論じる上で欠くことのできない鉢の形態変化についての分析が報告されました。 口縁部の形態変化をどのように理解するかをめぐって議論がありました。 |
 |
高上 拓(M2) 大谷3号窯出土稜椀の評価に向けて 今回は篠窯を評価していくうえで不可欠な緑釉陶器についての分析です。 製作手順などをめぐって白熱した議論が繰り広げられました。 |
 |
中久保辰夫(M2) 篠窯跡群における須恵器椀の出現とその背景 今回からは去年度で調査が終了した京都府亀岡市篠窯跡群 での調査成果をふまえた発表がしばらく続きます。 本日は大谷3号窯から出土した須恵器椀について中久保君が、発表しました。 |
 |
寺前直人(助教) 古墳と古墳時代社会と国家形成 GW明けの最初の研究発表は、都出比呂志先生が提唱された前方後円墳体制について、助教の寺前さんが、最近の古墳時代研究の動向を交えてまとめられました。 |
 |
前田俊雄(M2) 横穴式石室非導入地域について 本年度最初の研究発表は大学院生の前田さんでした。 7月に行われる研究会での準備発表として、 近畿地方の古墳時代後期の横穴式石室がない地域をとりあげ、 その背景を論じました。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる