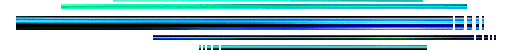
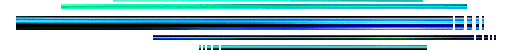
1日目
2014年度研究室旅行の行先は、壱岐・長崎。
集合場所の博多港からフェリーに乗って壱岐島まで渡ります。
到着直後に「割烹豊月」さんでお昼をいただきました。
天ぷら定食と煮魚定食の2択です。さすが島です、海の幸がおいしいですね。
ごはんの後はさっそく古墳見学!
この日は島の中心部にある壱岐古墳群をまわります。
6世紀後半〜7世紀頃に大きな古墳が集中して築かれ、対馬で古墳が少なくなるのと入れ替わるように壱岐島では盛んに古墳がつくられます。
最初に向かった双六古墳で壱岐市教育委員会の松見さんと合流。
この日1日、案内・解説役を引き受けていただきました。
双六古墳は長崎県でも最大の前方後円墳で、計量スプーンをひっくり返して置いたようなこんもりとした墳丘が特徴的。石室のなかも今回特別に見学させていただきました。入口にはお供えがあり、今でも信仰の対象となっているそうです。
次は鬼の窟古墳。石室が開放されており、中に入るとライトアップされます。閉塞石もそのままで臨場感たっぷりです。
その次は笹塚古墳。金銅装馬具が発見されたことで有名です。双六古墳も鬼の窟古墳もそうでしたが、このあたりの横穴式石室は「巨石古墳」と呼ばれ、非常に大きな石を持ってきてかなりのこだわりを持って組み立てられています。笹塚古墳ではちょっと大きさの足りない巨石の継ぎ目をごまかそうとする石室職人のちゃっかりした一面が垣間見えます。
ここで時代は離れますが、生池城という中世の山城を歩いて回りました。まわりを囲む堀が巨大で、当時の山城の様相が生々しく残っています。
再び古墳時代に戻り、百合畑古墳群を歩きます。小円墳が何個も連なっていて、歩道や石室入口が綺麗に整備されていました。
最後は掛木古墳に行きました。古墳のすぐ横には民家があり、特徴的なこんもりした墳丘が北風避けになるそうで、このあたりでは山の南におうちを建てることがよくあるそうです。石室内には壱岐で唯一発見された刳抜式石棺が置かれています。
以上でこの日は見学を終え、宿へ向かいました。国民宿舎「壱岐荘」でお世話になりました。温泉が最高な宿でした。
2日目
2日目の始まりは一支国博物館。
入口でパンフレットと一緒に有料展示ゾーンに入れるステッカーをもらいました。亀形馬具、弥生の舟、人面石などデザインが数種類あるのでどれが当たるか楽しみですね!
昨日に引き続き壱岐市の松見さんに案内していただきました。この博物館は内装やパネル、展示の順序までよく練られていて、展示室を歩くのがわくわくでした。ここの年表はなんと現代からだんだん過去へ遡る逆行形式です。
博物館の展示は地元愛にも溢れています。原の辻遺跡を舞台に一支国の都を描いたムービーはすべて地元の人が出演しているそうで、とてもリアルにできています。一支国を再現したミニチュア模型も地元の人から顔を募集して作ったそうで、ひとりひとり個性が光っています。
一通り見学した後、同じ建物内にある長崎県立埋蔵文化財センターで調査研究や保存処理の現場を見せていただきました。木製品のPEG処理施設や金属製品の処理の様子、数々の特殊機器など、なかなかみることのできない豪華な研究施設で、最近の科学のちからを目の当たりにしてきました。3Dプリンターってすごいですね。
文化財を保存し、研究や普及に活かすためのプロフェッショナルな世界を見せていただき、大変貴重な勉強となりました。
昼食は「ふうりん」さんで、刺身定食をいただきました。新鮮なお魚はお醤油と相性抜群ですね、島に来てよかったです。
昼食後はカラカミ遺跡に行きました。この遺跡は弥生時代の鍛冶遺構があり、見学の際は発掘調査中でした。壱岐市の松見さんが再び登場、遺跡の紹介をしてくださりました。何から何まで本当にありがとうございます。この遺跡は海に囲まれた壱岐島にあってかなり内陸山間部に位置することから、当時の鉄器生産が重要な役割であったことがうかがえます。
バス移動の途中で、お土産屋さんのうにハウスに寄り、みんな家族、友人、部活など思い思いの人へのお土産選びをしました。うにアイスなどユニークなものも売っていました。その後、原の辻遺跡の復元公園へ向かいます。建物、柵列、植物など弥生時代をしており、周囲の広々とした田園風景とも馴染んでいました。遺跡のための景観保護も整っているそうで、かつて栄えた一支国の首都の広大さを感じます。
たくさんの遺跡を巡った壱岐ともいよいよお別れです。印通寺港からフェリーに乗って唐津へ向かいます。行きの高速船とはうって変わって、ゆるゆるとした乗船時間で、寝たり海を眺めたりして過ごしました。
3日目
ついに最終日!最初に向かったのは長崎県松浦市の鷹島歴史民俗資料館。
ここはなんとかつて元軍に侵攻された地です。そして文献史上で有名な、暴風雨で沈没した元寇船が近年発見されました。資料館の山下さんに解説をしていただきながら、発掘された元寇にまつわる考古資料を見せていただきました。歴史の教科書でおなじみの「てつはう」の実物もここにあります。水中考古学というなかなか身近にない分野でしたが、歴史探究の手法ひとつとしてとても興味深く見学させてもらいました。ありがとうございました。 次は平戸に向かいます。
到着してすぐ「一楽食堂」さんで昼食。長崎ちゃんぽんをいただきました。野菜もお肉もたっぷりでおなかいっぱいです。
午後からは平戸オランダ商館に行ってきました。
建物は発掘で見つかった柱穴などから1639年に建てられた商館の倉庫を忠実に復元したそうです。掲げられた築造時の年号がキリスト教にちなむ西暦であったため、徳川家康が怒って取り壊させたそうで、今は1639の年号の掲げられた状態で復元されています。
研究室OBの赤木さんに案内していただきながら、当時の貿易にまつわる絵画や地図、貿易品の陶磁器などたくさんの展示資料を見学しました。徳川家康直筆の貿易許可をする朱印状の実物など、徳川政権下も海外貿易拠点として認められてきた平戸の歴史が感じられます。
お忙しい中丁寧に解説をしていただいた職員の方々、ありがとうございました。
オランダ商館の見学後、岳崎古墳にバスで向かいます。今回の旅行最後の遺跡です。岳崎古墳は5世紀中頃の前方後円墳で、列島内で最も西にある前方後円墳とされます。登れる前方後円墳、楽しいですね。
この後バスで博多まで戻り、解散となりました。
壱岐島・長崎という遠出の長旅でしたが、なかなか行けない遺跡・博物館・資料館などじっくり見学することができ、貴重な経験となりました。
今回の研究室旅行では壱岐市、鷹島歴史民俗資料館、平戸市の方々に大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。
(文責:3回生H)
戻る