 |
研究室だより(2005.10〜) |
 |
今年度は3名が課程博士学位請求論文を提出し,その公開試問が行われた。提出者の試問期日と題目は以下の通り。
公開試問は、まず学位申請者が提出した論文の要旨を述べ(30分程度)、主査・副査(2名)の教員からの試問・コメントを受けそれに答えた後(1時間程度)、教員をはじめ本研究室に在籍する学生・院生といった参加者からの質問を受けるという形で進行した。
学外からは、横山の試問に濱島敦俊本学名誉教授(現・台湾曁南国際大学・教授)、蓮田の試問に嶋尾稔氏(慶應義塾大学・助教授)にご参加をいただいた。
2006年1月25日(水)、元中国社会科学院歴史研究所研究員である陳智超氏をお招きし、阪大に於いて「基盤研究(B)「近代世界システム以前の諸地域システムと広域ネットワーク」小規模國際シンポジウム「中國史料の世界」と題するシンポジウムが行われた。
陳氏は「史料の収集・解読と利用(文獻的收集解読與利用)」と題して講演を行ない、明版『名公書判清明集』発見から標点本出版に至る書誌学的知見、祖父・陳垣を中心とした陳家の活動の軌跡などを披露された。さらに近著『陳智超自選集』(安徽大学出版社,2003年)の紹介も行われた。その後青木敦助教授が「行政としての裁判−宋代判語に見る民事的法律と土地典賣−」と題する研究報告を行い、濱島敦俊名誉教授が両氏の報告へのコメントを行う形で進行した。
陳氏は『宋会要輯稿補編』(新華書店,1988年)、『名公書判清明集』(中華書局,1987・2002年)の編集に携わったことにより広く知られているが、書誌学を中心とした分野でも多くの作品を著している。
12月21日から1月2日にかけて、岡田雅志(D1)とハノイ留学中(※)の牧野直子(M2)の2名がベトナム・ニンビン省で行われた紅河デルタ村落史料調査に参加した。本調査は、紅河デルタの開拓史を村落史料から再検討することを企図したものであり、広島大学八尾隆生助教授を団長に、日本側は大学教員3名、院生2名(岡田・牧野)、学部生1名、ベトナム側はハノイ国家大学のスタッフ2名を団員とする共同調査である。近年、ベトナムでも「近世史料革命」と呼べる状況が生まれ、外国人研究者が直接、村落史料にアクセスできるようになっており、ベトナム史研究は新たな段階に入ろうとしている。本調査においても、この時期特有の寒風に苦しみつつも、団員たちは次々と発見される貴重な村落文書を前に興奮の声をあげた。本調査は、今後もナムディン省・タイビン省に調査地を移して続けられる予定である。
 |
 |
ここに掲載した2枚の写真のうち、左の写真は某族祠堂内の祖先を祀る祭壇である。新調したと思われる対聯・扁額の漢字の下に現代ベトナム語による翻音が併記されている。右は、最近では珍しい伝統的様式を残す家屋の写真である。
12月12日から20日にかけて、片山剛教授・大坪慶之(D3)の二名が中国・広東省において、1930年代の中国大陸における土地調査事業に関する文献・実地調査を行った。
両名はまず広東省档案館・孫中山文献館において文献調査を行ったのち、高要県小湘鎮を視察した。またこの課題とは別に、順徳県龍江鎮において「紫雲閣」と呼ばれる仏教寺院の実地調査も行った。今回の視察はいずれ本格的な実地調査を行うための予備調査であり、本調査は2006年以降に行われる予定である。

12月10日・11日の2日間、上智大学で行われた東南アジア史学会第74回研究大会において、D1の岡田(ベトナム近世史専攻)が研究発表を行った。
題目は「ベトナム西北地方、黒タイ・ムオンの成立に関する一考察〜18、19世紀におけるベトナム王朝との関係分析から〜」である。
小松久男教授(東京大学大学院人文社会系研究科)をお招きして、今年
度後期の集中講義が五日間の日程で行なわれた。
今回は「中央アジア近代のイスラーム復興」と題され、先生のご専門で
ある近代における中央アジアのイスラームが主題であった。講義は中央ア
ジアのトルコ化とイスラーム文明の普及から説き起こされ、ロシアよる植
民地化以降のムスリムの活動が中心の内容であった。
近代の中央アジアは、トルコ人、ロシア人、ムスリムの活動が絡み合
い、政治・文化などの面において複雑な状況にあったが、それを先生は、
タタール商人の活動、ブハラ、ヒヴァ、コーカンド三国でのチンギス家の
権威、ロシア植民地化以降のムスリム社会の変容とその反応(アンディジ
ャン蜂起、ジャディード運動)などといった幅広い切り口で講義を展開さ
れた。特に、これまでの先生の諸論文で扱われたテーマについて、その後の史料
状況の改善による新たな成果を付け加え、さらに今後の研究の可能性をも示された点は、
受講者に研究というものの面白さを改めて感じさせてくれた。
我々の研究室は前近代の中央アジアに一つの力点を置いていることもあ
り、近代の中央アジアは知識が不足しがちな分野である。しかし、歴史を
研究対象とする限り通時的理解は欠くべからざることである。その点、今
回の先生の丁寧な説明は出席した学部生・院生に益するところ大であった
。なお、近年イスラーム世界は国際情勢を考える上で特に重要な
地域となっており、そのため様々な分野の学生が多く出席したことを付記してお
きたい。

本研究室の院生、梶原(D3)が今年九月より北京に留学している。彼から北京の著名な史跡の写真が届いたので、その一部をここに紹介したい。
 |
 |
上掲の写真二点は、北京の名勝のひとつである天壇公園で撮影されたものである。左は冬至に天を祀った祭壇である圜丘壇、右は皇帝の位牌を安置する廟で皇穹宇と呼ばれる。
このような史跡に直接触れることのできる留学は研究のうえで貴重な財産となる。北京での厳しい冬を迎える中、ますますの知的研鑽に励まれたい。研究室一同の思いである。
12月1日(木)、来年度卒論を執筆する三回生を対象に第一回目の卒論相談会が行われた。学部三回生には卒業論文提出一年前のこの時期に、卒論の構想を発表し院生・教員からの助言を得る最初の機会が与えられる。
今回発表された題目は次の通り。
今回、発表者の三人は自らの関心とテーマを明示し、更にそのテーマに関する現在の研究動向の報告を行った。質疑の際に出されたアドバイスにより、現在の問題点をより明らかにすることが出来たと思われる。この機会を利用して、更に具体的な作業に繋げてほしい。
11月4日(金)、恒例の文学部研究室対抗ソフトボール大会が開かれた。今季の大会では、二大会連続で四位と振るわなかった東洋史チームに活を入れるべく、留学していた元主将の大坪(D3)が一時帰国し、戦列に復帰した。
一回戦は対哲学戦。わがチームは、浮き足立っていた初回こそ2点を先制されたものの、その裏の攻撃から落ち着きを取り戻し、打線が大爆発して37対4というスコアで圧勝した。続く準決勝の対日本史学戦は、ルーキー林(2回生)の攻守にわたる活躍により熱戦を制し、東洋史チームが14対11で逃げ切った。決勝戦では英米文学チームと雌雄を決することになった。ところが、それまでの疲れが出たのか、わが研究室が誇る東洋史マシンガン打線がさっぱり機能せず、今年の日本シリーズの某チームの如くなすすべもなく0対4で2安打完封負けを喫し、二位に甘んじたのであった。
試合後は研究室に戻って残念会が行われ、栄えある主将賞には今季限りで引退する浦川(M2)が選ばれた。
今季の敗因は、主力メンバーの体力の衰えに尽きると言っても過言ではない。今後は「鍛えよ肉体!」を合言葉に、伊藤主将には自らの進退をかけてチーム力アップに取り組んでもらいたい。
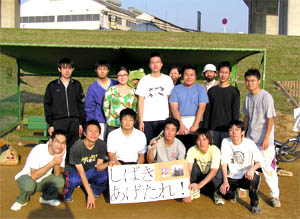
10月22日(土)、南京大学歴史系副教授の夏維中氏(明清江蘇社会経済史)が大阪大学で講演された。「明代南京の城磚銘文について」と題した今回の講演は、明初の南京都城建築の際に用いられた建築資材である磚に着目し、そこに刻まれた銘文の内容から、明代の南京都城の構造や、磚の産地・製造・運搬の過程を明らかにするものであった。氏はさらにそこから里甲制成立以前の長江中・下流域の徭役形態にまで言及された。
従来の文献史料のみによる研究にとどまらない斬新な研究方法や視点は、聴衆にとって大変示唆に富むものであった。
10月6日・20日・27日の合同演習で今年度二回目の修士論文構想報告が行われた。各人、持ち時間の二時間(発表1時間半、質疑30分)を目一杯使い、これま
での研究成果を発表した。合同演習は、学部二年生から院生・教員までを含めた本研究室に所属する全員が出席しているので、修士論文の構想発表とはいえ、出席者各自の研究
分野や知識に配慮した、誰にでも理解できる発表が求められる。修士論文執筆のために
ごく限られた専門分野を勉強していると忘れがちなことであるが、これはおよそ論文と
いうものを執筆する際には注意すべきことである。
発表者にとっては論文執筆前に自らの知識や研究の意義を再確認する良い機会となった
はずである。
発表者には今回の発表・質疑を踏まえ、提出期限までの残り少ない時間を
有意義に使ってもらいたい。今年度の発表者とその題目は以下の通りである(発表順)。
・白玉冬 「韃靼の移住に関する一考察」(10/6)
・山本一 「嘉慶・道光期の地方官僚と知識人 ―阮元と詁経精舎・学海堂を中心に―」(10/20)
・浦川政輝 「北宋の治安維持政策」(10/27)
秋セメスターに入って間もない10月15日(土)、今年度の卒業論文執筆予定者を対象とする相談会が、半日を費やして行われた。
今年度卒業論文を執筆する者にとって、研究室全員の前で作業の経過を発表する機会は今回が最後となる。発表者は夏季休暇を含む前回から半年あまりの期間に取り組んだ作業の成果・進捗具合の報告を行い、それに対して教員や他の院生・学生が助言・批評を行った。
今回の発表者の題目は以下の通り。
今回は都合三回目の相談会ということもあり、執筆者は各々史料を読み込んで厳密な検討を行うことを求められている。しかし、発表者の中にはそうした要求に応えられずにいる者もおり、質疑応答の際には「作業量が未だ充分ではない」「自論と先行研究との差異が明確ではない」などといった厳しい指摘があいついだ。
卒論執筆者は今回出された指摘を真摯に受け止め、水準の高い卒論を完成されたい。