大阪ラスキン・モリスセンター収蔵品よる企画展
今に生きるラスキン
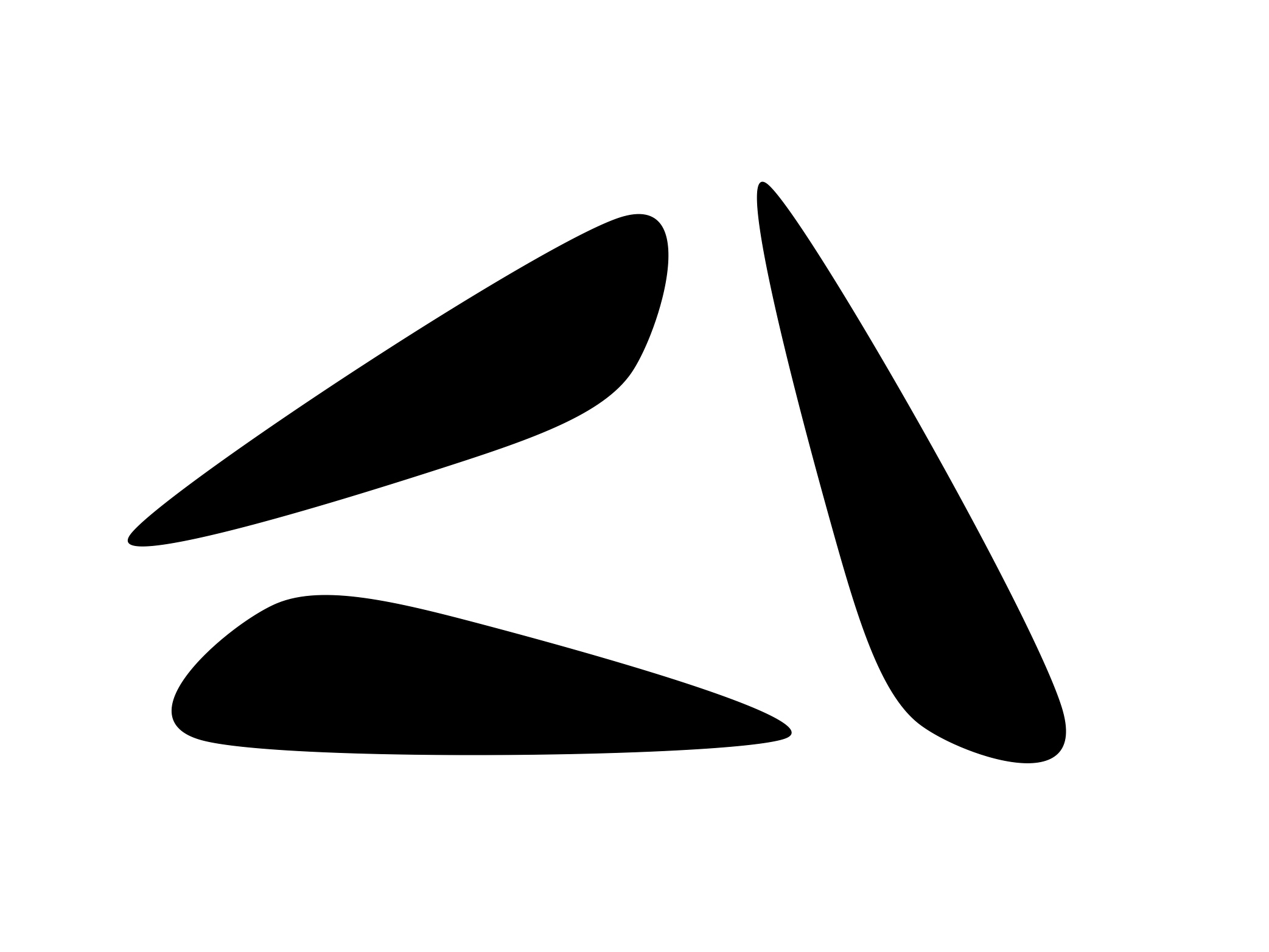
今に生きるラスキン展
期間:2024年9月20日(金)〜10月20日(日)
場所:大阪大学中之島センター4階ギャラリー
主催:大阪大学中之島芸術センター
協力:大阪ラスキン・モリスセンター studio-L
詳細:パンフレット
第1部 ラスキン多面体
1819年ロンドンに生まれたラスキンは、6歳で初めてヨーロッパ大陸を旅し、12歳で素描を学び始めた。 1832年J・M・W・ターナーの絵画世界に出会い、翌年アルプスの山嶺の美を知る。 1837年オックスフォード大学に入学したラスキンは、『近代画家論』(第1巻、1843年)で美術批評家として登場した。 鋭い観察眼に支えられたラスキンの批評は、芸術が生まれる場としての社会や自然環境それ自体にまで及んでいく。 1870年代には社会福祉や環境保護の実践にも乗り出し、人間の生きかたを問い直した。
第2部 聖ジョージ・ギルド
芸術の衰退を、汚染と搾取という自然と社会のモラル低下の象徴ととらえたラスキンは、 経済へと議論の幅を広げ、1860年から『コーンヒル・マガジン』にて「この最後の者にも」の連載を始めた。 人々の命にこそ富の源泉を見る彼の新しい経済論は当時非難されたものの、 やがて市場経済と大都市中心の社会に対して、中世に見られた農村社会を理想とするプロジェクトへと発展する。 こうして1870年代後半に生まれたのが聖ジョージ・ギルドである。 ギルドはラスキンの思想を土台として、現在も活動を続けている。
第3部 コミュニティ実践
大阪ラスキン・モリスセンターは、2006年に露木紀夫の私設資料館として設立され、 2019年に一般財団法人となってstudio-Lと共同で、多くの人々に開かれた施設として再出発しようとしている。 大阪府能勢町にあるセンターは、ジョン・ラスキンや、彼の思想に影響を受けたウィリアム・モリスに関係する資料を管理している。 これらの資料は、露木が30年以上かけて各国の古書店から集めたものである。 センターは、貴重な資料を学術研究に役立てるとともに、ラスキンに学びながら地域の生活を豊かにすることを目的として活動をおこなっている。