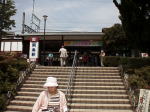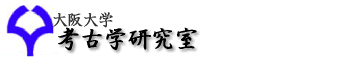 −研究室小旅行記・明日香編−
−研究室小旅行記・明日香編−
| 参 加 者 の 声 |
新歓小旅行に参加して 「午前10時に近鉄飛鳥駅集合。昼食は持参の事」
今年の新歓小旅行は飛鳥の見学である。当日の天気は晴れ。しかし、これを好天とみなすかどうかは各人によって意見の分かれるところだろう。 10時集合と言うことであったが交通機関の関係上、約半数の人々が微妙に遅れることとなってしまった。飛鳥駅は他の団体の人々の待ち合わせ場所になっていたようで、結局10時過ぎに私達が出発するころには、他に2つの団体さんで人口密度が上昇していた。このうち片方の小学生の団体は、どうやら自転車という文明の利器を使用するようであったが、考古学研究室のメンバーは徒歩。
?時頃、高松塚にて諸々の事情により遅れてこられた福永先生と合流。ここには小学生たちがすでに到着しており、休憩状態にはいっていたが、私達は先へと進んだ。この後、彼らの姿をあまり見かけなくなる。 福永先生と清家助手が先頭に立ってサクサク進まれる一方で、この頃から皆の暑さに対する疲労が蓄積されつつあったようである。徐々にではあるが、口数が
やや元気を回復した後、石舞台古墳へと向かった。やはり飛鳥といえばこの古墳なのであろうか。朝とは違った団体さんがいっぱいである。ここへは何度も来たことがあるが、わずかとはいえ古墳に関する知識を得た後見ると、漠然とおっきーという感想しか持てなかった時とは違うことに気づきなんだか嬉しかった。しかし、石舞台の墳丘への階段は行く度にどんどん進化しているように思われるのは気のせいだろうか。
一日のうち最も気温の高い時間帯が過ぎても、疲れはどんどん溜まっていく一方である。そのせいかどうかは分からないが、菖蒲池古墳で童心に帰った人が数名。フェンスの向こうにわずかに見える石棺を見る順番待ちの間に、近くに生えていたカラスノエンドウで笛を作ろうと試みたのである。しかし昔の記憶はそう簡単には呼び戻すことはできず、成功者はいなかったようである。ちなみにこの古墳の石棺をオートフォーカスカメラできれいに撮ることはかなり高度な技が必要である。
最後に向かったのは欽明天皇陵との説もある見瀬丸山古墳。全長約310メートルの巨大な古墳である。伸びた草の中、獣道を作りながら墳丘を上っていくと驚くような景色が広がっていた。大和三山のひとつである畝傍山がちょうど正面に望むことができ、その手前には原っぱが広がっていたのである。それが丸山古墳の前方部であるとはすぐには気づけなかった。それほど巨大なのだと圧倒された。やはり紙の上での数値を知っているだけでは、本当のすごさは理解できないということを実感させられた経験である。これはこれから考古学を学んでいく上で大切な事だと思う。 この時、歓迎会の会場予約時間の都合上、乗らなければならない電車の時刻が迫っているということを知らされた。そのため丸山古墳に対する感動もそこそこに、セカセカと最寄駅へ急ぎ、一路難波へ。 会が始まり腰を下ろしたため、一日の疲れが押し寄せてきた人も多かったようである。しかし、最初は無口だった人も次第に元気を取り戻しはじめたころ、都出先生が御登場になられた。御元気そうでなによりである。その後いつものように楽しい会となったのである。しかし、途中で帰宅した私には二次会以降のことはわからない。 一日を通じて、非常に疲れるスケジュールではあったが、反面非常に濃い内容のものであったと思う。ただ遺跡を見学する以上のものを学ぶことができたのではないかと思われるのである。とにかく研究室の皆様ご苦労様でした。 文:三回生中川 |
Copyright 1999 大阪大学考古学研究室 (Osaka University Department of Archaeology) All rights reserved
無断転載はご遠慮下さい
e-mail:seike@let.osaka-u.ac.jp