研究会・学術・学習情報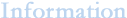
『パブリック・ヒストリー』
◆◇ 第9号(2012年2月出版) ◇◆
栗原麻子「総論 ソシアビリテ論と紛争研究の接点をめぐって」、1-4頁
栗原麻子「1 古典期アテナイにおける互酬的秩序―課題と展望―」、5-14頁
中尾恭三「2 マグネシアのアシュリアと国家間関係」、15-28頁
森新太「3 他都市における同職組合―在ボローニャ・フィレンツェ商人組合規約―」、29-36頁
紫垣聡「4 ドイツ中近世の地域社会における秩序形成をめぐる研究状況」、37-46頁
水田大紀「5 パトロネジの「終焉」―近代イギリスにおける官僚制度改革と能力主義の浸透―」、47-53頁
北村昌史「6 互酬性からみた近代ドイツ社会―結社と社会国家―」、54-63頁
特集 世代と歴史学のいま 第3回
Lars KLEIN, "Vietnamkriegs-Berichterstatter als unerreichtes Vorbild? Selbst- und Fremdzuschreibungen einer Reporter-Generation", 64-79頁
上田耕造「公益同盟戦争―ブルボン公ジャン2世とルイ11世との相補関係―」、80-94頁
福島邦久「18世紀におけるオランダ東インド会社とアジア経済―綿と貴金属の貿易を通して―」、95-114頁
岩﨑佳孝「南北戦争後のアメリカ先住民連合による立憲共和政体構想―インディアン・テリトリーにおけるオクムルギー会議(1870-1878)―」、115-133頁
書評 134-141頁
- 酒井一臣「藤川隆男著 『人種差別の世界史―白人性とは何か―』」、134-136頁
- 宗村敦子「竹内幸雄著 『自由主義とイギリス帝国―スミスの時代からイラク戦争まで―』」、136-141頁
第16回ワークショップ西洋史・大阪 報告要旨 143-146頁
- 波部雄一郎(関西学院大学)「初期ヘレニズム期東方におけるディオニュソス崇拝―プトレマイオス・フィロパトルによる巨大船建造の意義―」
- 奥山広規(広島大学)「碑文における字形分析から何を言えるのか」
- 田中玉美(名古屋大学)「メロヴィング期ガリアにおける医師の役割」
- 法花津晃(九州大学)「10世紀と11世紀初頭マコネ地方における在俗聖職者と文書」
- 中川順子(熊本大学)「近世イングランドにおける他者とその境界」
- 藤川隆男(大阪大学)「オーストラリアのアジアへの接近と白豪主義の終焉」
執筆者紹介(HTML)