スタッフ・学生紹介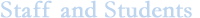
学生担当論文の紹介 10章
10.The future of dreams: from Freud to Artemidorus SIMON PRICE
中山 裕介
本論文は、夢の研究に関して、現代精神分析学の創始者であるフロイトと、紀元2世紀ころ、ローマ世界で活躍したアルテミドロスという人物を比較し、両者の特性、類似点、相違点などを検討しようとするものである。それによって、現代と古代とでは、夢の本質の捉え方が対照的であることを明示するのに成功している論文であるといえよう。論文の構成としては、まず序論で本論文の主旨と狙いを述べ、それ後4つの節を設けて議論を展開する形をとっている。第 1 節は、自民族中心主義についての議論である。フロイトをその始祖とする精神分析学は、自民族中心主義的要素の濃い学派であり、自らの理論を他の学問分野へ適応させようとする傾向がしばしばみられる。それは、精神分析学に社会的に普遍な妥当性と、 hard な科学としての地位を与えたいという、彼らの願望から生じたものなのだろう。したがって、夢の研究においてもフロイトのモデルを古代のモデルに当てはめようという試みがなされてきたのである。しかし、 Price はこのような態度を強く批判している。そのような「現代→古代」という単純な図式は、歴史学的、論理的に問題があり、適切ではないとしている。この批判は、古代が必ずしも現代より劣っているわけではないという認識を持ったものであり、かなり適切は判断であると私は考える。
次に、第 2 節では、アルテミドロスの夢解釈が、実際どのようなシステムであったかが紹介されている。アルテミドロスはまず、夢を、未来を示す夢( oneiroi )と、現在を示す夢( enhypnia )に分けている。そして、夢解釈者は、 oneiroi をその仕事として扱うべきだとし、 enhypnia は欲望や恐怖など、 dreamer の思考と関連する即時的な夢なので、解釈の対象にすべきでないとしている。ここには、「精神の正しい人は情動によって動かされない」という、ストア派の影響が色濃く現れているといえよう。そのような分類の上で、 oneiroi を解釈する際の原則について述べている。すなわち、夢解釈の原則は、メタファーによる心像( dream imagery )の現実での結果( actual outcome )への結びつけという、類似性の並列に則っているとするのだ。その際の留意点として、完全に覚えている夢のみの使用、解釈者の深い知識、 dreamer の詳細な情報の必要性をあげている。 dreamer の詳細な情報とは、出生、財産、健康状態、年齢、習慣、癖、精神状態、社会的地位などのさまざまな要素のことであり、このことの強調は・ u 椦 @w) ロイトの理論では見られないことである。 Price はここから personality に関する問題にふれているが、説得力のある論になっているとはいえない。アルテミドロスとフロイトの違いは、近親相姦の夢の解釈においても見ることができる。フロイト派によると、近親相姦の夢はあまりにショッキングで、夢の検閲を通過できないものとされている。しかし、アルテミドロスによると、それはいたって普通の夢であり、夢の解釈に欠かすことのできないものとされている。たとえば、母親は生まれの国の象徴で、従順な母親との性交は管理の象徴であり、為政者にとって縁起のよい夢であった。このように、近親相姦の夢は、無害な象徴的な意味を持つものであった。
アルテミドロスはさらに、夢の起源の問題について述べている。つまり、夢が神によるもの、すなわち、外的な要因のものなのか、それとも、精神によるもの、すなわち、内的な要因のものなのか、という問題である。アリストテレスが、夢が外的な要因ではないと断言しているのに対し、アルテミドロスは、一方では外的であり、一方では内的である曖昧な起源であるとして、その起源の明言を避けている。
つづく第3節では、アルテミドロスの夢解釈の科学性について検討している。旧来の評価によると、アルテミドロスの夢解釈は、錬金術や人相術と同類のまやかしだとされ、科学の歴史から排除されてきた。しかし、近年、彼の理論が古代医学の見識とのつながりを持っていたことが認識されてきている。当時の医学理論は、経験主義、合理主義、方法論主義の3つが有力であったが、アルテミドロスの理論は経験主義に則ったものであった。そこで彼は経験主義における、3つの方法論を提示している。まず1つめは、 tradition である。 tradition は、権威と経験の一般的な同意に基づく先行発見の蓄積である、と定義付けることができよう。アルテミドロスの特徴として、そのスコープの大きさが挙げられる。彼は、夢に関するすべての先行研究を調査しており、動物学にも精通していたのである。2つめは、 analogy であり、これは似たものの転移である。たとえば、下痢の治療にリンゴのかわりにセイヨウカリンを用いていたことがわかっている。3つめは、 experience である。これは、同じ様態でしばしば見られた観察であると定義付けることができる。アルテミドロスは experience を最も重要視した。そのことにより、 tradition への批判が可能になり、 analogy のスターティング・ポイントを供給することができた。また、社会的・政治的時代錯誤を起こすこともなくなった。
以上のように、アルテミドロスの理論は、客観性・論理性をもっており、科学の歴史から排除することは妥当でないだろう。では、当時の評価はどのようなものなのであったのだろうか。解答を先に述べると、アルテミドロスの夢解釈は、幅広く受けられてはいたが、地位としては決して高いものでなかった。当時はいけにえによる予言が、組織化・体系化され、公的な仕事として扱われた唯一の占いであり、夢解釈の仕事は軽蔑される傾向にあった。人々は、夢が未来を予言しうることは受け入れたが、夢の解釈は単なる偶然に過ぎなかったのである。夢の解釈が完全な科学的方法論として認知されるのにはフロイトの登場を待たなければならなかったのである。そのような状況において、アルテミドロスは夢解釈を高度な学問分野へと押し上げようとしていたのである。
最後の第4節では、アルテミドロスの後世における重要性が述べられている。アルテミドロスは、まず、予言理論の権威として、9世紀のアラブ世界でアハメットの輩出などに貢献している。印刷技術の進歩に伴い、16世紀までに、イタリア語、フランス語、ドイツ語、英語、などに翻訳され、各地に広がっていった。しかし、社会レベルで実践されることはあっても、世界について普遍的な理論として述べられたり、公的に組織化されることはなく、依然として周辺的な活動のままであった。アルテミドロスはその後、フロイトの引用により、心理学の権威として扱われるようになる。フロイトはアルテミドロスへの尊敬の念をその著作の中で明言している。フロイトは、夢解釈を symbolic なものと decoding なものに分類している。 symbolic は直観力に依存しており、それゆえ本質的に任意であるという問題点を持ち、科学性は低い。それに対して、 decoding な夢解釈は一種の暗号解読法であり、あり程度の理論性はもっている。アルテミドロスはこの単純な機械的作業に、 dreamer のさまざまな要素の配慮を付け加えたという点で、フロイトは彼を高く評価している。
アルテミドロスとフロイトの根本的な違いは、そのねらいに見出すことができよう。つまり、アルテミドロスは夢とその結果の一致を探求し、現在と未来の関係を理解しようとした。対して、フロイトは因果関係の問題を重要視した。つまり、夢とその意味を探求し、夢の中に隠された意味を理解しようとしたのである。 Price は論文の上で、その目的を明確には言及しておらず、また、それが何であるのかわかりにくい。ともすれば、アルテミドロスの賞賛のような印象も受けよう。しかし、これはアルテミドロスの理論をひとつの科学として認識する論文であり、科学史の論文であるといえよう。また、今日まで無視されてきたテクストを引用しているという点で、方法論としてはおおいに評価できるだろう。