トップページ > STAFF and STUDENT > 教員紹介 > 栗原麻子 > ゼミ紹介 > 現在のページ
スタッフ・学生紹介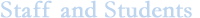
学生担当論文の紹介 11章
11. Pausanias: a Greek pilgrim in the Roman world JAS ELSNER
藤堂 かおり
筆者は、この論文でパウサニアスの『ギリシア記』を取り上げ、ローマ支配の時代に生きた彼がアイデンティティのためにどのようにギリシアの過去を扱ったのか、について見ている。そして、今までの者とは異なり、『ギリシア記』をギリシア的なものを体系化し要約したものと考え、『ギリシア記』が2世紀におけるギリシア人のアイデンティティについての何を明らかにしているのかということに焦点を置いている。
第一節 HISTORICAL AND LITERARY CONTEXT では、まずパウサニアスと単なる旅行者との違いを明らかにしている。違いとしては、パウサニアスは自国内を回りそこについて書いていること、パウサニアスの関心が宗教的場所や儀式にあったこと、が挙げられている。そして、いくつかの聖域では、彼は外部者ではなく、内部者・入信者であり、宗教目的で聖なる場所を訪れる者は巡礼者であるため、パウサニアスも巡礼者であると述べられている。また、パウサニアスの記述は単なる遺跡の列挙ではなく、我々にとってキリスト教以前の巡礼を知ることのできる直接的文学資料となるものである。『ギリシア記』で、パウサニアスは最も注目すべき名所を選び編集し、最も名高い伝説を明らかにしようとしている。その中で、パウサニアス考えるギリシアとは、過去として賞賛されるものであり、また現在においても聖なるものの中にあり続けるものであった。
第二節 STRUCTURING GREECE: PLACE AS MYTH AND AS EXPERIENCE パウサニアスは、ギリシア人読者に向けて、ギリシア世界を書いたが、その構成のしかたも独特のものであった。彼は、読者も『ギリシア記』を読みながら旅しているように書き、読者にもアイデンティティ探究の旅を経験してもらおうとしている。アイデンティティが『ギリシア記』の核としてあり、それを求める手段として、地理に重点が置かれている。そして、パウサニアスは単に地形を通った旅だけではなく、その場の価値の神話や歴史的解釈も表すなど、『ギリシア記』が呼び起こすアイデンティティは過去に由来するものとなっている。また『ギリシア記』では、そこに住んでいるからギリシア人である、というように場所が人々にアイデンティティを与えており、人と場所との初期のつながりをパウサニアスは熱心に記録した。
第三節 IDENTITY PAST, IDENTITY PRESENT: PAUSANIAS AND THE ROMANS では、過去と現在、そしてローマ人をパウサニアスがどのように扱っているかが書かれている。パウサニアスは、アイデンティティのために過去を求め、現在を避けている。その現在というのはローマ支配の時代であり、ローマ人は邪悪の典型とされている。パウサニアスの描くギリシアの神話というのは、どのようにギリシア人が独立と自由を勝ち取ったかであったため、現在の状況とは相容れないものであった。そのため、政治的な方向へとアイデンティティを求めようとすることが無理であったため、パウサニアスは宗教的方面へとアイデンティティを求めた。そして、現在によって否定されるような歴史的過去は求めずに、歴史に関わらずその神聖さが普及したものを求めた。
第四節 PAUSANIAS AS PILGRIM: IDENTITY AND THE SACRED では、パウサニアスの巡礼者としての面を述べ、『ギリシア記』を後のキリスト教徒にもつながるものだとしている。巡礼者としての性格を示すものをいくつか挙げている。『ギリシア記』はパウサニアスや読者がギリシアの聖なるアイデンティティに直面することで変化するという点で通過儀礼の要素をもっている。また、彼は読者にも旅の経験を提供するような構成をとっているのに、宗教儀式を書くときになるとその中身を語らないなど沈黙の姿勢をとる。この沈黙は、それ自体儀式的な行動であり、タブーや報いの宗教的心性の結果であることもある。また、秘密であることは他にはないことを示し、他にはないことは聖なるものであることを支え、聖なるものであることはアイデンティティを保証するものであるため、この沈黙もアイデンティティのためである。
第五節VIEWING AND IDENTITY パウサニアスは、ギリシア的なものを列挙しているが、その中身を詳しく見ていくと複雑なものとなっている。現在と過去はからみ合い、社会歴史的アイデンティティを成すが、『ギリシア記』ではそうなっていないため、ここでのアイデンティティは矛盾を含み、筋の通ったものではない。実際、パウサニアスは、物事を見る際に、訪れた場所によって2つの異なる見方をとっている。同じ人間のアイデンティティでも状況が異なれば異なるものとなっている。
第六節CONCLUSION では、結論と、パウサニアスとキリスト教徒との違いが述べられている。『ギリシア記』には、一般的で世俗的であり、誰でも得ることが可能なアイデンティティと、ある儀式や信仰の内部者にしか共有されないアイデンティティの2つのアイデンティティが存在している。そして、キリスト教徒たちも自文化の中で場所に意味を与えるような場所や神話を通してアイデンティティを思い出させるために聖地へと旅したことや、儀式に対して関心をもったことなど、多くの点でパウサニアスのアプローチは、後のキリスト教徒たちのさきがけとなるものであった。しかし、パウサニアスとキリスト教徒との違いも明らかである。パウサニアスが自国内を回り、矛盾するような数々の伝承を呼び起こし、儀式について沈黙した一方で、キリスト教徒たちは自分の国ではないところへと旅し、聖書と場所を結びつけ、儀式について沈黙する必要がなかった。キリスト教徒と違い、パウサニアスにとっては、社会・政治的アイデンティティの世俗世界と聖なる世界との間には大きな差異があった。
POSTSCRIPT 2003 では、筆者自身が3つの問題点を挙げている。パウサニアスをギリシア文化の内部者をとしたこと・パウサニアスをsecond sophisticの中で見る見方・巡礼者としてのパウサニアスの問題である。最後の問題が一番大きいが、筆者自身はパウサニアスを巡礼者とすることは有効であるとして締めくくっている。
パウサニアスを巡礼者とする考えに異議を唱える者もいるようだが、私はこの考えは評価できるものだと思う。確かに、パウサニアスとキリスト教徒との違いは明白であり、共通点よりも相違点の方が大きいかもしれない。しかし、パウサニアスを巡礼者と一言で表現することによって、彼の業績のイメージをよりはっきりと思い浮かべることが可能になる。アイデンティティを求めてギリシア各地を回った、という表現では得られない印象を得ることができる。宗教的なイメージはもちろん、使命感や願い、尊敬の心といったイメージも付随的ではあっても浮かんでくる。パウサニアスはなんらかの強い使命感を持って各地を回ったのではないだろうか、彼には何か叶えたい願いがあったのではないか、彼は遺跡などを敬ったはずだ、巡礼という一語でこのようにイメージを膨らませることができる。そして、そのようにして思い浮かべたイメージはパウサニアスや『ギリシア記』の役割と大きく異なることはなく、巡礼者という語は彼やその作品をうまく表したものだと思う。
私の筆者に対する希望としては、もう少し読者の問題を扱ってほしかった。筆者は、ただギリシア人向けに書かれたものだという。しかし、それはギリシア人全般を指しているのか。それとも、ギリシアに住んでいるギリシア人/ローマに住んでいるギリシア人など対象とする地域や、農民/富裕者層など対象とする階層があったのだろうか。立場が異なれば、求めるアイデンティティの質や量も同じではないはずだ。また、パウサニアスの『ギリシア記』を読んでも、得られるアイデンティティも異なるように思う。すると、全員がパウサニアスとともにアイデンティティ探究の旅ができたとは限らないのではないだろうか。
また、筆者はギリシア人のアイデンティティのためにパウサニアスが現在を避けている、と述べている。確かに、パウサニアスはローマをよくは思っていないし、筆者の言うように見ているはずの建造物を描写していないかもしれない。しかし、過去と現在というのは、はっきりとは切り離せないものであるし、パウサニアスはローマ支配の状況だからこそ『ギリシア記』を書こうと思った。その点で、パウサニアス自身から現在を完全に取り去ることはできず、現在は『ギリシア記』の中に含まれているように感じる。また、『ギリシア記』を読む人の中にも現在は必ず存在し、『ギリシア記』を読むことによっても過去のみならず現在についても考える。現在のギリシア人が置かれている境遇があるからこそ、過去のギリシアの輝きが増す。パウサニアスは過去を振り返ることで現在の環境について考え直し再び過去のすばらしさを認識している。パウサニアスは現在を避けてはおらず、また現在は避けることのできないものであるように感じた。
<参考文献>
・パウサニアス(馬場恵二訳)『ギリシア案内記』(上)(下)、岩波書店、1999年。