スタッフ・学生紹介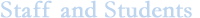
学生担当論文の紹介 3章
3. Law, society, and homosexuality in classical Athens DAVID COHEN
余田 温子
本論文の著者である David Cohen は、カリフォルニア大学ロサンジェルス校で法学の博士号を、ケンブリッジ大学で古典文学と古代史の博士号を取得した。現在はカリフォルニア大学バークレー校で修辞学・古典文学の教授と戦争犯罪研究所の所長を務めている。 Law, Violence, and Community in Classical Athens (Cambridge University Press, 1995) や Law, Society, and Sexuality: The Enforcement of Morals at Classical Athens (Cambridge University Press, 1991). が代表的な著作である。法律や社会史、修辞法や人権と、関心の幅は多岐に渡っている。本論文では古代アテネにおける同性愛のあり方を、法律と社会という面から明らかにしようと試みられている。
P.61 から P.63 では、古代ギリシャの同性愛に関する先行研究として、 Kenneth Dover と Michel Foucault の見解が紹介される。彼らは異性愛 / 同性愛という現代的な二分は古代世界には適応できないと述べている。さらに彼らは、古代ギリシャにおいて同性愛行為における能動的役割と受動的役割は区別され、能動的役割については自然なものとされるが、受動的役割については自由市民にふさわしくないとして非難の対象となったとしている。著者は、このような解釈はアテネの社会と文化が抱える矛盾や複雑さを反映していないと批判している。アメリカの社会人類学者である B.Malinowski は、トロブリアント諸島において近親相姦は最大の禁忌とされるが、実際は近親相姦をめぐるスキャンダルがあったという例から、規範と社会的現実はしばしば矛盾するが、対立や矛盾の重要性を認めることが文化の複雑さの理解につながると結論した。著者は矛盾を文化体系の中心としてとらえる人類学的な論理が歴史学にもあてはまるとし、矛盾をアテネの同性愛研究の出発点としている。
P.63 から P.67 では、同性愛を規制する法律について、売春に関する法律・交際に関する法律・ヒュブリス (hubris) 法という 3 つのカテゴリーにわけて述べられている。売春に関する法律は、売春を行った市民から市民権の一部を剥奪すると定め、また自由身分の少年や女性対する売春行為の斡旋も禁止している。交際に関する法律は、就学年齢にある少年と年上の男性との接触を規制し、学校がしばしば成人男性が少年を誘惑する場となったことから、学校の環境にも規定を設ける。さらに、奴隷が自由民の少年と交際することも禁じている。
従来の研究ではヒュブリス法が同性愛を規制する法であると考えられることはあまりなく、またアテナイ人男性と自由身分の少年との金銭を伴わない同性愛を禁じる法律はないと考えられてきた。この考え方の裏には、同性愛における能動的役割は非難の対象ではなかったという標準的見解がある。しかしアリストテレスは、加害者を喜ばせることによって被害者の名誉が損なわれる行為のすべてがヒュブリスに相当するとした。これを受けて雄弁家アエスキネスは、ヒュブリス法は同性愛を規制するものであると主張する。彼らは能動的役割をも非難し、金銭の有無は問題にしていないといえる。さらに従来の説は同意の有無は問題となったか、また子供の同意は有効であったか否かという視点に欠けると著者は批判し、雄弁家の発言から次のように述べる。被害者が大人の場合、同意があれば加害者への咎めは軽減されたが、被害者は服従することで自らに対するヒュブリスを犯したと非難された。対して子供の場合は同意の有無にかかわらず、少年を侮辱したものはヒュブリス法によって罰せられた。
以上、3つのカテゴリーの法から、同性愛に関する法律が多岐にわたることが示された。著者によると、これらの法律の背景には同性愛のはらむ危険性に対するアテネの人々の懸念がある。上述のように、受動的役割を受け入れた少年は将来の市民にはふさわしくないと非難され、また売春を行った男性は市民権を制限されたということは、同性愛はポリスの基盤である市民集団を揺るがす危険性をはらんでいたということになる。アテネの同性愛関連の諸法はポリスの将来の担い手を同性愛から守るために制定されたといえる。
しかし、このような法律が実際にはほとんど適用されなくとも不思議ではないと著者は述べている。 Malinowski が述べたように法的規範と社会的秩序や社会的現実の間には格差があるからである。 P.67 から P.75 では、同性愛に関するアテネの社会的規範について、「 zero-sum game 」をキーワードに述べられる。
名誉とセクシュアリティーには密接な関係があり、男性にとっての名誉は、しばしば妻や母、娘の貞潔と自分の男らしさによって得られた。競争社会では男らしさ、つまり名誉は女性の奪い合いの中で示される。争奪戦に勝った男性は男らしさを示すことで名誉を得るが、対象となった女性の夫の名誉は傷つけられる。このように、一方が名誉を得ると他方の名誉が損なわれる状態を、著者は「 zero-sum game 」とする。しかし、古代アテネでは女性の結婚年齢が低く、また不倫は厳しく罰せられたことなどから、競争的なセクシュアリティーが女性の奪い合いという形で現われることはほとんどなかった。そこで、名誉をかけた性的な競争の対象は少年へとずれることになったのだ。
少年は肉体的側面と文化的・社会的側面という二方向から女性と同一視された。アリストテレスは生殖能力という点で人間と動物との間に差はなく、男性は女性と性行為をもつべきであり、その際、男性は能動的、女性は受動的役割を果たすことが自然であると述べる。よって、男性は女性と性行為を行うべきという考え方が性行為に関する社会的規範の根底にあったと考えられ、同性愛 / 異性愛の区別はなかったという Dover らの意見を鵜呑みにすべきではない。プラトンが同性愛を賞賛し、理想化しようとしたことの背景には、異性愛を自然とする規範があったといえる。にもかかわらず同性愛を許容する傾向が確かに存在したのは、ギリシャでは生殖能力がなく能動的役割を果たせない少年は、女性的であると考えられたからである。肉体的同一視は文化的・社会的な面の同一視へとつながる。女性に課される貞潔で慎み深くあれという社会的規範が少年にも適応されたのである。
P.75 から P.77 では、まずアテネの人々の同性愛についての考え方が多様であったことを示した後、著者の結論が述べられている。たとえばプラトンは『饗宴』の中で同性愛を極めて精神的なものとして理想化している。対してアリストファネスは喜劇の中で同性愛の現実をあからさまに描くことで、プラトンが唱えたような同性愛の理想の偽善を明らかにしている。また、アリストテレスは同性愛を病的な状態であると考えた。このように、同性愛に対して様々な価値観を抱え、また同性愛に対して根深い不安をもちつつもこれを禁じない文化をどのように評価すべきだろうか。 Cohen は以下のように結論付けている。文化というものは均質な統一体ではない。よって同性愛に関する一定の考え方というものをアテネ人の中に見出すことはできない。多様な考え方や規範と現実のギャップは、アテネ社会の不安や矛盾、不一致を反映している。そして、このような不安や矛盾こそが複雑で混沌とした文化を形成しており、多様性を合理化するべきでない。多様性をひとつの枠に当てはめてしまうことは、アテネにおける同性愛の、『多色』という本質を理解する上で妨げとなるのだ。
最後に、本論文に評価を加えたい。まず本論文に欠けている点を検討する。アテネの同性愛を語る上で、身分とのかかわりは大変重要であるが、著者は身分について多くを述べていない。また、本論文は少年愛に特化しているが、実際は成年男性同士の同性愛もアテナイ社会では多かったとされている。成年男性同士の同性愛について語ることなしに、アテネの同性愛の全体像を描くことはできないだろう。また、ヒュブリス法は金銭を伴わない同性愛をも禁じていると述べられているが、このような解釈は一般的ではない。たとえば、 James Davidson の Dover,Foucault and Greek homosexuality: penetration and the truth of sex では、アテネの法律は同性愛行為ではなく、報酬を受け取ることや貪欲を防ぐために売春を禁じたと述べられている。また、論文集の編者である Robin Osborne は Introduction の中で、 Cohen は M. Foucaut を批判するが、 Foucaut 以来の社会的関係と権力関係とを結びつける傾向が彼にも見られるとしている。
次に評価すべき点を挙げていきたい。成人男性対少年の関係と男性対女性の関係の両方を扱い、比較したことは従来の研究には見られない点であり、評価に値する。また、 Dover や Foucault が許される同性愛と許されない同性愛を明確に区別したのに対して、 Cohen はこの区別は不明確であったとしている。 Cohen の考え方はアテナイ人の様々な態度や法的規範と社会的規範の矛盾をより反映しているといえるだろう。さらに、人類学の理論の歴史学への応用についても注目すべきである。人類学の研究で見出された普遍的な枠組みの中に、過去のある時代、ある場所の文化を当てはめて歴史学の研究とすることは行きすぎであるといえる。しかし Cohen は Malinowski などの人類学者の研究を紹介するが、あくまでアテネの文化と比較するにとどめている。このような態度も評価すべきである。