スタッフ・学生紹介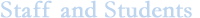
学生担当論文の紹介 5章
5. The Mediterranean and the Roman revolution: politics, war and the economy FERGUS MILLAR
藤 朝子
著者の Fergus Millar はオクスフォード大学のトリニティカレッジとオールソウルズカレッジで教育を受け、1962年にはオクスフォード大学にて哲学と古代史の勉強ののち、哲学の博士号をとる。1984年から2002年までオクスフォード大学とロンドン大学にて教鞭をとり、引退後は古代史学の名誉教授として教壇にたつ。 Millar は専門分野において多大な活躍を成し、名誉ある Journal of Roman Studies の編集(1975−1979)に携わり、 British Classical Association の会長もつとめ、 Millar 自身もメンバーである、英国学士院においてさまざまな学術団体を支えてきた。古代ギリシャ史・ローマ史研究の権威としてオクスフォードやヘルシンキだけでなく海外の学会でも高く評価される Millar の最初の出版物は1964年の A Study of Cassius Dio は、40年以上経つ現在においてもローマ史を研究する上で重要な歴史家ディオ・カッシウス研究においてもっとも優れたものとして評価されている。第二の著書は1977年の The Emperor in the Roman World(31BC-AD337) であるが、 Millar はこの著書においてはじめてローマ皇帝のさまざまな所業を文化的・社会的枠組みでとらえなおし、政治活動や社会的・文化的な善悪のカリカチュアとしてではなくローマ帝国の一構成員として見直す試みをなした。これに次ぐ重要な研究として1993年には The Roman New East(31BC-AD337) というこの時代区分においてローマを中心的に扱わない著書をあらわした。 Millar の重要な研究著書にはこれ以後も1998年の The Crowd in the Late Republic や2002年の The Roman Republic in Political Thought などをあらわしており、ローマ史のあらゆる側面を広く扱って論文を出版し講義を行っている。
本論は Studies in Ancient Greek and Roman Society (ケンブリッジ大学出版)の論文集の第5章を構成するものである。この論文集は Past and Present の中で発表された論文を集めた構成になっており、本論が掲載されたのは1984年である。
本論の論旨は内乱期ローマの地中海地域における社会的・経済的影響をまとめたもので、政治的・経済的に統合されたとされるローマ帝国が元首政を背景にした国家であることを再考した上で、共和政の終わりにかけて、どのように状況に応じて変化し、それが帝政に移行したかを詳細な史実から見出せる具体的な事例を挙げながら述べている。本論文集の編集者である Robin Osborne はこの論文の政治経済的な視点をローマ研究史における新しい視点として高く評価している。また共和制ローマの構造をどのように定義づけられるかという議論を再度持ち上げる話題性を持つと評している。特にローマ帝国の覇権の寄せ集め的性格や帝国の多地域にわたって確認できる多様な政治的・経済的な事情を追っていく論文としては興味深い指摘をいくつも与えてくれる論文なのではないだろうか。
本論の最初の部分、論文集のp119からp120にかけてアルプス地方を例にとり、ローマの拡張・内乱期の活動と地方社会の政治経済との間にある程度の関連性があることを述べている。カエサルの西アルプス侵攻において包囲を耐え抜いたことから名付けられた町の存在やアオスタの植民市建設において徹底的に統合された地域社会などを挙げて説明されている。また長距離貿易の存在を指摘し、多地域間の商業が社会的・経済的枠組みとなった上で軍事・政治的闘争が行われていたのではないかという推定する。スラのよって滅ぼされたはずの町ハラエで漁業が続いていたことを例に挙げて内乱期の混乱の中でも商業は途絶えることがなかったとしている。
p121からp126にかけてはローマの支配が一般市民の社会や経済にどのような影響を与えたかが述べられている。ここでは文字資料が比較的多く現存するためローマの影響を考える上で重要な意義を持っているとされるエジプトでのローマ人の扱いや記念石柱の文化などが挙げられている。紀元前1世紀にギリシャ・ローマの住民は異なる慣習を持つ人々、または野蛮人に囲まれて生活していることを自覚していたという指摘から、外部からの影響による相互の文化・慣習の浸透の可能性へと展開される。しかし、具体的、詳細な記述のある史料ほど大きな流れで長期的に見た場合に変化を確認しにくいという指摘をつけ加えられている。次にガリア地方を取り上げて高価な材料を用いた貨幣が減少傾向にあった例を用いて、影響がなくなったという観点から論を進めている。この理由としてはカエサルの占領後の賠償金支払いのため、もしくは貨幣で支払っていた軍隊が不必要になったからではないかとした。当時騎兵は軍事的有効手段であり、地中海全域で活躍していたことを考えるとガリア兵はローマ支配の特徴や地域社会構造を知る手がかりになることも指摘している。しかしこれらの例を見出した記録は断片的に残っているだけでは財産関係や社会構造においてどれほど影響が及んだのかは不明であるとし、土地や社会的階級によって習慣や文化が違うことから断定的な見解を述べるに足る史料とは言えないとした。
p126では奴隷売買は戦争が経済に与えた影響となり得るかを考察している。戦争での捕虜はたいてい奴隷となったがこれらについては将校や仲介商人の利益となるため直接国家の利益には結びつかないとして否定している。次にp129にかけて、非従属地域の意義の説明にうつる。ローマにいつでも占領される立場にありながらもそれら諸地域を制圧することは大きな影響があったとする。ギリシャの諸都市には包囲に耐えうる政治経済的強さを持った共同体が多く存在し、また、著者が指摘したいのはヘレニズム時代の軍事勢力が弱いことからローマの優越性による経済・社会への影響は否定できるという点である。これは地方社会が選択的な意志を持ち、ローマ支配自体は変動的で不完全なものであるとした意表のつく可能性を示唆したものである。
p130にかけては先ほど述べた地中海諸地域の選択的側面を具体的に4点あげて説明している。ひとつにはさまざまな方向から起こりえた暴力的支配と貢納の要求、二つ目に自由で孤立した状態でいることのリスクの高さ、三つ目に地理的な距離が原因と考えられるローマの緩慢な搾取と要求、そして最後に属州に要求される政治的賛同と経済的援助である。
p131からp133にかけて長距離海上貿易の影響は有用であるか議論される。しかしここでも著者は、単なる事例の列挙は海路貿易の規模や経済全体への意義を示すものではないとしてあらかじめ忠告している。貿易に関する見解は古くから多く述べられてきたが、著者はまずプリニウスが提案した貿易における輸出輸入量の研究は否定的にとらえている。貴重品・ワイン・奴隷などの流通は政治的統制や当時の陸海軍戦術の影響を受けなかったとし、またローマの属州は系統的に海路貿易に介在していなかったことから貿易構造や貿易先での活動が及ぼした影響というのは少なく、また不確かであると主張している。自国の産品の輸出による利益の獲得には消極的であったのではないかという指摘もある。以上の点から経済への影響は少なかったのではないかという点を導き出している。
p133から最後にかけてローマの社会的・経済的生活への影響はもっと広い視点に見ることによって確認できると述べている。それは王国や帝国の興亡はつぎはぎだらけの統率力の変容であるとし、またローマに限っては直属の州とローマ支配圏外との区別のあいまいさを指摘した上で細かい単位で影響を考察することの難しさを強調している。共和制ローマにおける経済効果を分析しつくすことができるのならば、貨幣・穀物・奴隷・貴重品の流動は複雑なパターンのひとつでしかないという指摘はもっともであると考えられる。Osborne もこの指摘は高く評価しているが、疑問に思えるのは先に述べられたように史料の限界を考えるならば、分析の完成度にも限界があり、パターンのひとつでしかなくとも、その研究を深めていくことの意義が大切なのではないかという点である。やや裏返した主張になっているとも思われる。
最後に現段階では社会・経済モデルを経験的なデータで構築できない中、将来性のある方向は実際の生産性であり、流通機構であるとしているが、個人レベルの生活の中でも革命のような大きな変化が与える影響として見出すことのできる特徴とまたその限界が示す意味を Philotas of Amphissa の例を挙げて説明して論を終えている。社会経済史を深く研究するにあたって必要なものはさらなるモデルであり、それが対立する国家や派閥の要求するものから得られるか、戦争における必要性とその効果から得られるものであるのかは疑問視したままである。
感想として、この論文は全体を通してその論旨は明確であるが、ローマを社会的・経済的にとらえた場合に新しい視点を見出すという方向からみるとやや積極性に欠けたものであったのではないかと考えられる。ひとつの史実から、また一片の史料から展開できる論の可能性・多様性を広げたという点では非常に斬新で将来性を見出せるものであるように思えるが、逆に、そのもととなる資料が限られており、その限界がある程度現段階ですでに見えてしまっていることを暗に主張してしまっているのではないかとも受け取れる。しかし、その過程において、ひとつの方法論の限界や資料から導き出せないものがどのような意味を持っているかについて指摘されている点は今後古代史に限らず歴史学を研究することに対して有用な指摘であったのではないだろうか。特に、最後の Philotas of Amphissa の生涯を通して、戦乱のさなかにおいても根本的なギリシャ性を失わない住民の生活が読み取ることができるという事例は大変興味深く読むことができた。また、 Millar が挑戦している文化的・社会的枠組みからとらえなおすという観点では古代ローマにおける新しい社会的側面をいくつも抽出することには成功しているのではないだろうか。