スタッフ・学生紹介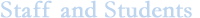
学生担当論文の紹介 6章
6.Democratic politics in Republican Rome JOHN NORTH
土井 啓瑛
民主政といえば我々にとってなじみのある言葉だが、ローマにおいて、民主政的な要素は全くなかったのだろうか。共和政末期の民会のシステムに民主政の効果的な要素があったか、というのが本論文の議論の主題である。
本論文は章ごとに分けられていないが、内容は通説とその反論の紹介、その中で注目に値する二つの議論の紹介、そして著者自身の見解という流れになっている。問題の鍵となるのは、民会とそれらの組織上の力の行使が重要か否かであると著者 North は述べている。
まず、一時的に古代史家に受け入れられた通説が紹介されている。ここでは“ frozen waste ”と呼ばれており、以下の四点が挙げられている。第一に、ローマは狭い世襲の寡頭政治によって支配されていたこと。第二に、民会での集団投票システムにおいて、裕福な投票者が進行をコントロールしていたこと。この通説によると、クリエンテーラ関係で投票者の態度が決まり、この個人と家系のネットワークに構造全体が依存していた。第三に、これらの支配的な家系は、安定した長期的な同盟に自らを関係させていたこと。第四に、立法行為や政務官の選挙はライバルグループによる競争的な操作で決められていたこと。
これらの“ frozen waste ”は投票者自身の意見、関心から切り離されているし、ポリュビオスがローマの民会に民主制的要素を見出したことはある程度現実味があったからではないかと著者は考えている。そして、どれほど新しい解釈が出てきたのか、どのような進歩がなされ得るかを調査することを本論文の目的としている。
では、一連の“ frozen waste ”理論に対してどのような反応があったのだろうか。次の四点が挙げられている。第一に、政治のトップエリートを規定するのに‘ nobles 'という言葉を使うのは間違いであり、寡頭政治は従来考えられていたよりも新たな家系の加入にオープンであったこと。第二に、義務のネットワーク(クリエンテーラ関係)の再検討によって、それらのつながりが従来の考えよりも縛れていない、予測できない、交渉できるようなものだったこと。第三に、エリートメンバーの動機を我々が集中してみることで選挙の勝者としての問題の重要性が隠されてきたこと。すなわち、なぜ投票者が支持したのかを考えねばならないということ。第四に、ポリュビオスの考えが地位を回復してきていること、である。
これらは‘ frozen waste 'にとって致命的であると North は考えている。さらに、これらの反論の中でも特に二つの議論を取り上げている。その二つの議論というのは Hopkins と Burton が Death and Renewal で論じている議論と、 Fergus Millar の議論である。これら二つの議論の結論は全く逆なのだが、それは‘ democracy 'という言葉の定義が厳密になされていないからだと指摘されている。
まず、一つ目の議論である Hopkins と Burton の議論は、エリートの加入と主要なローマ家系の生存戦略の結果を統計上分析したものである。彼らは、ローマは民主的ではないという結論を出しているが、これに対して著者は、この分析から普遍的な内部エリートと一、二世代の間だけエリートに加入する外部エリート存在したという解釈している。そして、新しい家系がエリートへ参入するのを民衆の投票が決めていたのではないかという民主制的要素を見出す立場をとっている。
二つ目の議論の Millar は、ポリュビオスの主張する‘民主制的要素'を擁護し、ローマを民主政的であったと主張している。 Millar の論では民主制や民主正論を喚起することに正当性を与えていないが、寡頭制ローマの中に‘民主制的要素'という問題を喚起した点で、著者は Millar を評価している。
以上の議論をふまえて、 North は三つの仮説を打ち出している。第一に、共和制ローマの国政上の配置は、ローマの政治生活を十分に伝え得ないのではないかということ。第二に、ローマの寡頭制は確立した権威の地位を持つということ。民会はエリートよって招集、演説、解散され、大衆に特有の領域ではなかった。この権威に相当するものはアテナイにはない。これらはローマの確立された寡頭制の力を再び強調するものである。第三に、ローマ人の大衆の意思は寡頭政内の分派というコンテクストの中で説明されること。したがって、ローマの民主的な政治とは階級の機能や寡頭政の家々、グループ、個人の進歩の競合であったと著者は主張している。とても重要な状況において、支配階級が民衆の投票の仲裁を受け入れたというのが、単純な事実なのだと。
そして、この論文で著者が最も主張したいことは、競争的な寡頭政治と投票民会の関係を分析のツールとして捕らえることが可能ならば、それはローマの政治的発達に対する我々の考えに衝撃を与えるものになるだろう、ということである。民主政か寡頭政かという問題ではなく、寡頭政の中に民主制的要素を見出すことが重要なのである。
この論文の議論は、ローマの民主政はとても特有の形態として見られるべきであること、類似のシステムとの比較、分類を必要とすることであった。ただし、 5 世紀のアテナイとの比較は役に立たないと著者は述べている。なぜなら、ローマの支配的エリートの力のほうがずっと強かったためである。そして、内乱が終結すると投票者の意見は皇帝への重要性を失ったのである。
2003 年に書かれた Post Script によると、著者が基本的に考えを変えた点はほぼない。アテナイの民主政との比較はいまだに有効ではなく、ローマの状況を最もよく特徴付けるのは、エリートとの競争と関係する、時々の民衆の投票の役割だと改めて述べている。
さて、以上が論文の内容であるが、いくつか問題点を挙げておこう。まず、この論文で扱われているのは共和制末期であるが、史料的問題については詳しく述べられていない。帝政に移行しローマが安定すると、アウグストゥスの時代に共和制の再興が歌われ、ウェルギリウスらは帝政を賛美した。それゆえ、その前の時代である共和制末期が暗く描かれている場合があり、この点は再考が必要であろう。また、共和制末期の史料といえば Cicero によるものが多いが、 Cicero の史料は現実というよりも理想論を述べているような、フィクション的な性格がある。他に史料がないので Cicero による史料を使わなければならないのだが、 Cicero 自身が混乱の時代より以前を理想的ととらえているのか否か、またどの時代の民会システムが史料に反映されているのか、といった問題が残り、この点についても検討が必要であろう。
そして、 North は支配的エリートが分かれたのは投票者の見解が決定的になった場合であるとしている。すなわち、平時はそのような競合はなかったという立場をとっている。しかし一方で、 A.Yakobson などは普段から競争はあったのだとする立場をとっており、著者の解釈が必ずしも受け入れられているわけではないことを忘れてはならないだろう。また、を著者は共和制末期危機の時代と捕らえているようだが、違った見解も考慮するべきと思われる。
授業中の議論で上がった話題に、ローマの民会の中身についての問題がある。前 139 年から選挙民会で秘密投票制が導入され、前 109 年にはすべての投票に秘密投票制が取り入れられた。一般的な見方では、それによって一人の人間が負っている複数の義務の対立が表立って出てこなくなったためクリエンテーラ関係は安定したと考えられている。一般的な見解に対して、義務が表立たなくなったのだからクリエンテーラ関係が弱くなったのではないかという見解があることも挙げられた。
また、民主政を語るのならば元老院との関係も論文中で十分に議論する必要があったのではないかという意見もでたが、これについてはおそらく元老院との関係は前提としてあるものとされているため詳しく述べられていないのであろう。