スタッフ・学生紹介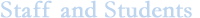
学生担当論文の紹介 7章
7.The Golden Age and sin in Augustan ideology ANDREW WALLACE-HADRILL
高辻 真由子
この論文は、アウグストゥス時代の文学における「黄金時代」や「罪」の概念を検証し、その概念が当時のイデオロギーに対してどのような役割を果たしたのかを探ることを趣旨とする。アウグストゥスの解釈にあたって、長年続いた彼の帝政についての議論から離れ、当時の政治的な力を持つ詩を通じて、彼の体制が促したイデオロギーを考察し、更にそこで、ローマ外の東方から入った思想に注目している点が新しい、と編集者 Osborne は評価する。しかしこの分野に続いたのは、歴史家よりも文学者の分析であった。
宗教者たちは堕落の神話を用いて人々を導いてきた。アウグストゥス時代の詩人たち、特にウェルギリウス、ホラティウスなどの宮廷詩人は、こうした宗教家たちと同じように、人々の考えを体制支持に導く働きをしたと考えられる。
第一節「黄金時代の再来」では、ウェルギリウスの作品をたどり、その作品によってアウグストゥスが救世主として位置づけられる過程を追う。ウェルギリウスの『牧歌集』第4歌では、黄金時代の再来が予言されているが、その黄金時代はヘシオドスの黄金・銀・銅・鉄の時代の神話や、クロノス ( ローマではサトゥルヌス ) の治世という二つのギリシアの伝統に基づく。しかしまた、ギリシア神話が遠い過去を振り返って人間社会の現状を説明するものであるのに対して、循環して再来するという概念を採用していたり、東方ユダヤの救世主思想などのギリシア文学以外から引用するなど、相違点も見られる。黄金時代の再来の背景には、三頭政治下の不安定な情勢があった。立て続く戦争に人々は不安を抱き、予言や神託に救いを求めていた。時折りしもオクタウィアヌスとアントニウスの休戦が結ばれた頃で、作品自体は救世主の出現を予言する明るい文章だが、戦争再開が懸念されていた。しかし、アクティウムの海戦でオクタウィアヌスが勝利すると、『農耕詩』ではまだ不安を残しつつもオクタウィアヌスを救世主とし、更に、彼がアウグストゥスと改名して支配を確立すると、『アエネーイス』ではアウグストゥスをサトゥルヌスの治世 ( 黄金時代 ) を復興するであろう救世主として評価した。これがローマ人に影響し、皇帝と黄金時代の再来を結びつけることが多くなったが、常に戦争が無いことが楽園の特徴であった。
第二節「罪と堕落」では、内戦が終わった後も、「罪」の概念を利用して、その罪から人々を救い出すアウグストゥスの救世主性が強調され続けたことが述べられる。当時の概念では、楽園には法律も私有財産もなかった。サトゥルヌスの治世には、何事も彼の手本に従うので法律は不要であった。法律はその後の道徳の低下の産物であって、貪欲になったために人間は幸せを失った。金、財産に対する欲望が罪の根源として、この時代の文章に現れはじめる。しかし、財産の安全、階級の不平等、厳しい法制度というものは、アウグストゥスの体制がむしろ守ったものなので、ここで矛盾が発生した。ウェルギリウスはサトゥルヌスを立法者としたり、労働を讃えるなど修正を試みるが、結局この矛盾も大きな問題とはならなかった。罪によって堕落する人々は神の怒りを防ぐため、本来儀式に則った償いをしなくてはならないが、『農耕詩』ではもはや伝統的儀式では不十分になり、 scelus( 罪 ) から国家を守るためには若きアウグストゥスが必要であるとされた。 scelus はもともと内戦を意味していたが、アウグストゥスの道徳関連の法律を浸透させるため、次第に姦通などの道徳的な罪を指すようになった。楽園はまだ予言的口調で述べられていることから、戦争が終結した今も到来したとは言えず、アウグストゥスに委ねられている。堕落の神話はギリシア人にとっては現状の説明であるが、アウグストゥス時代には体制の中央に皇帝として彼を据えるためのイデオロギー的機能を果たした。
第3節「罪と寛容」では、 scelus が武装反乱であれ、性的不品行であれ、対立を形成するものであることから、結果として発展した clementia( 寛容 ) に注目する。カエサルが示す clementia は、破れた敵が罪を後悔してカエサルに全てを委ね、家来になるという、政治上の対立を和らげるための効果的な技術であった。ところがその後、 clementia は政治の枠を出る。もはや政治的罪も性的な罪もアウグストゥスのイデオロギーからすれば違いはなかった。セネカは clementia を4段階に分析する。①人間は非本的に罪深く、②皇帝が現状からの脱出の希望である。③救済者である皇帝は clementia を示さなくてはならないし、④ clementia を示す者が黄金時代を呼び戻す、と clementia の非政治的罪を終わらせる力を強調して、ローマ人に皇帝の支配を納得させる。ここでは、皇帝が自身の倫理観に基づいて有罪の判断、罪の判定を行い、もはや政敵を赦すこととは関係しない。
第4節「地上の王国と天上の王国」では、救世主に関する東西の関連を検証する。厳しい現実に対して、詩人たちはローマ人を罪から守り、楽園に連れもどす救世主を描き出すが、そこにはキリスト教思想との類似がある。パウロの説教を分析 ( ①アダムの堕落以来人間は罪深く、②神が人々を罪から救うために、キリストを遣わした。③キリストは悔い改めるもの全てを許す。④救世主とは、アダムの原罪をなくし、楽園への道を開く ) するとセネカの clementia 分析と似ており、キリストと皇帝の大まかな役割は同じである。古典学者はローマの思想とユダヤ・キリスト教徒の隔たりを大きいとする傾向があるが、ウェルギリウスがシビラの予言を通じて東方の救世主思想を紹介しているし、セネカはギリシアの博愛者としての王 (Basileus) のような皇帝像を形成している。他方、ローマの政治的革命によって、ローマのイデオロギーが領内の国民に広まりもしているし、パウロとセネカの言葉や思想のつながりはなんら不思議ではない。
第5節「形成過程のイデオロギー」では、アウグストゥスがイデオロギーに対してどこまで意図的であったのかということが考察される。当時のイデオロギーは、アウグストゥスが作り、命令によって影響力のある公的経路で広まったのだろうか。ヴェルギリウスやホラティウスは報酬について率直に述べ、読者はそれにためらいを見せているので、全てのローマ人が同意していた考えとは言えないのではないか。当時、王政を嫌悪し自由を愛する旧来の共和制イデオロギーが根強く残っていた。しかし三頭政治時代に、政治紛争はローマ人自身の罪であると認識され、自身の罪から守るために君主の必要性が認められ始めた。そこで東方から救世主という概念が引用された。だが、アウグストゥスが事実上の皇帝となったのは、ローマ人を守るためなのか、それとも自分の利益のためであろうか?アウグストゥス自身は、権力への関心を否定し、元老院へ返還したが、彼の支配は依然続く。戦争が終結することで、罪の意識が重要性を失ったが、アウグストゥスは性に関する罪を繰り返し批判することで新たな罪の意識を引き起こし、自己の地位の安定を図ったが、彼はイデオロギーを創ったというより利用したというのがふさわしい。マエケナスを通じて詩人たちの忠誠を形成することで、強制する必要なく、のぞむイデオロギーを作品に反映させる事が出来た。表現については詩人たちが独自のものを見つけるに任せられていたが、そのうちのひとつが、黄金時代の再来であったという結論に至り、本論文は締めくくられる。
前半2節では、アウグストゥスが、戦乱の世にギリシアや東方のユダヤの思想を取り込んで、黄金時代を呼び戻す救世主と位置づけられ、内乱の終結後も新たな危機である堕落という罪の意識を生み出して、救世主性を維持し続けたと、一見すっきりとした論理で説明されるが、最後の第5節によると、アウグストゥスはイデオロギーを創ったのではないし、それぞれの詩人たちが独自の表現を見つけるに任せたとあるから、このようにあたかも一人の人間が計画して一貫した理念に基づいて形成したかのようなイデオロギーはかえって不自然に感じる。そもそも構成において、アウグストゥス時代のイデオロギーの内容や、形成・変化する過程、それが政治的に利用されたことを一通り論じた後で、そのイデオロギーを考案したのは誰か、どういった経路で広まったのかということが問われることに違和感を感じる。まずこれらの基本的な問題をはっきりさせずして、イデオロギーの内容やそれが意図するもの、社会に果たした役割というものは見えてこないのではないか。
本論文では、アウグストゥスはマエケナスを通じて詩人の忠誠を形成することで、強制することなく、都合の良いイデオロギーを作品に反映させたとしているが、当時の詩人たちは政治と関わることを嫌い、独立不羈の傾向が強く、援助を受けていたとはいえ、アウグストゥスに盲従していたわけではない。ホラティウスはアウグストゥスに、アウグストゥスや義理の息子ティベリウスとドルーススの事業を祝賀する『皇帝讃歌』を作成するように命じられるが、気乗りがしないようで、壮大なテーマを思いつかず、締りのない冗長な作品をやっとのことで仕上げた。そのほかマエケナスは援助している詩人たちにアウグストゥスを讃えるように要請するが、詩人たちはたびたび言い訳をして断っている。事実、アウグストゥス時代に直接アウグストゥスを讃える政治的な叙事詩はほとんど生まれなかった。これでは、アウグストゥスの事実上の帝政を正当化するのには不十分ではないのだろうか。更には、アウグストゥスを風刺する作品すら作られたことがあるそうだが、彼は笑ってすまし、文学活動を弾圧したり検閲したりせぬようにティベリウスに訓戒を与えたという。アウグストゥス自身は文学作品をイデオロギー戦略としてどのくらい重要視していたのだろうか。期待していないはずはないが、全幅の信頼とも言えないであろう。「イデオロギーを創ったのではなく利用した」「詩人たちが独自の表現を見つけるに任せる」と Wallace-Hadrill 自身が述べているのも、その表れではないだろうか。
しかし、たとえ忠誠を以ってアウグストゥス自身を讃えなかったとしても、ウェルギリウスもホラティウスも長年続いた内戦にはうんざりしており、内戦を終結させた点においては評価しているのは確かであろう。文学は権力に純粋に奉仕したのではなく、アウグストゥスの政治革命が、単に野心家たちによる権力の暴力的奪取ではなく、「秩序の回復」というローマ人全体の願いであり、アウグストゥスの利益がそのままローマの利益に一致したので、文学もそれに呼応したのではないだろうか。アウグストゥスは、政敵アントニウスがオリエントの華美な習慣を身につけ、酒と女に溺れて滅んだのとは違い、欠点はあれど、あくまでローマ人であった。その対比から、国を愛する者にとって、アウグストゥスを支持することは、ローマの伝統を支持することにつながったのではないだろうか。
もうひとつ、ローマの思想にユダヤ・キリスト教の思想が影響していたということが問題になる。斬新な仮説で、一考の価値ありとは思うが、やはりそのまま賛同できないと思う。まず、前半で挙げられたウェルギリウスの『牧歌集』の第4歌に、『イザヤ書』の第 11 章を連想させる、黄金時代を導く神的な力を持った子供の誕生が予言的口調で述べられていることから、東方の救世主思想が影響したと主張されるが、『イザヤ書』第 11 章とこの詩を比較すると、類似点よりむしろ相違点のほうが多い。ではこの「救世主」とは誰か。当時、オクタウィアヌスとアントニウスの協定によって、平和が一時的に成るが、まだこの時点でオクタウィアヌスにも、もちろんアントニウスにも救世主信仰を生み出す力はなかった。もともと、アントニウスの部下であるポリオに捧げられた詩であるので、後に救世主と讃えられるオクタウィアヌスの意図が入り込んだとは考えにくい。しかし、一時的にでもカエサルの後継者2人が和解して、当時のローマ人たちがこれから来る平和に寄せた期待は大きく、誕生を予言された子どもとは、来るべき平和を象徴的に表したものではないかと考えられる。平和という抽象的で、特定の人間を表したのではないものであったとすると、もはや東方の救世主思想は当てはまらないのではないだろうか。また、セネカとパウロの思想の類似点が論じられるが、ギリシア神話が、好ましくない現状を説明するのに、過去を振り返ったのと同じように、皇帝支配という本来ローマ人が嫌う現状を納得させるために、人々の罪深さを理由にするのは、キリスト教思想の影響がなくとも、ごく自然に起こりえることではないか。また同様に、救済者とみなされる者 ( この場合は皇帝 ) が、許しや寛容を示し、最高の時代に導くと考えられるのも、特別なことではなく、必ずしも東方の思想の影響のためとは言えないはずだ。しかも、ここでは寛容の内容が両者の間で大きく違う。確かにローマとユダヤ・キリスト教の思想の間には、類似点もあり、なんらかの共通する概念があったかもしれないが、かといってイデオロギーに影響したというのは、慎重さを必要とするだろう。
アウグストゥスの時代は文学においても黄金時代といわれるが、この時代はそれまでほぼ同数だった散文と詩の均衡が崩れ、詩がはるかに散文に勝る時代であった。これは、演説によって世論に働きかけ、歴史の流れを変える大雄弁家の時代が終わったためだが、弁舌に代わって、詩が古代の伝説を詠い、過去の出来事から連続性を抽出することで、社会に対して重要な役割を果たした。詩が重要な役割を果たしたと考えられるのは、書物があまり普及せず、教育が大幅に記憶に頼っていた時代には、子どもの頃から詩人の作品の長い一節を暗記して、集団で朗詠することで、精神教育が行われていたので、イデオロギーを浸透させるにはかなり効果を発揮したのではないかと考えられるからだ。ただ、詩によって、イデオロギーを広めることが出来たとしても、それが何処まで現実に反映されたかについては慎重にならなくてはならないだろう。ウェルギリウスは農業人口が減って慢性的な穀物不足であった当時の社会を反映して、農業労働に尊敬を払わせるべく、『農耕詩』を製作するが、発表された頃には輸入で不足が解消されていたこともあって、ウェルギリウスが賛美した農業とは正反対の大土地所有による大農経営が発展しただけで、当初考えられていたような目的には、全く役立たなかった。風俗の改革にも失敗している。
この論文に続く研究は今のところ文学者によるものが主になっているが、歴史的観点からの分析も必要であろう。第5節を見ると、イデオロギーに関してまだはっきりと答え切れていない問題があるように思う。 イデオロギー研究は、対象が確たる形で残るものではなく、捉えにくいものなので、まだまだ議論・研究の余地を残している。