スタッフ・学生紹介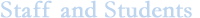
Robin Osborne, Introduction
本書は1982年から2001年にかけて Past and Present 誌に掲載された古代史関係の論文選である。同様の企画としては M. Finley, Studies in Ancient Scoeity (London, 1974) が、1970年までの掲載論文をまとめているが、フィンリー編の論文選と今回のオズボーン編の論文集のあいだには、その間の時代の変遷を反映して、研究手法と対象の拡がりをみいだすことができる。
序章では、編者である R ・オズボーンが M ・フィンリー編の論文選を意識しながら、編集方針について解説している。オズボーンによれば、その間の変化の最たるものは、フィンリーが強調しなければならなかった視点、つまり政治的な事件や制度は同時代の社会構造 structure のなかでした理解できないという主張 ? が、今日ではとくに論じる必要もないほどに標準化していることである。政治・事件・制度を社会の中にはめ込まれたものとしてとらえようとする立場は、よりひろく歴史学全般をとらえた場合には、アナール運動を中心とする、近年の政治史回帰と、政治史と文化史の交錯状況と共鳴するものであるといえよう。このような制度史の拡散と、制度化されない歴史への関心を、オズボーンは M ・フーコーの影響ととらえている。フーコーの著作の中で「社会的諸関係は権利関係であるという思想」「政治諸制度の中に権力を位置づける」という思想は、たとえば『監獄の誕生』のなかに明示されていよう。それにたいしてオズボーンは、フーコーが『性の歴史』でセクシュアルなふるまいが社会慣行に規定されていることを示したことに注目する。なぜならばフーコーの『性の歴史』はギリシア文学者 K ・ドーバーの『古代ギリシアの同性愛』とともに、ギリシア史における同性愛研究のターニング・ポイントとなったからである。本論文集所収の2論文は、それ以降ギリシアの同性愛についての認識が、現代の同性愛や性愛についての観念に規定されながらも、深化していく過程を反映している。
オズボーンによればフーコーの新しさは、知と権力の関係を明確に理論化したことにあった。知のありかたを問題とする Intellectual History の流行を反映して、本書所収論文にも、アルテミドロス、パウサニアス、イソップ伝など、思想的・文学的史料から、狭い意味での事実ではなく、著者(あるいは著作)の反映する自己認識や社会認識を追求するものが目立っている。これらはフィクションを歴史の対象とし、また、一つの文献をひとまりのものとして扱う点が特徴的であり、文学と歴史学の接近と、歴史史料としての文学の価値の再評価を、反映している。しかしながら、所収諸論文は、あくまで、作者や作品に内向化していく文学研究ではなく、歴史家の仕事である。それらは、夢についての観念であれ、ギリシア人としての自己認識であれ、これらは、「理念」が構築され、社会的ないろいろな立場の中で諸集団が相互に交渉したり操作を加えるなかで、「理念」が構築されていく過程であるとか、集団や個人の自己認識の形成を関心の対象としているのである。
全体は時代別の構成になっている。時間の関係等により、授業中にとりあげることのできなかった論文、書評のそろわなかった論文もあるが、個別論文の紹介については、以下、ゼミ受講生の手にゆだねたい。