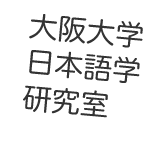お知らせ:『現代日本語研究』第9号(2017)以後の号に掲載された論文は、OUKA (Osaka University Knowledge Archive) に掲載されています。以下、各号の数字をクリックするとOUKAの目次に飛びます。
現代日本語研究

第15号(2024.03)
- 「〈最終講義〉探索的コーパス言語学・補考」石井 正彦
- 「抽象名詞の計量的語誌データ―雑誌と新聞のの経年コーパスを見比べる―」金 愛蘭
- 「日中における無生物主語他動詞文の使用実態調査―レジスターとジャンルに注目して―」麻 子軒
- 「借用語における形態素脱落の通時的変化―英語からの借用語における屈折辞 -ed の場合―」眞野 美穂
- 「日本語の否定対極表現とアクセント(Ⅱ)―最小表現の数詞“ 1 ”を含む名詞句に助詞“も”が後接する場合―」三宅 知宏
- 「数量詞を含む同格構造についての再検討―同格名詞句との比較から―」眞野 美穂
- 「「最後」と比べた「一番最後」の特徴」保田 凪澄
- 「現代新聞語彙における副用語の“非基本語化”―使用率減少と散布度増加の関係からみた量的類型―」石井 正彦
- 2021年度卒業論文要旨
- 「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究―「在室(する) 」,「在宅 (する) 」などをめぐって―」小林 英樹 「副詞「まるで」が共起する述語について」朴 秀娟
- 「動詞の第二中止形のアスペクトと述語らしさ―シテイテとシテの比較―」森田 耕平
- 「『歌詞コンテンツデータ集』の概要と研究利用の可能性」東条 佳奈
- 「 新聞社説の叙述系基本語彙」石井 正彦
- 2020年度卒業論文要旨
- 「外国人介護職員の受入れをめぐる地方の課題について―高知県における日本語学習支援を中心に―」佐野 由紀子
- 「漢語複合名詞の形成と再分析―動詞-名詞型複合名詞の二義性―」田野村 忠温
- 「いわゆる「措定文」をめぐって」三宅 知宏
- 「語彙調査における高頻度語の分離に関する計量的検討」石井 正彦
- 2019年度卒業論文要旨
- 「タリ節における「~てみる」をめぐって」高橋 美奈子
- 「文章における位置・出現回数と名詞表現との関わり―新聞記事における〈「事件」をめぐる表現〉の現れ方を通して―」雨宮 雄一
- 「実践医療用語における語構成要素の意味分類試案―「先天性」を例に―」東条 佳奈・相良 かおる・小野 正子・山崎 誠
- 「書きことばにおけるパラ言語情報と非言語情報―ウェブログを例として―」岸本 千秋
- 「政見放送にみられる「聞き手」設定の日韓差について」韓 娥凜
- 「日本語における『聖書』由来の語彙(Ⅳ)―“目からウロコ(が落ちる)”をめぐって―」三宅 知宏
- 「コロケーションの成立と変化に関する事例的検討―新聞「デフレ+動詞」句の通時的頻度調査から―」石井 正彦
-
- 「上級学習者と母語話者の行為要求表現の違い―「励ましの手紙」を例に―」高梨 信乃
- 「非動作性名詞のサ変動詞語幹化用法の意味と特徴」田島 誠也
- 「2ちゃんねる「同人板」の「伏字」―計量分析から見る変形の特徴―」石原 若菜
- 「困難を表す接尾辞「-にくい」「-づらい」の用法―ウェブコーパスに基づく考察―」王 淦
- 「自動車の固有名に見る階層性─メインネームとサブネーム命名の類型」箕川恵理子
- 「一対比較法による日本語名詞句階層の測定」麻 子軒
- 「探索的コーパス言語学のための覚書」石井 正彦
-
- 「復刊にあたって─宮島さんとの思い出とともに」仁田義雄
- 「宮島達夫先生をしのんで」工藤真由美
- 「スタイルから見た新聞記事の名詞型述語文」安達太郎
- 「順接条件節「なら」の接続形態」前田直子
- 「自動車の固有名に見る階層性─メインネームとサブネーム命名の類型」箕川恵理子
- 「近現代語における感情形容詞「切ない」の意味変化」佐々井明里
- 「「擬似助数詞」の成立可否を決める要因」東条佳奈
- 「“イツ”と“カモシレナイ”の共起関係に関する覚書」三宅知宏
- 「文の長さの統計モデル」石井正彦
- 第8号(2001.2)
-
- 「『文章における臨時一語化』の諸形式-新聞の四字漢語の場合-」石井 正彦
- 「発話の非流暢性の引き金と要因について-言語学的音声学的分析-」氏平 明
- 「動詞的要素と名詞的要素で構成される二字漢語動名詞に関する再考」小林 英樹
- 「『ことばのはやし』と『ことばのその』-付載文典の比較について」山東 功
- 「動詞『思う』のモーダルな用法について」宮崎 和人
- 第7号(2000.3)
-
- 「アスペクトテンス体系と極性」工藤 真由美
- 「『するべきだ』『したほうがいい』と『しなくてはいけない』の違いについての覚え書き」雨宮 雄一
- 「物集高見『日本文語』について」山東 功
- 「江戸期鶴岡方言における意志推量表現形式の変化」舩木 礼子
- 「個人の言語直観の信頼性について-接続詞スルトを含む文連鎖の場合-」本多真紀子
- 「『(ヤ)ガナ』と『ヤンカ』の用法機能上の相違について」前川 朱里
- 「ウチの受身とソトの受身-受身文の意味と構造の対応再考-」山田 敏弘
- 「逆接表現の記述と体系-ケド、ワリニ、ノニ、クセニをめぐって-」渡辺 学
- 第6号(1999.3)
-
- 「現代日本語の文法的否定形式と語彙的否定形式」工藤 真由美
- 「複数事態を表す述語について」小林 英樹
- 「程度副詞との共起関係による状態性述語の分類」佐野 由紀子
- 「大阪方言におけるテオク形の用法-東京方言との対照を中心に-」高田 祥司
- 「若年層の関西方言における否定辞ンヘンについて-談話から見た使用実態-」高木 千惠
- 「ア系統指示詞の用法に関する一考察」庵 功雄
- 第5号(1998.3)
-
- 「言語活動の単位としての文」仁田 義雄
- 「現代日本語受動文の構文的タイプ」張 麟声
- 「文の叙述内容と主題の有無の関わりについての覚書」高橋 美奈子
- 「ダカラとソレデの違いについて」岡部 寛
- 「格成分から主題への取り立て-主題の連続における導入部-」清水 佳子
- 「『シテイル」VS‘PERFECTIVE’‘INPERFECTIVE’-非形態的アスペクト論に向けての試論-」池田 英喜
- 「程度を表す連体修飾成分について-程度評価づけの修飾成分と数量的程度の修飾成分-」呉 [ケン]定
- 「『VNをする』構文で使えない動名詞について」小林 英樹
- 「程度限定における「主観性」について」佐野 由紀子
- 「基準時から見て、相対的な未来の動作変化を表す副詞(その2)」高 正道
- 「《累加》から《展開》へ-いわゆる接続詞分類の一試案-」黄 淑燕
- 「日本語の参与者追跡システムについて(3)-連体修飾節のベネファクティブを中心に-」山田 敏弘
- 第4号(1997.3)
-
- 「受動文の分類について」張 麟声
- 「受け取り取り外し動詞から形成される受身文について」丁 意祥
- 「措定文の一面-主格名詞句が『が』でマークされる措定文について-」高橋美奈子
- 「主題連鎖と『のだ』との関連」清水佳子
- 「二字漢語動名詞の主要部について」小林英樹
- 「 連体修飾表現に関する日韓対照研究-「の』に対応する韓国語の『wi』『in』-」呉 □定
- 「発話行為文の文末に出現するタ形」池田英喜
- 「基準時から見て、相対的な過去を表す時間副詞その1-アスペクトの面を中心として-」高 正道
- 「日本語の参与者追跡システムについて(2)-談話における複文中のベネファクティブを中心に-」山田敏弘
- 第3号(1996.3)
-
- 「条件接続形式を用いた<勧め>表現-シタライイ、シタラ、シタラドウ-」高梨 信乃
- 「日本語の主題素性の照合と句構造」三宅 知宏
- 「『ニ』型有情動作主明示式非情受身文について」張 麟声
- 「ノデの視点とノニの視点-トイウノデとトイウノニから-」岩崎 卓
- 「指示と代用-文脈指示における指示表現の機能の違い-」庵 功雄
- 「日本語の参与者追跡システムについて(1)-」授受表現を中心として-山田 敏弘
- 「修飾節中にコ系指示詞を持つ名詞修飾表現について」高橋 美奈子
- 「仮定を表す『~てみろ』の用法について」長野 ゆり
- 「韓国語の漢語動詞の使役表現」李 楨淑
- 第2号(1995.3)
-
- 「形容詞の名詞かざり」宮島 達夫
- 「テキストの中の文のテンスモダリティ-その一つの覚書-」仁田 義雄
- 「日本語の複合名詞句の構造-制限的/非制限的連体修飾節をめぐって-」三宅 知宏
- 「従属節のテンスと視点」岩崎 卓
- 「語彙的意味に基づく結束性について-名詞の項構造との関連から-」庵 功雄
- 「いわゆる<持ち主の受身>について-非分離性関係の受身について-」丁 意祥
- 「所謂『外の関係』における項の出現制約に関する一考察」山田 敏弘
- 「喚情的前提に関する日中同形語の対照研究-前提評価語の『評価(する)』『指導(する)』を中心に-」高 偉建
- 「『~ておく』の用法について」長野 ゆり
- 第1号(1994.3)
-
- 「発刊にあたって-『初めにことばありき』」宮島 達夫
- 「<疑い>を表す形式の問いかけ的使用-『カナ』を中心とした覚書-」仁田 義雄
- 「否定疑問文による確認要求的表現について」三宅 知宏
- 「所謂確認要求のジャナイカとダロウ-情報伝達機能論的な観点から-」鄭 相哲
- 「 定性に関する一考察-定情報という概念について-」庵 功雄
- 「『こんな』類と『こういう』類」岡部 寛
- 「『トハ』文の主節の述語について」塩入 すみ
- 「『~てみる』の用法の一側面-命令形条件表現をとる『~てみる』の用法について-」長野 ゆり
第14号(2022.12)
第13号(2021.12)
第12号(2020.12)
第11号(2019.3)
第10号(2018.3)
第9号(2017.3) [復刊]
表示できない一部の文字を□で置き換えている箇所があります。ご了承下さい。