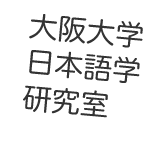教員紹介
-
三宅 知宏(みやけ ともひろ)教授

- 研究分野:
- 日本語学・言語学
- 専門:
- 日本語学・言語学
- 研究テーマ:
- 普遍的な一般言語研究を視野に入れた,個別言語としての日本語の研究
- E-mail:
研究紹介
普遍的な一般言語研究を視野に入れつつ,個別言語としての日本語の具体的な言語現象について,分析を行っています。その際,日本語を母語としない人向けの日本語教育や,母語話者向けの国語科教育への応用可能性も念頭においた「観察」,「記述」を心掛け,一般言語研究における言語理論への展開をふまえた「説明」を目指しています。なお,対象とする言語現象,および依拠する言語理論に,制限は加えていません。興味を持てば,何でも対象にし,何でも方法にする,というスタイルです。
メッセージ
(学部志望者に) 例えば「太郎が部屋( )出た」,「煙が煙突( )出た」という二つの文の( )内に適切な助詞を入れる場合,前者は“から”“を”のどちらでもよいのに対し,後者は“を”が不可で,“から”のみ可能であることを,日本語を母語とする人であれば「知っている」はずです。しかしそれをすぐに説明できるでしょうか。「知らない」ことを「知る」ようになるのではなく,「無意識に知っている」ことを「意識的に知る」ようになるという学問分野の面白さを紹介したいと思っています。 (大学院志望者に) 日本語と呼ばれる言語(諸方言も含む)は,どのような性格の言語なのか,他の言語とどのように違い,どのように同じなのか,そもそも人間の言語(日本語も含まれる)とはどのようなものか,というようなことに関心を持ち,その解明に挑んでみようとする人にとって,本学は最高の研究環境にあると断言できます。 -
眞野 美穂(まの みほ)准教授

- 研究分野:
- 言語学・日本語学
- 専門:
- 形態論・統語論
- 研究テーマ:
- 通言語学的な一般化を目指した、日本語の研究。
- E-mail:
- m.mano.hmtアットマークosaka-u.ac.jp
研究紹介
これまで、主に現代日本語を対象とし、語自体が持つ情報と、それが文の中で果たす機能、そして作り出される文の構造との関係に焦点を当てながら、与格主語構文、類別詞や同格名詞句などの研究を行ってきました。他言語の言語現象との共通点や差異を考えることで、通言語的な一般化を目指しています。ただ、特に名詞に関しては、まだまだ十分に記述されていない言語現象も多いことから、これからは、より多角的に名詞を観察し、動詞研究の知見と融合させることで、体系的な分析につなげたいと考えています。
メッセージ
日本語は研究の蓄積が多い言語の1つですが、それでもまだまだわからないことの方が多いのが現状です。皆さんが日々ことばを使う中でふと感じた疑問が何かを解き明かす問いになるかもしれません。ただ、その疑問から仕組みを探り、そこに潜む法則を解き明かすためには、できるだけ多くの言語現象やその特徴を知っておく必要があると思います。様々な言語現象(そして言語にも)に出会える本学で一緒に日本語の研究に取り組んでみませんか?
(Webサイトはこちら) -
高木 千恵(たかぎ ちえ)教授

- 研究分野:
- 社会言語学
- 専門:
- 社会言語学、方言学
- 研究テーマ:
- 接触による言語の変容、方言文法の記述、方言の記録と保存
- E-mail:
- takagicアットマークlet.osaka-u.ac.jp
研究紹介
社会言語学を専門にしています。具体的には、異なる体系を持つ言語(方言)どうしの接触によって起こるダイナミックな言語変化に興味を持っています。これまでは、関西の若年層の話しことばに注目して、メディアによる標準語の影響を受けながらも独自性を保ち続ける地域語の姿を明らかにしてきました。地域社会に生きる人々が、標準語という絶対的権威をもつ言語変種と日常的に接触しながら自身のことばをどのように運用しているか、その実態を解明し、地域社会のことばの動向を追究したいと考えています。
メッセージ
社会言語学は、ことばと、それを操る人間とのかかわりに関心を寄せる学問分野です。わたしたちは決して、日本語の教科書に出てくるようなことばづかいだけで生きているわけではありません。相手に応じて、場面に応じて、ときには無意識のうちにことばを切換えています。その、とらえどころのない生きたことばたちと向き合いながら、ことばの使い手である人間を理解していくのが社会言語学だと思っています。みなさんが日常生活のなかで感じることばへの疑問の多くが、社会言語学のテーマになりうることと思います。
(Webサイトはこちら) -
新谷 知佳(しんたに ちか)助教

- 研究分野:
- 日本語学、日本語教育
- 専門:
- 日本語学、コーパス
- 研究テーマ:
- コーパスを用いた自他対応をもつ動詞対における自他の使用傾向の分析
- E-mail:
- shintani.hmtアットマークosaka-u.ac.jp
研究紹介
コーパスにおける使用頻度の分析を通して、日本語の自動詞と他動詞の使用傾向について研究しています。日本語には、「乾く」「乾かす」、「挟まる」「挟む」のように対応関係にある自動詞と他動詞がたくさんありますが、それぞれの動詞対で自他の使用傾向は異なっています。日本語教育への応用を目指し、どのような傾向の違いがあるのかを明らかにすることを目指しています。
メッセージ
日本語非母語話者への日本語教育に携わる中で抱いた疑問や違和感が、研究の出発点になっています。母語話者にとっては当たり前のことでも、教える際にはその仕組みを丁寧にわかりやすく伝えなければなりません。たとえば、留学生に「窓が開いている」と「窓が開けてある」はどう違うか、と聞かれたら何と答えますか。その説明は、名詞、動詞を置き換えた文でも成り立つでしょうか。よく使う、あまり使わないといった使用傾向の違いはあるでしょうか。単純そうに見えてそうでないことも多くあります。ぜひ一緒に議論しましょう。