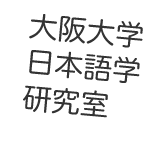お知らせ:『阪大日本語研究』に掲載された論文は、OUKA (Osaka University Knowledge Archive) に掲載されています。以下、各号の数字をクリックするとOUKAの目次に飛びます。
阪大日本語研究

第36号(2024.2)
- 「日本語における数量詞の共起と合成の仕組みに関する一試案」眞野 美穂
- 「生活情報番組のディスコース・ストラテジー : 固定的性別役割分業意識の容認へと導く言語的装置の分析」西野 由起江
- 「「-まる」「-める」を伴う形容詞派生動詞の使用傾向 : 自他対応に着目して」新谷 知佳
- 「タンデム学習の会話における日本語学習者の他者開始 : パートナーの自己修復:ことばの説明に導く連鎖」蔡 真彦
- 「中国人日本語教室学習者の日本語談話におけるフィラーの使用に関する一考察 : 第二言語環境習得と外国語環境習得の違いに注目して」冷 羽涵
- 彙報
- 編集後記
第35号(2023.2)
- 「現代新聞における語結合の慣用化」石井 正彦
- 「日本語のチューター活動における訂正 : 会話分析の観点からの一考察」李 頌雅
- 「タンデム学習におけるテキストの読み上げ活動」蔡 真彦
- 彙報
- 編集後記
第34号(2022.2)
- 「現代新聞語彙における“基本語化と“非基本語化”―使用率・均等度の平均変化率を用いた量的検討―」石井 正彦
- 「接種」の語史―種痘関連用語の生成と消長―」田野村 忠温
- 「補助動詞“しまう”の用法と意味的構造」近藤 優美子
- 「生活情報番組“あさイチ”の談話行動に組み込まれるジェンダー・イデオロギー―批判的談話研究の視点から―」西野 由起江
- 「明治期における接尾辞「化」の展開―学術誌における用法を中心に―」沙 広聡
- 彙報
- 編集後記
第33号(2021.2)
- 「博物館内ツアーにおいて観客にガイドの物語への参与を促す実践」バーデルスキー・マシュー
- 「音訳語「珈琲」の歴史」田野村 忠温
- 「ことばの説明実践―留学生チューティーと日本人大学生チューターの学習活動を中心に―」李 頌雅
- 「他者開始におけるポライトネス・ストラテジーの場面間切り替え―韓国語母語話者の日本語談話と韓国語談話の対照分析―」金 道瑛
- 「地方在住外国人労働者の日本語バラエティに対する意識―質的アプローチによる予備研究―」ヘネシー・クリストファー
- 彙報
- 編集後記
第32号(2020.2)
- 「若年層関西方言話者のカジュアルスタイルにおける「ネ」の使用」高木 千恵
- 「福沢諭吉のコルリ(カレー)をめぐって」田野村 忠温
- 「関西若年層のカジュアル談話にみるスタイル切換え―首都圏移住者を例に―」上林 葵
- 彙報
- 編集後記
第31号(2019.2)
- 「関西方言における素材待遇形式の分布―読みがたり昔ばなし資料を手がかりに―」酒井 雅史
- 「日本の大学院の実践共同体に参加する初期段階における学習過程―ある中国人留学生のインタビュー調査から得た理解―」郭 菲
- 「中国人技能実習生の日本語学習アプローチ―日本語能力試験のN1、N2に合格していない人1)に焦点を当てる―」栄 苗苗
- 「現代新聞の「うれしい+名詞」表現における感情惹起のパターン」李 河恩
- 彙報
- 編集後記
第30号(2018.2)
- 「名詞の助数詞的用法に関する検討―カテゴリー化に注目して―」東条 佳奈
- 「ウェブログの計量的文体研究―文末表現とウェブ記号の関係を中心に―」岸本 千秋
- 「日韓政治ディスコースにおける正当化ストラテジー―批判的談話分析による異文化間対照の試み―」韓 娥凜
- 「連語論的アプローチによる無生物主語他動詞文の日中対照―対格名詞が「人名詞」である場合―」麻 子軒
- 「社会的文脈から日本語学習と学習者オートノミーを捉える試み―日本で働く中国出身者の学習経験についてのライフストーリーをもとに―」中井 好男
- 彙報
- 編集後記
第29号(2017.2)
- 「否定疑問文と確認要求的表現―対照方言研究の一試論―」三宅 知宏
- 「対面式タンデム学習における学び:日本語学習者と日本語話者のやりとりにおけるLREを手がかりに」青木 直子・栄 苗苗・郭 菲・劉 姝・王 静斎・丁 愛美
- 「連語論的アプローチによる無生物主語他動詞文の日中対照―対格名詞が事名詞である場合―」麻 子軒
- 「ウェブログの計量的文体研究―文とウェブ記号の関係を中心に―」岸本 千秋
- 「日韓同性間の会話における不同意・否定的評価の相互行為―ジェンダーとポライトネスの観点からみる対立と冗談―」張 允娥
- 「EPA介護福祉士候補者による日本語の専有― 1年間のインタビューにもとづくケース・スタディ―」藤原 京佳
- 「上級日本語学習者に見られる文法の問題―修士論文の草稿を例に―」高梨 信乃・齊藤 美穂・朴 秀娟・太田 陽子・庵 功雄
- 「鹿児島県甑島里方言の終助詞」白岩 広行・門屋 飛央・野間 純平・松丸 真大
- 彙報
- 編集後記
第28号(2016.2)
- 「山形市方言の文末詞の相互承接」渋谷 勝己
- 「動詞の第二中止形の意味と機能―姿勢変化動詞の分析―」森田 耕平
- 「自然習得者における中間言語的特徴の定着化―自然談話データにみる連体修飾表現を中心に―」小田 佐智子
- 「日本語学習者がインターネット上のリソースを教室外の学習に利用し始めるメカニズム:修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(M-GTA)による理論構築」欧 麗賢
- 「中国人留学生の日本の大学院の学術的コミュニティへの参加―文系大学院生のケース・スタディ―」郭 菲
- 「日本語が上達した中国人研修生の日本語学習アプローチ」栄 苗苗
- 彙報
- 編集後記
第27号(2015.3)
- 「関西の接客場面における形式名詞ブンの拡張用法」高木 千恵
- 「日本語学習者によるピア・レスポンスにおける教師の支援とスキャフォールディングとしての可能性」中井 好男
- 「南琉球八重山黒島方言におけるテンス・アスペクト・エビデンシャリティー接尾辞jassuの記述的研究」原田 走一郎
- 「動詞の第二中止形が表す意味―アスペクトと動詞のタイプに注目して―」森田 耕平
- 「名詞型助数詞の用法―準助数詞「セット」と「組」を中心に―」東条 佳奈
- 「タイ人配偶者の否定表現に関する事例研究―自然習得と教室学習を比較して―」小田 佐智子
- 「滋賀県長浜市方言における素材待遇形式の運用―語用論的運用とその要因―」酒井 雅史
- 「Professional learning communityにおける教師の学び:タイの大学で教える日本語教師のケース・スタディ」大河内 瞳
- 彙報
- 編集後記
第26号(2014.3)
- 「沖縄系2世における言語生活史と日本語保持に関わる要因―ブラジルとボリビアの沖縄系移民社会の場合―」 朴 秀娟/森 幸一/工藤 眞由美
- 「言語社会化の過程―親子3人の会話における謝罪表現を中心に―」マシュー・バーデルスキー
- 「近畿方言におけるネン・テンの成立―昔話資料を手がかりに―」野間 純平
- 「南琉球八重山黒島方言における形容詞のサブグループ―接辞kuが続く形式に注目して―」原田 走一郎
- 「滋賀県長浜市方言における待遇表現形式の使い分け―面接調査による使い分けの意識から― 」 酒井 雅史
- 「目標言語話者とのEメールのやりとりを通した教室外の日本語学習」欧 麗賢
- 彙報
- 編集後記
第25号(2013.3)
- 「沖縄系エスニックコミュニティにおける日本語と沖縄方言の継承意識ーブラジル及びボリビアの言語生活調査からー」朴 秀娟/森 幸一/工藤 真由美
- 「ハワイ日系社会における方言接触と人称代名詞の様相ー残されたオーラルヒストリーデータをもとにー」白岩 広行/平本 恵美/朝日 祥之
- 「大阪方言におけるノダ相当表現ーノヤからネンへの変遷に注目してー」野間純平
- 「教師の悩みはどこから来るのか?ー日本語教師たちとのナラティブ探究を投資てー」末吉 朋美
- 「Eタンデムにおいてドイツ人日本語学習者の動機を変化させた要因」脇坂 真彩子
- 彙報
- 編集後記
第24号(2012.2)
- 「『新しい歴史教科書』の言語使用 —中学校歴史教科書8種の比較調査から—」 石井 正彦
- 「福島方言の自発表現」 白岩 広行
- 「福岡市方言のアスペクトマーカにみられる言語変化」 平塚 雄亮
- 「対面式タンデム学習の互恵性が学習者オートノミーを高めるプロセス:日本語学習者と英語学習者のケース・スタディ」 脇坂 真彩子
- 彙報
- 編集後記
別冊3(2011.2)
- 「20世紀後半の新聞語彙における外来語の基本語化」金 愛蘭
第23号(2011.2)
- 「ブラジルとボリビアにおける沖縄系エスニックコミュニティと日本語」白岩 広行/森田 耕平/齊藤 美穂/朴 秀娟/森 幸一/工藤 眞由美
- 「接続助辞ガ・ケレドモの意味・機能と文法的制約」齊藤 美穂
- 「方言の推量形式における意味変化 −談話的機能へ−」白岩 広行
- 「教師による「語りの場」の意義 −ある日本語教師とのナラティヴ探求を通して−」末吉 朋美
- 「形態素の自立用法と結合用法の関係 −外来語系語基「メール」の通時的な遷移傾向を例に−」金 妹伶
- 「略語の使用とカテゴリー的意味 −『朝日新聞』の「コンビニ」を例に−」クドヤーロワ タチアーナ
- 彙報
- 編集後記
第22号(2010.2)
- 「Teacher anxiety revisited: A permeating sacred story 」AOKI Naoko
- 「ボリビアのオキナワ移住地における言語接触」白岩 広行/森田 耕平/王子田 笑子/工藤 真由美
- 「否定とも肯定とも共起する副詞「とても」について -否定用法に見られる「条件づけ」を中心に-」朴 秀娟
- 「マルチメディア・コーパスの構築と活用 -表現行動の計量的研究のために-」孫 栄奭
- 「帰国児童における第二言語としての日本語の磨滅 -流暢さに注目して-」金 昴京
- 「文末形式の運用とスタイル切り換え -日本語を学ぶ中国語母語話者の縦断データから-」寺尾 綾
- 「日本に定住する中国人はなぜ地域の日本語教室をやめるのか -学習者の背後にある社会的環境からその原因を見る-」周 萍
- 「中国人就学生の日本語学習の実態 -再履修者のケース・スタディによる分析-」中井 好男
- 「「ネイティブ」教師・「ノンネイティブ」教師の意識とその実践 -ティーム・ティーチングを通して見えてきたもの-」岡本 和恵
- 彙報
- 編集後記
第21号(2009.2)
- 「テレビ放送のマルチメディア・コーパス -映像・音声を利用した計量的言語使用研究の可能性-」石井 正彦
- 「コーパスからのコロケーション情報抽出 -分析手法の検討とコロケーション辞典項目の試作-」田野村 忠温
- 「臨時的な複合名詞を作る2字漢語形容動詞について」蔡 珮菁
- 「副詞に接続するガ・ケレドモの用法」齊藤 美穂
- 「「大阪方言の命令形」に後接する終助詞ヤ・ナ」牧野 由紀子
- 「大阪方言アクセントにおける二拍5類語の現在 -三世代話者の読み上げデータからのケーススタディ-」武田 佳子
- 「地域の日本語教室をやめた中国人学習者のケース・スタディ」周 萍
- 「中国人就学生の学習動機の変化のプロセスとそれに関わる要因」中井 好男
- 「調査報告:五箇山真木集落36年後 -待遇表現体系の拡散-」辻 加代子/金美貞
- 彙報
- 編集後記
第20号(2008.2)
- 「「標準語」の多様性を認める言説についての覚書 -特に1940年前後に注目して-」岡田 祥平
- 「動詞テ形に由来する副詞的成分の「副詞度」算出の試み」林 雅子
- 「「名詞+の」における叙述性の一考察」三浦 晃弘
- 「ある中国語を母語とする日本語学習者の言語的あいづち -日本語の習熟度からみた縦断的分析-」寺尾 綾
- 「韓国高年層日本語の否定表現からみる第二言語の保持」黄 永煕
- 「話の聞き取りに関わる撥音の長さ -近畿方言話者と首都圏方言話者-」山岸 智子
- 「初級クラスにおける媒介語の使用とやり取りの構造 -日本語を第2言語とするスリランカの日本語教師の考え方と授業実践-」ロクガマゲ・サマンティカ
- 「韓国人留学生のライフストーリーにみる留学の満足 -大学生活に対する期待との関わりから-」中山 亜紀子
- 彙報
- 編集後記
第19号(2007.2)
- 「関西方言のヤンナとヨナ」松丸 真大
- 「名詞句に接続するガ・ケドの用法」齊藤 美穂
- 「敬語形式「オイデ」の意味用法の変化」水谷 美保
- 「尾高型アクセントの二拍形式名詞が頭高型で発音されるとき -『日本語話し言葉コーパス』を用いた分析-」出野 晃子
- 「韓国人留学生のライフストーリーから見た日本人学生との社会的ネットワークの特徴 -「自分らしさ」という視点から」中山 亜紀子
- 「ドイツで育った日本人青年たちの日本語学習経験 -海外に暮らしながら日本語を学ぶ意味-」山口 悠希子
- 「新世代留学生の精神的成長に関するケース・スタディー -日本語教育への示唆」範 玉梅
- 「目標言語を第2言語とする教師とその実践 -スリランカの日本語教師のケース・スタディー-」ロクガマゲ・サマンティカ
- 彙報
- 編集後記
別冊2(2006.2)
- 「関西若年層の話しことばにみる言語変化の諸相」高木 千恵
第18号(2006.2)
- 「山形市方言の文末詞シタ -ベシタ・ガシタの意味にもとづいて-」渋谷 勝己/澤村 美幸/大久保 拓磨/松丸 真大
- 「スタイル切換えと切換え能力の発達 -青森県弘前市方言話者の目的表現を例に-」阿部 貴人
- 「「縮約形」再考」岡田 祥平
- 「韓国語話者の日韓両音声による「パラ言語情報」の実現に関する考察 -「問い返し」と「疑い」の比較を中心に-」李 宝瓊
- 「無意味語による日本語のリズム単位に関する一考察 -韓国語を母語とする学習者との比較の場合-」尹 英和
- 「「ざわざわ」とした教室の背後の専門的意味ーナラティブ探求から探るー」李 暁博
- 彙報
- 編集後記
第17号(2005.2)
- 「体験的過去をめぐって -宮城県登米郡中田町方言の述語構造-」工藤 真由美/佐藤 里美/八亀 裕美
- 「友だちとの会話と第2言語学習は両立するか -L1使用者とL2使用者の会話における訂正と発話援助-」永見 昌紀
- 「日本語学校における一人っ子の中国人留学生増加に伴う問題」範 玉梅
- 「韓国における接客言語行動意識-客側からの評価-」金 美貞
- 「〈女ことば/男ことば〉規範をめぐる戦後の新聞の言説 -国研「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」から-」佐竹 久仁子
- 「1950年代のブラジル日系社会と日本語」山東 功
- 彙報
- 編集後記
第16号(2004.3)
- 「ムードとテンス・アスペクトの相関性をめぐって」工藤 真由美
- 「Life after presentation: How we might best discuss and evaluate narrative-based research with / by teachers」AOKI Naoko
- 「関西圏における接客敬語行動-店舗形態におけるバラエティ<その2>-」真田 信治/金 美貞
- 「形容詞の文中での機能」八亀 裕美
- 「感情表現における普遍性(ユニバーサリティ)と言語文化属性:感情の知覚差」イブラヒム インガ
- 「日本語教師の専門知についてのナラティブ的理解」李 暁博
- 「『~まで』の意味・機能-〈格〉と〈とりたて〉の連続性-」難波 真奈美
- 「『特別な思い』と『特別の思い』-〈第二形容詞〉と〈第三形容詞〉の揺れについて-」中山 陽介
- 彙報
- 編集後記
第15号(2003.3)
- 「アスペクトと敬語-岐阜県高山方言の場合-」工藤 真由美/清水由美
- 「形容詞の評価的な意味と形容詞分類」八亀 裕美
- 「方言接触が生み出した言語変種に見られる言語的特徴-引用形式「ト」のゼロマーク化を例に-」朝日 祥之
- 「韓・日両言語の反対意見表明行動の対照研究-場の改まり度による表現形式の使い分けを中心に-」李 吉鎔
- 「『道教え』談話における音声的特徴-『くり返し』の発話を中心に-」越野 道子
- 「宮崎方言の『チャ』と『ト』」村田真美
- 彙報
- 編集後記
第14号(2002.3)
- 「終助辞『ネ』と『ナ』」宮崎 和人
- 「高知県幡多方言の使役形式―活用体系変化の一過程―」松丸 真大
- 「韓国語話者による日本語破擦音の音響的特性に関する考察」司空 煥
- 「徳島・吉野川流域におけるアクセントの現在」真田信治/武田佳子/余 健
- 彙報
- 編集後記
別冊1(2001.2)
- 「現代日本語の形容詞述語文」八亀 裕美
第13号(2001.2)
- 「ダロウの意味」木下 りか
- 「日・韓両言語における反対意見表明行動の対照研究―談話構造とスキーマを中心として―」李 吉鎔
- 「日本語学習者のタスク遂行過程における『気づき』」御舘 久里恵
- 「在日コリアン1世の接触変異音の生起と定着過程について―異なる社会的属性を有する1世を事例として―」金 美善
- 「地域的標準語の語法上の特徴―『広州普通話』を例として―」陳 於華
- 「母方言アクセントと移住先方言アクセント間の切り換え時に生じた逆転現象と平板型アクセント機能の解釈」余 健
- 彙報
- 編集後記
第12号(2000.3)
- 「八丈方言のアスペクト・テンスムード」工藤 真由美
- 「ミクロネシア・チュークの現日本語学習者による日本語音声」土岐 哲
- 「方言地理学と文法」渋谷 勝己
- 「状態の移行前を表す『もう/まだ』について」池田 英喜
- 「言語行動における遂行義務と回避義務」西尾 純二
- 海外文献紹介:「台湾における日本語普及計画」真田 信治/簡 月真
- 追悼 徳川宗賢先生
- 彙報
第11号(1999.3)
- 「西日本諸方言におけるアスペクト対立の動態」工藤 真由美
- 「『もう』と『まだ』―状態の移行を前提とする2つの副詞―」池田 英喜
- 「テモラウ受益文の働きかけ性をめぐって」山田 敏弘
- 「中根淑『日本文典』について」山東 功
- 「Storytellers in the tourist setting: The construction of language and self in contemporary rural Japan」KAWAMORI Hiroshi
- 海外文献紹介:「台湾における言語衝突史年表」真田 信治/簡 月真
- 彙報
第10号(1998.3)
- 「相互構文を作る『Vシアウ』をめぐって」仁田 義雄
- 「アクセントの下げとイントネーションの下げ」土岐 哲
- 「中間言語における可能表現の諸相」渋谷 勝己
- 「ブラジル人就労者における日本語の動詞習得の実態ー自然習得から学習へー」エレン ナカミズ
- 「日本語学習者のチュートリアルにおけるあいづちとその周辺ーフォローアップ・インタビューによる談話分析を中心にー」今石 幸子
- 「Examining Definitions of Learner Autonomy 」AOKI Naoko
- 「『山田孝雄』について」真田 信治
- 要旨
- 彙報
第9号(1997.3)
- 「プロセスとしての習得の研究」J. V. ネウストプニー
- 「韓国語話者による日本語倒置疑問文のイントネーションー上昇の形式とその習得パターンをめぐってー」土岐 哲/金 秀芝
- 「事例研究についての一考察」由井 紀久子
- 「階層性から一律へ、そして標準化へー五箇山親族呼称の60年ー」真田 信治
- 「旧南洋群島に残存する日本語の動詞の文法カテゴリー」渋谷 勝己
- 「日本語における切り替えの習得段階ーブラジル人就労者の例ー」エレン ナカミズ
- 「断定をめぐって」仁田 義雄
- 「The effect of inherent characteristics of nouns on co-reference」IORI Isao
- 要旨
- J. V. ネウストプニー先生略歴主要業績目録
- 彙報
第8号(1996.3)
- 「語り物の中のモダリティ」仁田 義雄
- 「『それが』とテキストの構造ー接続詞と指示詞の関係に関する一考察ー」庵 功雄
- 「在日韓国人の敬語運用の一斑ー日本語と韓国語の待遇規範意識のはざまでー」黄 鎭杰
- 「日本在住ブラジル人労働者における社会的ネットワークと日本語の使用」エレンナカミズ
- 「旧ヤップ公学校卒業生の日本語談話能力ー訂正過程についての一考察ー」由井 紀久子
- 「接触場面における話者交代」俣野 夕子
- 要旨
- 彙報
第7号(1995.3)
- 「多言語社会への対応―大阪:1994年―」宮島 達夫
- 「シテ節の『ハ』による取り立て」仁田 義雄
- 「条件接続形式による評価的複合表現―スルトイイ、スレバイイ、シタライイ―」高梨 信乃
- 「関西圏における接客敬語行動―店舗形態によるバラエティ<その1> ―」真田 信治/井上 文子
- 「日本語教育と言語管理」J. V. ネウストプニー
- 「日本語のリズムに関わる基礎的考察とその応用」土岐 哲
- 「動詞オクの意味の抽象化過程」由井 紀久子
- 要旨
- 宮島達夫先生略歴主要業績目録
- 彙報
第6号(1994.3)
- 「方言学から社会言語学へ」徳川 宗賢
- 「人物の類型化と感情ー常識を基軸とした日常会話分析の試みー」野呂 香代子
- 「可能文における格パタンの変遷」渋谷 勝己
- 「近畿方言の「ル・ラル」敬語に関する一考察」宮治 弘明
- 「京都市方言の丁寧融合型尊敬形式『お~やす』」森山 卓郎
- 「若年層における『問題敬語』の規範意識」尾崎 喜光
- 「富山県の方言について」真田 信治
- 徳川宗賢先生略歴主要業績目録
- 要旨
- 彙報
第5号(1993.3)
- 「日中同形語の文体差」宮島 達夫
- 「関西中央部における『オル』『~トル』軽卑化のメカニズム」井上 文子
- 「尊敬の助動詞『ハル』の成立をめぐってー明治期大阪語の場合ー」金沢 裕之
- 「二重ヲ格制約と第2言語獲得」阿部 忍/ダグラス・サディ
- 「『テハ』条件文の制約について」塩入 すみ
- 「モラウの意味的抽象化・希薄化の過程」由井 紀久子
- 「聞き手の行動 ~あいづちの既定条件~」今石 幸子
- 要旨
- 彙報
第4号(1992.3)
- 「十津川流域の可能表現」渋谷 勝己
- 「関西共通語化の現状―大阪型待遇表現形式の伝播をめぐって―」中井 精一
- 「談話における非言語行動の一側面―首振り動作・視線と談話との関係について―」山田 美樹
- 「『Xハ』型従属節について」塩入 すみ
- 「複文における『の(だ)』の機能-『のではなく(て)』『のでは』と『のだから』『のだが』-」野田 春美
- 要旨
- 彙報
- 付録:開設以来の言語関係講義題目
第3号(1991.3)
- 「寺村秀夫先生の思い出」玉村 文郎
- 「寺村秀夫の日本語文法研究への誘い」仁田 義雄
- 「『 デハ』の機能ー推論と接続語ー」浜田 麻里
- 「『のではなく』の機能」小金丸 春美
- 「韓日両言語の受身構文」李 吉遠
- 「日本語学習と日本語の文化的要素」高 偉建
- 「方言の語彙」徳川宗賢
- 寺村秀夫先生略年譜業績目録
- 要旨
- 彙報
第2号(1990.3)
- 「意志のモダリティについて」森山 卓郎
- 「引用プロトタイプ論を目指してー間接化に関する三つの原則を中心にー」王 笑峰
- 「『という』の機能について」中畠 孝幸
- 「『ので』の情報領域ー『から』の対話性と比較してー」花井 裕
- 「近畿中央部における人を主語とする存在表現の使い分けについてーアンケート調査から見た若年層の実態ー」宮治 弘明
- 要旨
- 彙報
第1号(1989.3)
- 「日本語研究のながれ」徳川 宗賢
- 「関西周辺部における言語接触の一斑-語法に関するグロットグラムから-」真田 信治
- 「述べ立てのモダリティと人称現象」仁田 義雄
- 「応答と談話管理システム」森山 卓郎
- 「意味研究メモ その1」寺村 秀夫
- 「『~のだ』の本質を求めて-再び山口佳也氏に答えて-」佐治圭三
- 要旨