研究会・学術・学習情報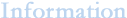
『パブリック・ヒストリー』
◆◇ 第3号(2006年2月出版) ◇◆
竹中 亨「ジャポニスムから世紀末の憂鬱へ ― 19 世紀末のオーストリアにおける日本観―」、1-18頁
デニス・O・フリン、アルトゥーロ・ヒラルディス(平山篤子訳)「グローバリゼーションは1571 年に始まった」、19-33頁
酒井一臣「「脱欧入亜」の同床異夢 ―アジア・太平洋地域協力の予兆―」、34-49頁
水田大紀「19 世紀後半イギリスにおける公開競争試験と「精神力」 ―人事委員会と試験官が考える官僚の「資質」について―」、50-61頁
竹内一博「アッティカのデーモスにおける「冠授与の布告」」、62-76頁
鷲田睦朗「<研究ノート>偽り隠す者、サッルスティウス ―『カティリーナの陰謀』の執筆理由―」、77-87頁
書評・新刊紹介88-97頁
後藤敦史「竹中亨著『帰依する世紀末 ドイツ近代の原理主義者群像』」
佐野克司「ベアトリス・アンドレ・サルビニ著 斉藤かぐみ訳『バビロン』」
森本慶太「森田安一編『日本とスイスの交流 幕末から明治へ』」
木谷名都子「藤川隆男編『白人とは何か? ―ホワイトネス・スタディーズ入門―』」
第10回ワークショップ西洋史・大阪 報告要旨99-102頁
- 津田博司(大阪大学大学院)「オーストラリアにおけるアンザック神話の形成 ― C.E.W. ビーンによる戦史編纂を中心に―」
- 安井倫子(大阪大学大学院)「1960 年代、フィラデルフィアにおける平等雇用をめざす黒人の闘い ―アファーマティブ・アクションの再検討のために―」
- 鈴木隆将(名古屋大学大学院)「10・11世紀前半ザクセンにおける女子修道院と帝国司教 ―ヒルヴァルツハウゼンを事例に―」
- 坂本優一郎(京都大学)「18 世紀イギリスにおける投資社会形成とその認識」
- 野村啓介(東北大学)「ボルドー商業会議所と1855 年のワイン格付制定 ―地域権力とワインの「秩序」の関係分析にむけて―」
- 栗原麻子(大阪大学)「古典期アッティカにおける復讐と刑罰」
執筆者紹介(HTML)