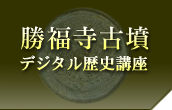

遺跡からみた川西の古代・中世
3.弥生時代後期(1世紀〜3世紀前半)

川西では、加茂遺跡の大集落が急に小さくなり、かわって栄根・下加茂・小戸遺跡などの集落が続くほか、北部まで新たな集落が現われるなど、大きな社会変化がうかがえます。高地性集落の鼓ヶ滝遺跡の存在は社会の変化のなかで、軍事的緊張状態が生まれたことを示唆しています。
大集落の解体
畿内有数の大集落であった加茂遺跡の集落も、弥生時代後期になると急に衰退し、東西二つの小集落に分裂します。この結果、加茂遺跡の集落は、これまでの周辺小集落と同等な大きさになってしまいました。また、このような大集落は、その後営まれることはありませんでした。弥生時代後期の大集落の解体は、畿内全体の傾向で、この地域だけでなく、弥生社会の大きな変動が考えられます。
この原因については、集落内での階層分化が進んだ結果、首長から一般庶民までがおなじ集落に住み続けることの意味が失われたためとみる考えが有力です。これ以後、首長層は一般集落とは異なる場所に居宅を構えたと推定されます。西日本の2世紀末〜3世紀初めの遺跡からは、そうした首長居宅の可能性がある建物区画が見つかり始めましたが、1世紀〜2世紀の遺跡では、まだ確認されていません。
この原因については、集落内での階層分化が進んだ結果、首長から一般庶民までがおなじ集落に住み続けることの意味が失われたためとみる考えが有力です。これ以後、首長層は一般集落とは異なる場所に居宅を構えたと推定されます。西日本の2世紀末〜3世紀初めの遺跡からは、そうした首長居宅の可能性がある建物区画が見つかり始めましたが、1世紀〜2世紀の遺跡では、まだ確認されていません。
住まいの変化

ベッド状遺構を持つ住居(栄根遺跡)
祭り

栄根銅鐸(東京国立博物館蔵)
そのうち栄根銅鐸は、明治44年に栄根字井坂15番地(現加茂1丁目15番地)で、採土作業中に偶然掘り出されました。復元すると高さ114cmにもなる大きなもので、銅鐸の中でも一番最後の型式のものであることから、2世紀頃に造られたと思われます。発見場所が加茂遺跡の崖下ということから、加茂遺跡をはじめ市域南部の人たちが、首長を中心にこの銅鐸を使った祭祀や儀礼をおこなった後にこの地に埋納した可能性が考えられます。
現在、栄根銅鐸は東京国立博物館に、満願寺銅鐸は大阪城天守閣にそれぞれ所蔵され、当館には栄根銅鐸の複製品があります。