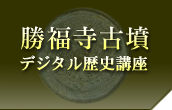

川西市の遺跡紹介
西畦野遺跡(にしうねのいせき)

西畦野遺跡周辺
畦野周辺には、奈良時代に国家の管理下に置かれた牧場があったということが、『日本後紀』大同三年(808)七月の条に「摂津国川辺郡畝野牧を廃す」と書かれていることからわかります。しかし、現在のところは牧場の正確な位置はわかっていません。

発掘調査のようす
ところで、これまで弥生時代の遺跡は市域南部(加茂・栄根遺跡等)を中心に発見されており、最北端の遺跡は鼓ヶ滝遺跡でした。今回の発掘調査によって、西畦野遺跡が市域では最北端の弥生時代の遺跡になりました。南部の栄根遺跡から但馬・丹波地方で造られた土器が出土していることから、当地方との交流が考えられ、北部の遺跡はこうした交流における窓口的な役割を果たしていたと考えられます。
今後の発掘調査により、交流のことや各時代の集落構造が明らかになっていくことと思います。牧場の正確な位置はわかりませんが、一庫大路次川の川原で一面に広がるのどかな田園風景を見ながら、草を食べたり走り回る牧馬の情景を想像するのも楽しいものです。
能勢電鉄畦野駅下車西へ徒歩30分