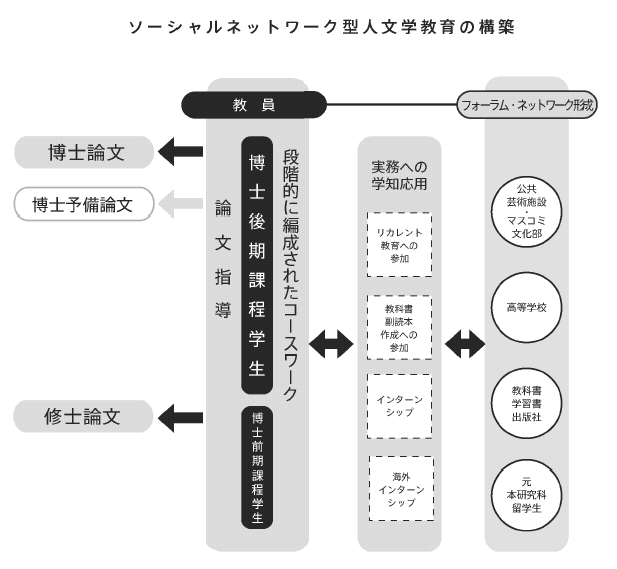|
|
あいさつ
−緒言にかえて−
文学研究科長・演劇学教授
天野文雄
不易と流行のバランスはいつの時代にも求められてきたことであろうが、現代はいずれかというと−というより、圧倒的にというべきかもしれないが−、流行のほうが求められている時代のように思われる。流行すなわち変化であり、また、新しさの追求ということにほかならないが、そうした現代の風潮が、もっぱら不易を固守してきた大学にも及んできている。それはまず、いわゆる大学の大衆化として、戦後まもなく学部において現われたが、近年、それは急速に大学院に波及しつつある。文部科学省の大学支援事業のひとつである「魅力ある大学院教育イニシアティブ」は、まさにそのような潮流を端的に象徴する事業であり、そこでは従来とは異なる新しい大学院のあり方がめざされている。こうして、大学院も確実に流行の時代に入ったことになるわけであるが、さいわいこの支援事業に採択されたわれわれ大阪大学文学研究科がかかげたプログラム「ソーシャルネットワーク型人文学教育の構築」は、専門分野の研究能力に加え、プラスアルファの能力の養成を大きな柱としている。いうまでもなく、それが時代の要請だからである。もっとも、それは一面では、大学院の大衆化という側面を有してもいるのであるが、しかし、それをあまりマイナスとしてとらえるのは、ややかつての大学像にとらわれすぎた見方であろう。歴史が証明しているように、どの時代にも変化はあり、またそれが不可欠でもあったのである。問題は、それがどのような変化なのかということであろうが、その意味で、この1年あまりのわれわれの取り組みは、今後の文学研究科の進むべき道についての貴重な基礎造りだったことになろう。
計画の概要
■ 本事業の大学全体としての位置付け
本研究科は、文学研究科としてはわが国有数の規模を有し、わが国の人文学研究をつねにリードしてきた。現在、大阪大学は、文系の教育・研究のさらなる拡大充実に力を注ごうとしており、そのため全学の研究推進室に<文系分野>および<文理融合分野>の先端的研究のための戦略ワーキングが設置された。本研究科は、人文学教育・研究の全学における中核として、COE研究「インターフェイスの人文学」でも拠点の役割を果たしてきた。また、本研究科と海外の高等教育・研究機関との学術交流は、大阪大学の国際交流の重要な部分を担っている。本研究科には、人文学の教育・研究の拡充に寄せるこうした全学の期待に沿って、資金、人員、施設に関しては、今後も全学の配分基準による従前の措置を約束しており、教育の高度化についてもこうしたリソースを活用することができよう。その上で、特定の事業については必要に応じて総長裁量経費などからの資金交付で支援することも考えられる。
■ これまでの教育研究活動の状況
本研究科では、以前から各専門分野で最先端の研究を発展させるよう指導に努めてきたが、1999年に大学院重点化が行われて以降、部局全体での大学院教育の組織化にも努力している。まず課程博士学位の取得を促進するべく、関連する諸制度を定めた(博士予備論文制度、公開審査など)。また博士前期課程修了後に就職する学生のための就職指導を開始した。2003年からは高度専門職業人養成を見据えた授業科目を設置し、インターンシップの組織化も行っている。2004年度からは「教育支援室」を開設し、教育と就職の支援体制を強化した。さらに2005年度からは各専門分野で年度教育目標を定めることとした。他方で、広域文化形態論、広域文化表現論両講座に三つの学際的な研究会(学生も参加)を組織し、博士後期課程学生の問題意識を活性化するとともに、研究成果の広域的な発信を促している。■ 魅力ある大学院教育への取組
本研究科は、21世紀の世界で人文学を創造的に発展させられるような研究者の育成をめざす。このためには学生が専門分野における学力に限らず、さまざまな能力を身につけるよう促さなければならないが、今回の応募に当たっては特に、本研究科と諸組織との連携活動における現場経験によって学生の視野の拡大、実務能力の涵養と発信力の強化をめざす取組を計画の中心とする。それは就職指導や社会貢献活動と重なる部分もあるが、ここではあくまで博士後期課程の学生を対象とする研究者養成のための教育プログラムの一環としてとらえている。具体的には以下の四つの取組を主な柱とする。
- 芸術系の諸分野で、公共芸術施設、マスコミの文化部門などとの間にフォーラムを組織し、これら諸機関スタッフのリカレント教育、学生のインターンシップ、さらに共同企画などを実施して、「現場」での共同作業を組み込んだ教育システムを形成する。
- 歴史系の諸分野で、高校・予備校教員・出版社員などのリカレント教育事業への参加、高校・大学レベルの教科書、副読本作りへの参加などを通じて、研究成果の要約・解説の訓練を施す。
- 文学語学系の諸分野で、大学レベルの教科書、副読本作りへの参加を通じて、研究成果の要約・解説の訓練を施す。
- 本研究科に留学経験があって現在外国で就業している人々とのネットワークを整備し、ニーズに応じて彼らのもとに学生を時限的に派遣し、教育その他の業務の補助を経験させる。
なお、本研究科は人文学の素養のある高度専門職業人の養成をもうひとつの教育目的としているが、上記の諸取組がこの目的に適うものであることはいうまでもない。
役員
活動概況
(2006年秋現在)
1. 芸術関連機関とのネットワーク形成とインターン、リカレント教育の遂行
アートネットワーク会議(PAN: Praxis, Arts Network)を3月に国立国際美術館において開催。美術、音楽、演劇、映画等関係者約60名が集まり、ネットワークの可能性について議論を交わした。同時にネットワークの参加者の登録も開始した。大学院生を京都国立美術館などに派遣し、実際の業務ならびにその補佐を行なうとともに、インターンなど今後の協力の可能性についても調査を行なった。
2. 中等歴史教育研究会の組織
大学院学生が運営し、京阪神だけでなく北海道、関東、東海、中国、九州の高校・予備校教員も共同研究者として、計4回の研究会を開催したほか、ホームページ・メーリングリストも立ち上げた。それらを通じて、アジア海域史と東南アジア史、近現代の宗教史、日本列島の北方史などの分野で現在の学界動向を踏まえた歴史教育改善の方向性を明らかにした。
3. 理想の教科書像の策定
すでに刊行されているフランス文学史、アメリカ史の教科書については使用者へのアンケート調査、古書店での書き込み等の調査をふまえ、改訂版の方針を策定した。新規のドイツ文学の教科書についても編集方針を定め、院生への役割分担を終えて、出版元との交渉や、一部、印刷の段階に入っている。
4. 国際連携ネットワーク構築と海外インターンシップ
旧留学生のメールアドレスの整備を終え、メールマガジン編集方針もほぼ策定されており、そのための原稿も集まった。また、旧留学生が多い韓国(ソウル)にて同窓会の立ち上げに関係者が参加し、協力体制を確立させた。日本人学生の海外インターンシップ先として米国アイヴィーリーグを中心に選定のための基礎的リサーチを行った後、公募選考によりペンシルバニア大学へ2名の院生を送り出している。