東洋史学研究室の歴史(2019.6.12.改訂)
- 1948年9月、大阪大学に法文学部が創設されました。東洋史は「科目」のみで、「講座」は未設立。(「講座」とは学校教育法に基づく国立大学の教育・研究単位のことです)
- 1949年5月、学制改革に伴って法文学部は文・法・経3学部に独立し、文学部に東洋史学講座が開設され、以下のスタッフで研究活動が開始されました。
- 教授:桑田 六郎(東西交渉史、東南アジア史専攻。1956年3月退官。1988年逝去)
- 助教授:守屋美都雄(中国古代史専攻。1966年、文学部長在任中に逝去)
- 助手:岡崎 精郎(内陸アジア史・西夏史専攻。追手門学院大学に転出。1993年逝去)
- 以来、教授は以下のように引き継がれました。いずれも学界で指導的立場にあり、世界的にも著名な研究者です。
- 守屋美都雄(1957年、助教授より昇任)
- 山田 信夫(北アジア・中央アジア史専攻。1967年、助教授より昇任。1983年3月退官。京都女子大学教授。1987年4月逝去)
- 斯波 義信(中国宋代史専攻。1979年、助教授より昇任。1986年4月、東京大学東洋文化研究所に転出。大阪大学名誉教授。東洋文庫理事。2017年、文化勲章を受章)
- 濱島 敦俊(中国明清史専攻。1987年、助教授より昇任。2001年3月退官。大阪大学名誉教授。現・曁南国際大学(台湾)教授)
- 森安 孝夫(イスラム化以前の内陸アジア史、東西文化交流史専攻。1994年、助教授より昇任。2012年3月退職。大阪大学名誉教授。現・神戸市外国語大学客員教授)
- 片山 剛(華南社会経済史(14~20世紀)専攻。1996年、助教授より昇任。2018年3月退職。大阪大学名誉教授。)
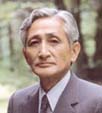 1979年4月、アジア諸民族史講座が開設され、初代教授には山田教授(右写真)が就任しました。それに伴い、斯波助教授が空席となった東洋史学講座教授に昇任しました。この結果、長年の希望であった2講座化が実現しました。
1979年4月、アジア諸民族史講座が開設され、初代教授には山田教授(右写真)が就任しました。それに伴い、斯波助教授が空席となった東洋史学講座教授に昇任しました。この結果、長年の希望であった2講座化が実現しました。- 歴代の教養部教授には、大学院併任教授あるいは非常勤講師として、文学部東洋史学研究室の教育にご支援をいただいてきました。
- 潮田富貴蔵(中国歴史地理学専攻。1972年2月逝去)
- 布目 潮渢(中国唐代史専攻。2001年1月逝去)
- 海野 一隆(中国歴史地理学専攻。2006年5月逝去)
- 谷口規矩雄(中国明清史専攻。大阪大学名誉教授)
- 1994年4月、教養部が廃止され、「全学共通教育機構」(現在の全学教育推進機構)が成立しました。これに伴って教養部所属の人文系教官は文学部の関連講座に所属替えとなり、東洋史担当の教授・助教授各1名は、それぞれ東洋史学講座・アジア諸民族史講座に所属することとなりました。
- 1995年4月、大阪大学文学部の組織が改編されて「大講座制」に移行したのに伴い、東洋史学講座・アジア諸民族史講座は、西洋史の2講座と共に「世界史学講座」を形成しました。しかしながら、利用史料読解の教育訓練を考慮して、学部学生の専攻は従来通り「東洋史学専攻」とし、研究・指導体制も東洋史学研究室・西洋史学研究室という研究室単位で存続しています。
- 1998年4月、大学院大学化に伴ない、世界史講座は他の6講座と共に「文化形態論専攻」へ改組されました。各教官は大学院文学研究科に所属替えし、学部教官を併任する形となりました。
- 2004年4月、独立行政法人化されました。
- 下記の諸先生方が助手/助教として在任されました。
- 杉本 憲司(中国考古学専攻。仏教大学名誉教授)
- 間野 英二(中央アジア史・西アジア史専攻。京都大学名誉教授)
- 中村 哲夫(中国近代史専攻。現・華東師範大学客座教授)
- 森川 哲雄(北アジア史・モンゴル史専攻。九州大学名誉教授)
- 本田 治(中国宋代史専攻。現・立命館大学特任教授)
- 堀 直(中央アジア史専攻。甲南大学名誉教授)
- 松田 孝一(モンゴル帝国史専攻。大阪国際大学名誉教授)
- 萩原 守(モンゴル近世史・清朝史専攻。現・神戸大学教授)
- 沈 中琦(日本近代史専攻。2005年1月逝去)
- 太田 出(中国清代史専攻。現・京都大学教授)
- 田口 宏二朗(中国明代史専攻。現・大阪大学教授)
- 杉山 清彦(大清帝国史・東北アジア史専攻。現・東京大学准教授)
- 山内 晋次(アジア海域史・日本古代史専攻。現・神戸女子大学教授)
- 坂尻 彰宏(中央アジア史・敦煌学専攻。現・大阪大学准教授)
- 赤木 崇敏(中央アジア史・敦煌、吐魯番学専攻。現・東京女子大学准教授)
- 岡田 雅志(東南アジア史。現・防衛大学校准教授)
- 伊藤 一馬(中国宋代史。現・大阪大学招へい研究員)
- 歴代の先生方の薫陶を受けて学位を取得したOB・OGが、現在、研究者として学究活動に邁進しています。近年だけでも下記の方々が研究職に就き、学界で活躍しています。
- 長井 千秋(中国財政史専攻。平成四年 [1992年] 博士後期課程単位取得退学。平成九年 [1997年] 博士号取得。現・愛知大学准教授)
- 中村 淳(モンゴル時代史専攻。平成九年 [1997年] 博士後期課程修了,博士号取得。現・駒澤大学教授)
- 松川 節(モンゴル時代史専攻。平成十年 [1998年] 博士後期課程修了,博士号取得。現・大谷大学教授)
- 松井 太(モンゴル時代史・中央アジア史専攻。平成十一年 [1999年] 博士後期課程修了,博士号取得。現・大阪大学教授)
- 石川 亮太(近代朝鮮経済史専攻。平成十五年 [2003年] 博士後期課程修了,博士号取得。現・立命館大学教授)
- 林 淑美(台湾史専攻。平成十五年 [2003年] 博士後期課程修了,博士号取得。元・名古屋商科大学准教授)
- 上谷 浩一(中国古代史専攻。平成十六年 [2004年] 博士後期課程修了,博士号取得。元・大阪体育大学教授)
- 佐藤 貴保(西夏史専攻。平成十六年 [2004年] 博士後期課程修了,博士号取得。現・盛岡大学准教授)
- 蓮田 隆志(ベトナム史専攻。平成十七年 [2005年] 博士後期課程単位取得退学。平成十八年 [2006年] 博士号取得。現・立命館アジア太平洋大学准教授)
- 横山 政子(中国近現代史専攻。平成十六年 [2004年] 博士後期課程単位取得退学。平成十八年 [2006年] 博士号取得。現・志學館大学教授)
- 笠井 幸代(トルコ文献学専攻。平成十三年 [2000年] 博士前期課程修了。平成二十年 [2008年] 博士号取得[ベルリン自由大学]。現・ベルリン科学アカデミー・トルファン研究所研究員)
- 大坪 慶之(清末政治史・外交史専攻。平成二十年[2008年]博士後期課程修了,博士号取得。現・三重大学准教授)
- 山本 明志(モンゴル時代史専攻。平成二十一年[2009年]博士後期課程単位取得退学。平成二十四年 [2012年] 博士号取得。現・大阪国際大学准教授)
- 向 正樹 (モンゴル時代史専攻。平成十九年[2007]年博士後期課程修了, 博士号取得。現・同志社大学准教授)
- 中田 美絵 (唐代中国史・中央ユーラシア史専攻。平成十九年[2007]年博士後期課程修了, 博士号取得。現・京都産業大学准教授)
- 鈴木 宏節 (中央ユーラシア史・古代トルコ民族史専攻。平成二十年[2008]年博士後期課程修了, 博士号取得。現・神戸女子大学准教授)
- このような歴史を経て、現在は荒川、桃木、松井、田口、計4名の教員が、日々研究と学生指導にあたっています。
※『東方学会報』No.97の「研究室便り」に、森安名誉教授による
「大阪大学大学院文学研究科におけるアジア研究」が掲載されました。あわせてご覧下さい。