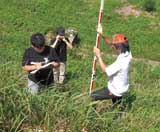
人文地理学とは、人間と環境・地域との関係を考察し、事象の空間的な分布がどのようなプロセスで形成されるのか、その成因を探究する学問分野です。そこでの主なキーワードには、環境・地域・空間・景観・場所・ネットワーク・フローなどがあり、多様な視点を持つのがこの分野の特徴です。人文地理学専修では、人間─環境関係、人間─空間関係をさまざまな角度から分析・考察しています。講義を通じて先行研究の視点や、方法論・手法などを理解し、演習や実習では、論文講読・フィールドワーク・データ解析・図表作成・プレゼンテーションなどを体験し、知識を深め、技術を習得します。人文地理学専修は1995年に講座化されましたが、大阪大学には1950年代以来、人文地理学者が在籍し、地図研究の蓄積があります。また、近年では都市・農村研究の蓄積もあり、多面的な研究と教育を行ってきています。間口が広い専修であるといえるでしょう。
入口がたくさんあるのが人文地理学です! 人文地理学では、人間と地域・環境・空間・場所との関係を、現地調査を重視しつつ、論理的・分析的に探究します。多くのことに関心のある人を待っています。 人文地理学では、調査・研究の方法論や技法の理解、論理的な思考、そして現地調査などの経験を重視した教育を行い、地域や空間で展開する問題を構造的に捉える視点を養います。
教員紹介
教授 佐藤 廉也
文化地理学/環境地理学 環境への文化的適応・地域文化の形成に関する研究、アジア・アフリカ地域研究 |
- メッセージ
- アフリカ(熱帯林・サバンナ)、中国内陸部(半乾燥地域)、ラオス(熱帯モンスーン)などでフィールド調査を続けながら、地域文化の形成や環境への文化的な適応をめぐる諸問題について研究しています。地理学ではさまざまな専門分野にまたがる横断的研究が求められ、「ブリッジ・サイエンス」と呼ばれることもあります。地理学を学ぶ上で大事なことは、世界の多様性に対する好奇心と、それを合理的に理解・説明したいという欲求です。世界の文化的多様性はどのようにして形成されるのでしょうか。一緒に考えてみませんか。
2024年 6月更新
教授 大呂 興平
 おおろ こうへい おおろ こうへい経済地理学/食と農の地理学 農業および農産物貿易の動態に関する地理学的研究 研究関心:牧畜、牛肉貿易、wagyu、離島、オセアニア |
- メッセージ
- 地理学は、地表面で起きている現象が、なぜそこで、どのように起きているのかを探求する学問です。私自身は日本の離島やオーストラリア、南太平洋の島々などの縁辺に身を置き、その産業や社会に関する研究を行ってきました。でも、私たちの身の回りでも、実にさまざまな「現象」や「問題」が起きています。現場を歩き、問いを立て、人々の話に耳を傾けながら現象を深く理解する。そうした知的作業は、皆さんが人生をより確かに生きるための礎になるはずです。そんな経験をともにできることを楽しみにしています。
2025年 4月更新
